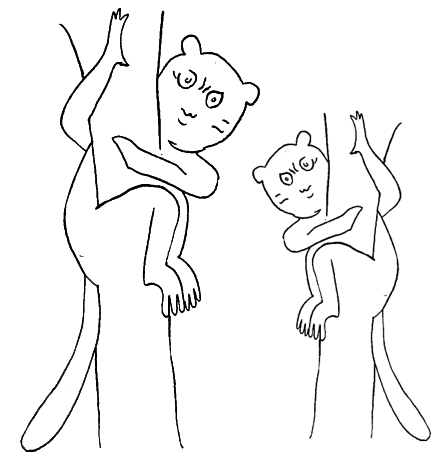
実証主義者の冷めた植民地主義
Posivivist's Cool
Colonialism
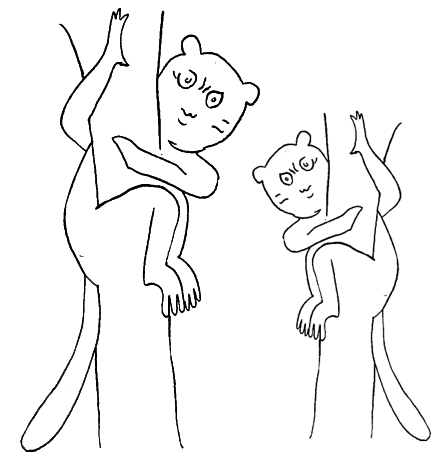
☆ こ こで引用するのは、伊藤幹治(1930-2016)先生の「南島研究回想」『国立民族学博物館研究報告』38(1): 63– 89 (2013)からのものである。柳田國男の最後の弟子ともいえる伊藤先生は、師匠たちの世代の日琉同祖論を批判しながら、長く「返還」前後の琉球沖縄およ び南西諸島の調査に専念されてこられた。戦前の日本軍人による琉球人に対する非人道的な行為から、伊藤先生が現地「調査」を拒否されたことや、ヤマトに対 する琉球人のエスニックアイデンティティの覚醒なども考察している。しかし、伊藤先生のこの回顧の最後には「こうした沖縄社会に潜在しているエスニッ ク・アイデンティティもしくはこれをイデオロギー化したエスニック・ナショナリズ ムに十分留意しながら,沖縄の島々の民俗社会とその文化を,これまで以上に冷めた 目で観察をつづけ,実証的研究をつづけることが求められよう」と括られている(伊藤 2013:87)。
☆ 伊藤先生は素朴な日琉同祖論の論者ではないが、しかしながら、先達たちの研究の蓄積を継承することは吝かではない。上の文章につづいて、再び「冷めた心」 と「ひろい視野」から調査に向かうべきと次のように記されている。「そして,沖縄(ウチ ナー)の研究者も日本(ヤマト)の研究者も,戦前から日琉同祖論を立証するために 積み重ねられてきた膨大な業績と謙虚に向きあい,これをこれまで以上に冷めた心で 再吟味することが求められよう。さらに,わかい世代の沖縄研究者は,かつて社会人 類学者の馬淵東一がオナリ神の信仰と習俗をめぐって,沖縄とインドネシア,オセア ニアの親族体系の比較をこころみたように(馬淵 1988: 15–112),沖縄の民俗社会と その文化をよりひろい視野から検討することが求められることになろう」(伊藤 2013:87)。
★ リンダ・トゥヒワイ・スミスは「脱植民地化の方法論」の冒頭(1999: 1)で「『研究』という言葉自体が、先住民の言語の中で最も汚れた言葉の一つであ る」と記している。脱植民地性が主張される沖縄=琉球の社会的政治的文脈の中で、調査する側の「冷めた心」 と「ひろい視野」は果たしてどのような意味をもつのだろうか。
| 3.2 日琉同祖論の脱構築 |
|
| 「戦後,民族学者が沖縄に関心を寄せるようになったのは,柳田国男が
『沖縄文化叢
説』を上梓した 3 年後のことである。日本民族学協会(現・日本文化人類学会)は,
1950 年 11 月に機関誌『民族学研究』第 15 巻第 2 号で「沖縄研究特集」を編集して
いる。これを企画したのは,歴史民族学から文化人類学に転じた石田英一郎であっ
た。 ■ 戦後まもなく石田は,柳田国男が『山島民譚集』(柳田 1997a)で取りあげた日本(p.71) の河童駒引伝承に注目し,これをユーラシア大陸の類例と比較して,その文化的系譜 関係を追求した『河童駒引考』(石田 1970)を上梓した。そして『民族学研究』が再 刊されると,編集者として献身的な努力を重ね,岡正雄(歴史民族学),江上波夫(東 洋史学),八幡一郎(考古学)を招いて,座談会「日本民族=文化の源流と日本国家 の形成」(第 13 巻第 3 号,1949 年)の司会をつとめるほか,「シャマニズム研究」(第 14 巻第 1 号,1949 年),「ルース・ベネディクト『菊と刀』の与えるもの」(第 14 巻 第 4 号,1950 年)などの特集を企画している。「沖縄研究特集」もこうした企画のひ とつであった。この特集号に柳田国男も日琉同祖論を立証しようとした「海神宮考」 (1997b)を寄せているが,編集方針をめぐって注目したいことがふたつある。 ■ひとつは,石田英一郎が「沖縄研究の成果と問題―巻頭のことば」のなかで,従 来の日琉同祖論にとらわれず,よりひろい視野から研究をすすめる必要性を強調して いることである。 ■ 石田は戦前の沖縄研究を評価し,日本と琉球の親近性を十分に認めたうえで,日本 と琉球の「同祖同系を強調するのあまり,沖縄人自身のエートノスの全体的把握や非 日本的な要素の究明」が見落とされ,誤った解釈が残されていないかを危惧してい る。将来の沖縄研究はよりひろい視野に立って,民族学的・考古学的・言語学的・人 類学的研究を必要とする,と述べている(石田 1950: 87)。 ■ もうひとつは,石田に実質的な編集を託された沖縄出身の金城朝永が,「編集後記」 のなかで従来の日琉同祖論を脱構築し,沖縄文化を日本文化と切り離して,これを 「ひとつの独立した単位」として把握することを強調していることである。金城はつ ぎのようなことを述べている。 ■ 敗戦を機に転換期を迎えた沖縄研究は,あたらしい視点を構築する必要がある。そ の前提として「沖縄の文化を,日本文化の中の変り種と見做し,主としてその中から 日本文化の類似点のみを拾い出して比べ合わせるが如き,従来の態度から脱却」しな ければならない。そして「琉球文化なるものを,一つの独立した単位として取扱い, 所謂大和文化の従属的地位から解放して,それに含まれている種々相を,今少し精密 に分析して,我が国のみならず,広く遠く隣接周辺の諸邦との比較をも試みてみるこ と」が必要だというのである(金城 1950: 148)。 ■ この提言は,石田の問題提起をより先鋭化した言説である。日本文化と琉球文化の 親近性をふまえ,琉球を「日本の古い分家」とみなした柳田の日琉同祖論と対峙し て,金城は琉球文化を日本文化と切り離す脱日琉同祖論を提起しているからである。 そこには,沖縄人(ウチナーンチュ)しての金城のエスニック・アイデンティティに(p.72) 根ざした心情を読み取ることができる。金城は日本の敗戦をまたとない好機ととら え,従来の日琉同祖論を脱構築しようとしたのである。 ■ 石田英一郎や金城朝永の提言のほかに,その 2 年後の 1952 年に,社会人類学者の 馬淵東一も「沖縄研究における民俗学と民俗学」を発表し,従来の日琉同祖論をなか ば肯定しながら,つぎのような琉球文化亜型論を提唱している。 ■ これまでの沖縄文化の研究は,主として日本との関連をたどる方向でおこなわれて きた。日本と沖縄の文化がいかなる他の文化と比べても,これほど共通の特徴を示す ものがないからである。そこに日琉文化ともいうべきひとつの文化の型が考えられる が,日本文化と沖縄文化のあいだには,内部的な分岐的変化や異質の文化要素の内在 もしくは受容の度合いなどの点でかなりのひらきがあるので,沖縄文化という亜型の 存在を考えぬわけにはいかない,というのである(馬淵 1974a: 517–520)。 ■ なお,馬淵は 1971 年に発表した「沖縄民俗社会研究の展望」のなかで琉球種族亜 型論を提起し,日本と琉球の「種族」を混成種族ととらえ,日本と沖縄の種族をそれ ぞれ同じ種族のなかのふたつの亜種族と推定している(馬淵 1974b: 529–533)。馬淵 の種族とは,文化系統を同じくするエスニック・グループのことである。馬淵は日琉 双方の種族を混成種族のなかのふたつの亜種族とみなしたわけである。 ■ 戦後の日本文化と琉球文化の比較研究は,すくなくとも 1950 年代前半から 70 年代 前半にかけては,柳田国男をはじめとする沖縄研究の先覚者たちが立証しようとつと めてきた日琉同祖論と,それを軌道修正した馬淵東一の琉球文化亜型論や琉球種族亜 型論と真摯に向きあうことが求められていたのである」。 |
(伊藤 2013:70-72) |
| 慶留間での調査拒絶 |
|
| 「1960 年 3 月,沖縄本島南西洋上の慶良間諸島の慶留間島に滞在中のことである。 宗家(ムートヤー)の老人から,戦時中この島に駐留していた軍人と同類のヤマトンチュ(日本人)と決めつけられ,協力を拒まれたことがあった。こうして, ヤマトン チュというアイデンティティの確認を迫られたときの,あの衝撃をいまでも忘れるこ とができない。戦争末期の 1945 年 3 月の沖縄戦直後に,その老人の娘さんがヤマト ンチュの軍人に自決を強いられて亡くなったということであった(伊藤 2011: 60)」 | (伊藤 2013:79-80) |
| 8 おわりに―揺らぐアイデンティティ |
|
| 「1957 年から 72 年にかけて,わたしが訪れた南西諸島は,沖縄の島々が大半を占め
ている。その沖縄社会では,現在普天間飛行場の移設,米軍の新型輸送機の配置,米
軍兵士による女性暴行,尖閣諸島の施政権などをめぐって,政治・社会・安全保障に
からむさまざまな問題が起こっている。
■いまから 18 年ほど前のことになるが,戦後 50 年という節目を迎えた 1995 年 9 月, 沖縄で衝撃的な事件が起きたことがある。沖縄本島における米軍兵士による少女暴行 事件である。このことに苦慮した当時の沖縄県知事は,「琉球王国の復活」という隠 喩で沖縄の独立を示唆したといわれている(鈴木 1997: 213)。この言説には,「沖縄 県民」としてのローカル・アイデンティティというよりは,むしろ「沖縄人」(ウチ ナーンチュ)としてのエスニック・アイデンディティに根ざしたエスニック・ナショ ナリズムがかいまみられる。そこに琉球王国以来の共通の歴史,共通の文化,共通の 言語,共通の感覚と感情を共有する「沖縄人」としての自意識が鮮明に表象されてい るからである。 ■日本民族学会の機関誌『民族学研究』の編集委員会は,こうした沖縄の現実を注視 したのであろうか。翌 96 年に「沖縄の特集」(第 61 巻第 3 号)を企画している。編 集主任の川田順造は,「『琉球』研究を求めて」のなかで,この特集が琉球の政治的統(p.86) 合以後のヤマト(大和)の琉球研究を「沖縄人研究者」の立場からとらえ直し,対象 とされる社会とその文化のひろがりと研究の視野の取り方を,将来の研究に向けてさ ぐることを意図したと述べている(川田 1996: 436)。 ■こうした編集委員会の求めに応えて,沖縄人研究者の比嘉政夫と津波高志が寄稿し ている。比嘉は「琉球列島文化研究の新視角」を寄せて従来の日琉同祖論を視野に入 れ,日本文化と琉球文化の同質性と異質性に言及しているが(比嘉 1996: 437–448), 津波は「対ヤマトの文化人類学」を寄稿し,そのなかで「対ヤマト意識」という概念 を提示して日琉同祖論の再考をうながしている。 ■津波によると,対ヤマト意識とは,奄美の島々から八重山の島々の人びとにおよぶ, ヤマト(日本)とみずからのあいだに刻み込まれた心の刻み目,文化としての刻み目 のことで,この刻み目がみずからを「ドミナントな日本文化の担い手ではないと位置 づける」ことであるという。そして,津波はヤマトと非連続の「文化それ自体の刻み 目としての対ヤマト意識を共有する領域」を「『沖縄』文化領域」とよんでいる(津 波 1996: 457–458)。 ■これは別にあたらしい言説ではない。1970 年代はじめの沖縄の「本土復帰」前後 に,一部の沖縄独立論者が日琉同祖論を否定して,「沖縄人」を「日本人」の対立概 念としてとらえ,沖縄人が日本人に対してもちつづけてきた「意識の切れ」を,沖縄 の土着思想の核とする考え方を打ち出していたからである(新川 1970: 22)。 ■こうした「意識の切れ」を津波は「心の刻み目」「文化としての刻み目」と言い換 えたに過ぎない。津波の心情を理解するのにやぶさかではないが,彼に求められてい るのは,「対ヤマトの文化人類学」を,どのようなかたちで構築するかということで あろう。これができなければ津波の言説は,沖縄独立論者の主張をなぞらえた日琉同 祖論に対する単なるアンチテーゼに過ぎなくなろう。 ■なお,津波の「「沖縄」文化地域」という概念も無条件に首肯しがたい。一五世紀 以降,琉球王国は版図を拡大して奄美の島々や宮古・八重山の島々を支配したので, 津波の「沖縄」とはかつての琉球王国が領有していた土地ということになる。津波は こうした島々を「相対的に個性的で対等な位置にある」と理解したいと述べている が,宮古や八重山の島々の民俗社会とその文化は,沖縄本島のそれとかならずしも一 様ではない。しかも,これらの島々はいまもなお沖縄のなかで「周縁」に位置づけら れているからである(伊藤 2002: 168–169)。 ■津波の「対ヤマトの文化人類学」は,かつての金城朝永の脱日琉同祖論をふまえ て,日本(ヤマト)に対する沖縄(ウチナー)の「異化」を改めて強調した言説に過(p.87) ぎない。そこに沖縄人(ウチナーンチュ)としての強烈なエスニック・アイデンティ ティが表象されているからである。こうした言説は,本土復帰以来の沖縄の人びとが 直面している政治=社会状況と決して無縁ではないが,将来の沖縄研究の方途を明示 することが津波に課せられた重い課題になろう」。 |
(伊藤 2013:85-87) |
★ 認 識論的植民地主義(epistemological colonialism)
| Epistemological
colonialism is the imposition of a dominant knowledge system (typically
Western) that marginalizes, devalues, or erases other forms of
knowledge, such as indigenous or non-Western epistemologies. This
process establishes a hierarchy where Western knowledge is considered
the universal standard and is reinforced through institutions like
universities and governments. As a result, local knowledge is often
seen as less valid and is undermined, leading to a "coloniality of
knowledge" that continues to shape power relations even after formal
colonialism ends. |
認識論的植民地主義とは、支配的な知識体系(典型的には西洋の)を押し
付け、先住民や非西洋の認識論といった他の知識形態を境界化、軽視、あるいは抹消する行為である。この過程で西洋知識が普遍的基準と見なされる階層構造が
確立され、大学や政府といった制度を通じて強化される。その結果、地域の知識はしばしば正当性が低いと見なされ、弱体化される。これにより「知識の植民地
性」が生じ、形式的な植民地主義が終わった後も権力関係を形作り続けるのである。 |
| Core components and impacts |
中心的な構成要素とインパクト |
| Knowledge hierarchy: A central tenet is the creation of a hierarchy where Western science is positioned as the most legitimate and objective form of knowledge, while other knowledge systems are often dismissed as "traditional," "local," or "superstitious". Institutional dominance: This hierarchy is maintained through institutions like universities, research bodies, and international organizations that often operate within a framework that privileges Western knowledge systems. This can shape funding, research agendas, and policy-making. Marginalization: The dominance of one system leads to the marginalization of non-Western voices and perspectives. This can mean that alternative solutions to problems are overlooked or dismissed. Harm to individuals and communities: Epistemological colonialism can cause "epistemic harm" by undermining the ability of colonized peoples to be both producers and receivers of knowledge. For example, the medical practices of indigenous peoples may be dismissed as witchcraft, or they may be seen as incapable of understanding their own history or world. Cultural and political impacts: The propagation of the colonizer's worldview through this process can have profound effects, such as the destruction or forced adaptation of indigenous ways of life and the imposition of Western concepts of the nation-state and capitalism. |
知識の階層構造: 中核的な理念は、西洋科学を最も正当で客観的な知識形態と位置付け、他の知識体系を「伝統的」「地域的」「迷信的」と軽視する階層構造の構築である。 制度的優位性: この階層構造は、大学・研究機関・国際機関といった組織によって維持される。これらの組織は西洋知識体系を優遇する枠組み内で活動することが多い。これは 資金調達、研究課題設定、政策決定に影響を与える。 周縁化: 一つの体系の優位性は、非西洋的な声や視点を周縁化する。これにより、問題に対する代替的な解決策が見過ごされたり、軽視されたりする可能性がある。 個人とコミュニティへの害: 認識論的植民地主義は、被植民地の人々が知識の生産者かつ受容者となる能力を損なうことで「認識論的害」を引き起こす。例えば、先住民の医療行為は妖術と して軽視されたり、先住民が自らの歴史や世界を理解する能力を持たないと見なされたりする。 文化的・政治的影響: このプロセスを通じて植民者の世界観が広まることは、先住民の生活様式の破壊や強制的な適応、国民や資本主義といった西洋的概念の押し付けなど、深刻な影 響をもたらす。 |
| Historical and contemporary
examples |
歴史的および現代の事例 |
| Education systems: Colonial powers established educational systems that promoted their own languages and knowledge while devaluing local languages and modes of thought. Research practices: Even in modern times, research can reflect epistemological colonialism. For example, an archaeologist's desire to excavate a burial ground for its "scientific value" can override the wishes of the local community that views the site as a sacred place of memory. International organizations: Organizations like the OECD promote a neoliberal vision of education that can be neocolonial in its impact, pushing Global North epistemologies at the expense of those from the Global South. |
教育制度: 植民地支配国は、自国の言語や知識を推進する一方で、現地の言語や思考様式を軽視する教育制度を確立した。 研究慣行: 現代においても、研究は認識論的植民地主義を反映しうる。例えば、考古学者が「科学的価値」を求めて埋葬地を発掘しようとする欲望は、その場所を聖なる記 憶の場と見なす地域社会の意思を無視しうる。 国際機関: OECDのような組織は、新自由主義的教育ビジョンを推進する。その影響は新植民地主義的であり、グローバル・サウス(南半球諸国)の認識論を犠牲にし て、グローバル・ノース(北半球諸国)の認識論を押し付ける。 |
| Google AI |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099