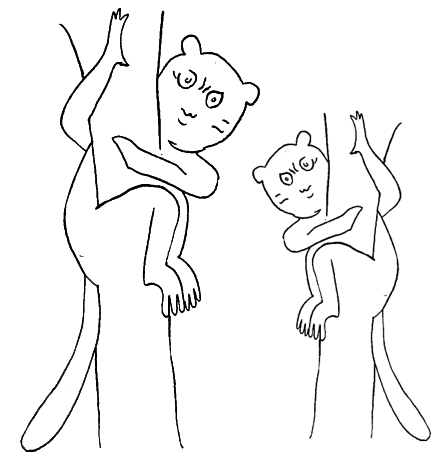
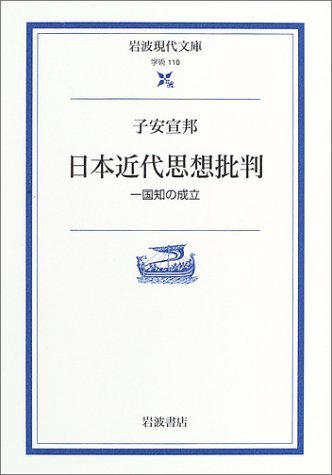
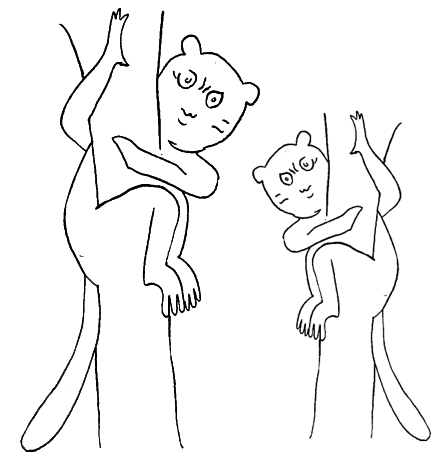
帝国日本の支配的言説
Dominant academic
discourses of the Japanese Empire
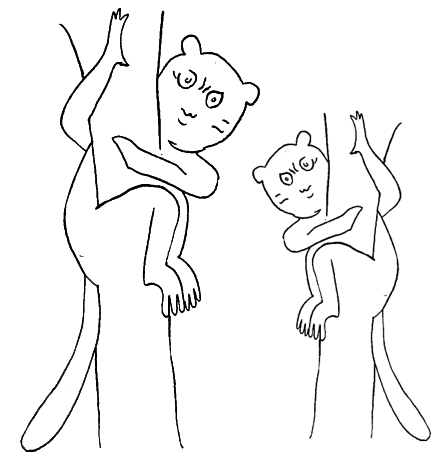
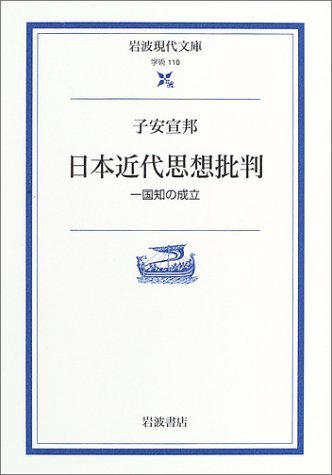
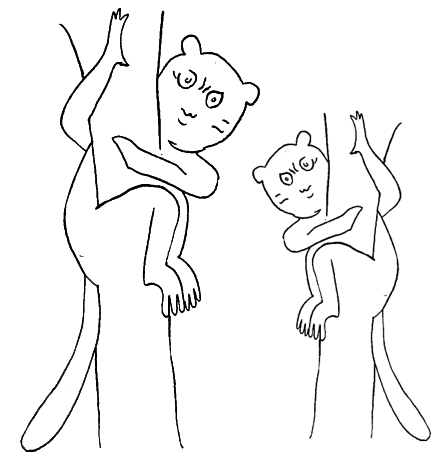
☆子安宣邦(こやす・のぶくに)『日本近代思想批判:一国知の成立』岩波書店、2003年の書肆による書誌紹介
| 本居宣長,平田篤胤,伊藤仁斎,荻生徂徠など江戸思想家のテクストを徹底的に読み込み,日本思想史の新局面を開いてきた子安宣邦氏は,その後近代日本の言説研究へと領域を拡大しました. |
|
| その端緒になったのは,1996年に刊行された『近代知のアルケオロジー』です.本書はその『近代知のアルケオロジー』を改題・増補したものですが,近代日本思想史の批判的研究へと離陸するにいたった著者の基本的な論点がここに収められています. | |
| このときのタイトルにいう「知のアルケオロジー」とは言うまでもなく,ミシェル・フーコーが提起した言説の分析方法です.起源や連続性によって歴史をたどるのではなく,起こったことを固有の状態のままにおいて,そのことが可能になった歴史的な前提を掘り起こそうとする方法です.子安氏は丸山真男のいう「歴史意識の古層」という考え方を批判的に考察しながら,フーコーの「知のアルケオロジー」に強い示唆を受け,近代日本の言説を分析しました. |
・知の考古学 |
| 本
書で指摘される大きな論点は,柳田民俗学の言説を成立させているものについてです.柳田民俗学は外部の視線によって成立する民族学より内的視線によっての
み成立する民俗学が優越するとする「一国知」であり,その展開によって「国民」の創出を意図していたことを追及します.さらに,一国言語学としての国語
学,他国の問題をその国の者に代わって日本の内的視線によって述べるという一国知的方法によって行われた支那学,第二次大戦を画期とする日本おける「近
代」をめぐる議論,戦争資料館のように歴史の表象化が死者を沈黙させるパラドクスなどを考察し,近代日本の言説の基盤にある根本的な問題を批判します. |
|
| 民
俗学,支那学,国語学,倫理学など,近代日本の学問的言説が,「帝国日本の支配的言説」であることを徹底的に暴き出した本書は,日本の近代を考察するとき
に避けて通れない議論を提起しています.日本人が築き上げた近代の学問が最初から含みもっていた前提を掘り起こしている本書を参照すれば,ナショナリズム
をめぐる問題やアジア認識の問題などを考察する際に,感情的・皮相的な議論に陥らず,本当の意味で問題に向き合えるのではないかと思われます.まさに日本
の近現代を考えるための基本文献です. |
|
| https://www.iwanami.co.jp/book/b255741.html |
|
| 近代知のアルケオロジー : 国家と戦争と知識人 / 子安宣邦著, 東京 : 岩波書店 , 1996.4 | |
| 1. 一国民俗学の成立 |
|
| 2. 近代知と中国認識:支那学の成立をめぐって |
|
| 3. 国語は死して日本語は生まれたか |
|
| 4. 日本の近代と近代化論:戦争と近代日本の知識人 |
|
| 5. 隠蔽と告発との間:戦争の記憶と戦後意識 |
|
| 6. 書かれたものと書きえぬこと:歴史表象と死者の記憶 |
|
| 子安宣邦(こやす・のぶくに)『日本近代思想批判:一国知の成立』岩波書店、2003年 | |
| 1. 一國知の成立 |
|
| 1.1 一国民俗学の成立 |
|
| 1.2 「一国民俗学」批判とはなんであったか |
|
| 1.3 国語は死して日本語は生まれたか |
|
| 2. 他者への視線 |
|
| 2.1 近代知と中国認識:支那学の成立をめぐって | |
| 2.2 日本思想史の成立とイスラム世界:和辻哲郎と大川周明 |
|
| 3. 近代と近代主義 |
|
| 3.1 日本の近代と近代化論:戦争と近代日本の知識人 | |
| 3.2 近代主義の錯誤と陥穽:丸山真男の近代 |
|
| 4. 歴史表象と記憶 |
|
| 4.1 隠蔽と告発との間:戦争の記憶と戦後意識 | |
| 4.2 書かれたものと書きえぬこと:歴史表象と死者の記憶 |
|
| 4.3 誰が維新を語るのか |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099