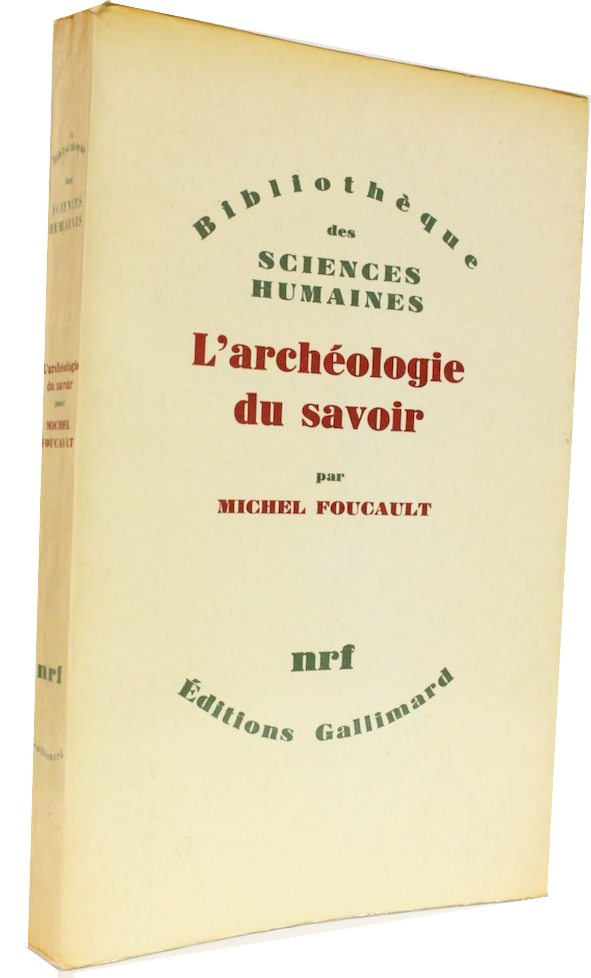
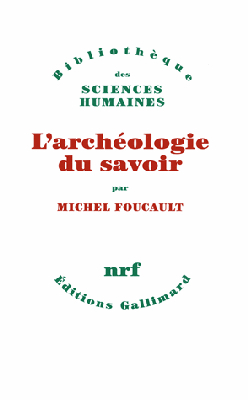
フーコー『知の考古学』ノート
L'Archéologie
du savoir per Michel Foucault
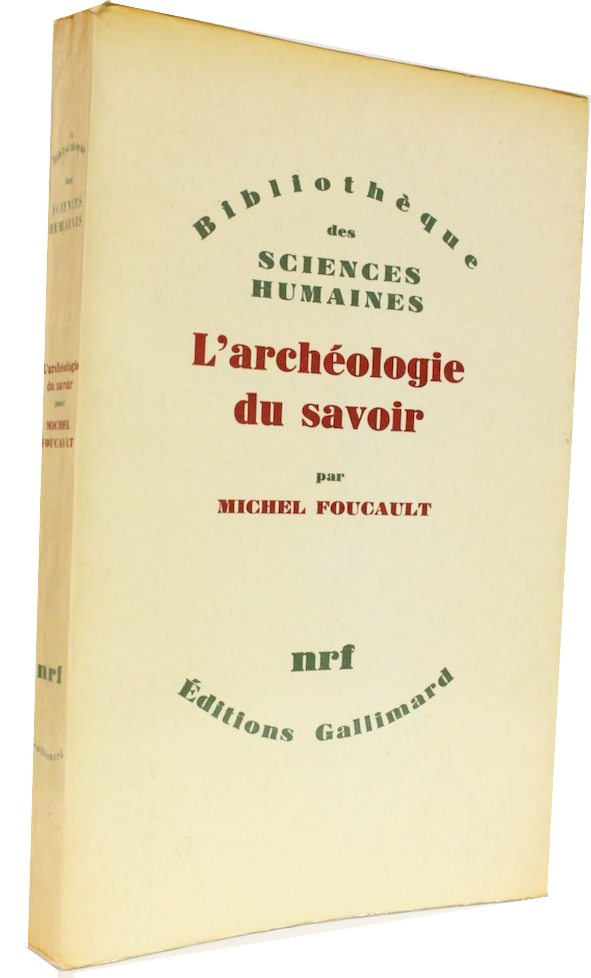
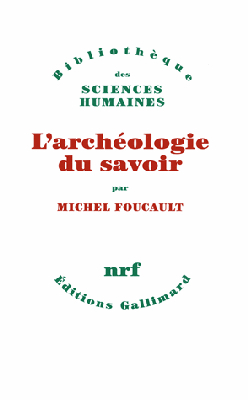
ミシェル・フーコーに よる『知の考古学』(L'archéologie du savoir, 1969)は、主体である個人の意識の下に作用する規則に従い、ある時代と領域で用 いられる言語と思考の境界を決定する可能性の概念体系を定める思考(エ ピステーム)と知識(言説形式)のシステムについての方法論と歴史学に ついての著作である。現代の思想史研究は、歴史的世界観の変遷に関わるものであるが、結局のところ、綿密な検証のもとに崩れ去る物語の連続性に依存している。思 想史は、広範に定義された知識様式の間の不連続点を示すが、それらの既存の知識様式は、歴史 的な言説の複雑な関係の中の個別の構造ではない。言説は不連続性と統一的なテーマによって定義される複雑な関係(言説的、制度的)に従って 出現し、変容する。
★歴史研究と思想史と考古学の関係
1. 歴史研究:語られたことの総体を語る——歴史の連続性、人間がおこなう解釈行為。歴史研究は、伝統を発見したり進化を見出したり、目的論を企図する行為にほかならない。
2. 伝統的な「思想史」:形式や類型、あるいは発達/進化/採用/放棄などのメタファーで語る——意識の至上権をよりどころとする(慎改 412)
3. 知の考古学研究:思想史的アプローチではない。[従来の]人間的思考法/至上の主体という発想から解放されたもの(慎改 412)。ヘーゲル流の否定のレトリックが駆使される(?)(例:科学の原理的普遍性や統一性を否定する)。言説そのもののレベルに止まりつづける(→解 釈学的方法の否定)
★フーコーのいう考古学は、思想史という知的探究を探究するメタファーであり、現実のサイエンスとしての「考古学」 のことではない。しかし、フーコーにとって考古学という比喩をつかう意義は次の点にあるように思われる:1)思想あるいは歴史は連続的に変化するとか何らかの要因で進 展する(フーコー[中村訳]1981:13)という〈ある種の進歩史観〉を完全に放棄すること。2)連続性を単純に放棄するという命令法ではなくて、思想史は事後的に連続したり、発展したり、 ある種の発見によって、変化を被るという、〈変化やダイナミズム〉の 並置は、思想史における事象の断片化、断絶化、不連続化(フーコー[中村訳]1981:12)が出発点としてあり、我々は、その不連続性を並べてなにかの意味の系列であるかのように物語化して いるのだという反省的視点をとることを要求する。3)考古学者が発掘する際に必要となるのは、地表から掘り下げていく、以前には我々は何も知らないのだと いう認識をもつこと、掘り下げていくプロセスのなかで、データを記述していくが、そこでは性急な解釈を中断すること、ただひたすらデータを細心にとること が要求される。4)資料を探究し、掘り下げてもはや何ものも発掘されない時点で、考古学発掘はおわり、ようやく、考古学資料の解釈にはいるが、そこでは、 時間の流れは、層位にもとづいて、何らかの不連続線(時代区分)による画定作業により、断片化が担保されている。
☆「「考古学」にとって、解釈は、使用すべき方法ではなくて、歴史の連続性がそうであるのと同様に、検討に付されるべきひとつの問題なのである」(慎改 421)——「主体の学への隷属からの解放」(慎改 421-422)
★ただし、これ以降のフーコーは、歴史の連続性や個別事象の解釈(実践)を批判するよりも、主体と真理の関係に探求のテーマが徐々にかわっていく。
☆目次
★
| I. INTRODUCTION |
1. イントロダクション |
| II. LES RÉGULARITÉS DISCURSIVES |
2. 言説の規則 |
| I. Les unités du discours. |
2.1. 言説の一貫性 |
| II. Les formations discursives. |
2.2. 言説編成 |
| III. La formation des objets. |
2.3. 事物の形成 |
| IV. La formation des modalités
énonciatives. |
2.4. 発語様相の形成 |
| V. La formation des concepts. | 2.5. 概念の形成 |
| VI. La formation des stratégies. |
2.6. 戦略の形成 |
| VII. Remarques et conséquences. |
2.7. 備考および結果 |
| III. L'ÉNONCÉ ET L'ARCHIVE |
3.ステートメント(言明)とアーカイブ |
| I. Définir l'énoncé. |
3.1. 言明の定義 |
| II. La fonction énonciative. |
3.2. 発語機能 |
| III. La description des énoncés. |
3.3. 言明の記述 |
| IV. Rareté, extériorité, cumul. |
3.4. 希少性、外見、蓄積性 |
| V. L'a priori historique et
l'archive. |
3.5. 歴史的アプリオリとアーカイブ |
| IV. LA DESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE |
4. 考古学的記述 |
| I. Archéologie et histoire des
idées. |
4.1 考古学と思想史 |
| II. L'original et le régulier. |
4.2. オリジナリティと規則(慎改 266) |
| III. Les contradictions. |
4.3. 矛盾 |
| IV. Les faits comparatifs. |
4.4. 比較的事実 |
| V. Le changement et les
transformations. |
4.5. 変化と変容 |
| VI. Science et savoir. |
4.6. 科学と知 |
| V. CONCLUSION |
5. 結論 |
| 出典:L'Archéologie
du savoir |
|
| The Archaeology of Knowledge
(L’archéologie du savoir, 1969) by Michel Foucault is a treatise about
the methodology and historiography of the systems of thought
(epistemes) and of knowledge (discursive formations) which follow rules
that operate beneath the consciousness of the subject individuals, and
which define a conceptual system of possibility that determines the
boundaries of language and thought used in a given time and domain.[1]
The archaeology of knowledge is the analytical method that Foucault
used in Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of
Reason (1961), The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical
Perception (1963), and The Order of Things: An Archaeology of the Human
Sciences (1966).[1] |
ミシェル・フーコーによる『知の考古学』(L'archéologie
du savoir,
1969)は、主体である個人の意識の下に作用する規則に従い、ある時代と領域で用いられる言語と思考の境界を決定する可能性の概念体系を定める思考(エ
ピステーム)と知識(言説形式)のシステムについての方法論と歴史学についての著作である[1]。A History of Insanity in
the Age of Reason (1961)、The Birth of the Clinic:
また、フーコーは、『狂気と文明-理性時代の狂気の歴史』(1961年)、『臨床医学の誕生-医療知覚の考古学』(1963年)、『物事の秩序』
(1963
年)において、知の分析方法を用いている。人間科学の考古学』(1966年)[1]。 |
| The contemporary study of the
History of Ideas concerns the transitions between historical
world-views, but ultimately depends upon narrative continuities that
break down under close inspection. The history of ideas marks points of
discontinuity between broadly defined modes of knowledge, but those
existing modes of knowledge are not discrete structures among the
complex relations of historical discourse. Discourses emerge and
transform according to a complex set of relationships (discursive and
institutional) defined by discontinuities and unified themes.[2] |
現代の思想史研究は、歴史的世界観の変遷に関わるものであるが、結局の
ところ、綿密な検証のもとに崩れ去る物語の連続性に依存している。思想史は、広範に定義された知識様式の間の不連続点を示すが、それらの既存の知識様式
は、歴史的な言説の複雑な関係の中で個別の構造をなしているわけではない。言説は不連続性と統一的なテーマによって定義される複雑な関係(言説的、制度
的)に従って出現し、変容する[2]。 |
| An énoncé (statement) is a
discourse, a way of speaking; the methodology studies only the “things
said” as emergences and transformations, without speculation about the
collective meaning of the statements of the things said.[3] A statement
is the set of rules that makes an expression — a phrase, a proposition,
an act of speech — into meaningful discourse, and is conceptually
different from signification; thus, the expression “The gold mountain
is in California” is discursively meaningless if it is unrelated to the
geographic reality of California.[4] Therefore, the function of
existence is necessary for an énoncé (statement) to have a discursive
meaning.[5] |
エ
ノンセ(陳述、言表、ステートメント)は、ひとつの言説(談話)、話し方である。方法論は、言われたことの陳述
の集合的な意味について推測することなく、出現と変容として「言われたこと」だけを研究する。言明とは、ある表現(フレーズ、命題、発話行為)を意味のあ
る言説にするための規則の集合であり、意味づけとは概念的に異なる。したがって、「金山はカリフォルニアにある」という表現は、それがカリフォルニアとい
う地理的現実と無関係であれば言説的には意味をなさないのである。したがって、エノンセ(陳述)が言説的な意味を持つためには、存在の機能が必要である。 |
| As a set of rules, the statement
has special meaning in the archaeology of knowledge, because it is the
rules that render an expression discursively meaningful, while the
syntax and the semantics are additional rules that make an expression
significative.[6] The structures of syntax and the structures of
semantics are insufficient to determine the discursive meaning of an
expression;[7] whether or not an expression complies with the rules of
discursive meaning, a grammatically correct sentence might lack
discursive meaning; inversely, a grammatically incorrect sentence might
be discursively meaningful; even when a group of letters are combined
in such a way that no recognizable lexical item is formulated can
possess discursive meaning, e.g. QWERTY identifies a type of keyboard
layout for typewriters and computers.[8] |
と
いうのも、ある表現(ステートメント)を言説的に意味あるものにするのは規則であり、構
文と意味論は表現を意味あるものにする追加的な規則であるからである。構文の構造と意味論の構造は、表現の論証的意味を決定するには不十分である;文法的
に正しい文章でも、その表現が言説実践の法則に則っているかどうかで、言説実践の意味が欠けてしまうことがある;逆に、文法的に不正確な文章も言説的に意
味があることがある;例えば、QWERTYの意味の配列はナンセンスな文字列だがタイプライターやコンピュータのキーボードレイアウトの一種である(利用
者にとって無意味配列でも、利用者に統一した配列を提供する点で意味のある配列である)ことがわかる。 |
| The meaning of an expression
depends upon the conditions in which the expression emerges and exists
within the discourse of a field or the discourse of a discipline; the
discursive meaning of an expression is determined by the statements
that precede and follow it.[9] To wit, the énoncés (statements)
constitute a network of rules that establish which expressions are
discursively meaningful; the rules are the preconditions for signifying
propositions, utterances, and acts of speech to have discursive
meaning. The analysis then deals with the organized dispersion of
statements, discursive formations, and Foucault reiterates that the
outlined archaeology of knowledge is one possible method of historical
analysis.[10] |
ある表現の意味はその表現がある分野のディスコースや学問のディスコー
スの中に出現し存在する条件に依存し、ある表現の言説的意味はそれに先行し後続する陳述によって決定される[9]
つまり、エノンセ(陳述)はどの表現が言説的に意味を持つかを定める規則のネットワークを構成し、規則は言論の提案、発話、行為に意味を与えるための前提
条件であり言説的意味を持たせる。そして分析は陳述、言説的形成の組織的分散を扱い、フーコーは知識の概括的考古学が歴史的分析の一つの可能な方法である
ことを繰り返し述べている[10]。 |
| The
philosopher Gilles Deleuze describes The Archaeology of Knowledge as,
"the most decisive step yet taken in the theory-practice of
multiplicities."[11] |
哲学者のジル・ドゥルーズは『知の考古学』を「多重性の理論と実践にお いてこれまでになされた最も決定的なステップ」[11]と表現している。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/The_Archaeology_of_Knowledge. | https://www.deepl.com/ja/translator. |
★日本語ウィキペディア
ミシェル・フーコーの『知の考古学』(ちのこうこがく、フランス語:L'
archéologie du savoir,
1969)は、客体たる人間の意識の下で作用するところの規則に従うものであり、そして所与の時代と地域で用いられる言語と思考の限界を決定するところの
可能性の概念的体系を定めるものである、思考と知識の体系の、方法論と歴史編集についての学術論文である[1]。『知の考古学』は、フーコーが『狂気の歴
史』(1961年)、『臨床医学の誕生』(英語: The Birth of the Clinic )(1963年)、そして『言葉と物』(英語:
The Order of Things )(1966年)で使ったところの分析的方法である。[1]
慎改康之訳
1 序論
2 言説の規則性(言説の統一性;言説形成 ほか)
3 言表とアルシーヴ(言表を定義すること;言表機能 ほか)
4 考古学的記述(考古学と思想史;独創的なものと規則的なもの ほか)
5 結論
| L'Archéologie
du savoir est un ouvrage du philosophe français Michel Foucault paru en
1969 chez Gallimard. Cet essai d'épistémologie tente d'expliquer la
démarche précédemment développée par l'auteur notamment dans Histoire
de la folie (1962) et Les Mots et les Choses (1966). Avec Les Mots et les Choses, c'est dans cet ouvrage que Foucault développe la notion d’épistémè. |
『知識の考古学』は、フランスの哲学者ミシェル・フーコーが1969年
にガリマール社から出版した著作です。この認識論に関するエッセイは、著者が『狂気の歴史』(1962年)や『言葉と物』(1966年)などで以前に展開
した考え方を説明しようとしたものです。 『言葉と物』に続き、この著作でフーコーは「エピステーム」の概念を展開している。 |
| I. Introduction II. Les régularités discursives I. Les unités du discours
III. L'énoncé et l'archiveII. Les formations discursives III. La formation des objets IV. La formation des modalités énonciatives V. La formation des concepts VI. La formation des stratégies VII. Remarques et conséquences I. Définir l'énoncé
IV. La description archéologiqueII. La fonction énonciative III. La description des énoncés IV. Rareté, extériorité, cumul V. La priori historique et l'archive I. Archéologie et histoire des
idées
V. ConclusionII. L'original et le régulier III. Les contradictions IV. Les faits comparatifs V. Le changement et les transformations VI. Science et savoir |
I. 序論 II. 言説の規則性 I. 言説の単位 II. 言説の形成
III. 発話とアーカイブIII. 対象の形成 IV. 発話様式の形成 V. 概念の形成 VI. 戦略の形成 VII. 備考と結論 I. 発話の定義
IV. 考古学的記述II. 発話機能 III. 発話記述 IV. 希少性、外在性、累積 V. 歴史的先験性とアーカイブ I. 考古学と思想史
V. 結論II. 原典と規則性 III. 矛盾 IV. 比較的事実 V. 変化と変容 VI. 科学と知識 |
★『知の考古学』英訳版、186ページ
| 1. Ideology is not exclusive of scientificity. Few discourses have given
so much place to ideology as clinical discourse or that of political economy:
this is not a sufficiently good reason to treat the totality of their statements
as being undermined by error, contradiction, and a lack of objectivity. |
イデオロギーは科学性を排しない。臨床的言説や政治経済学の言説ほどイデオロギーに大きな比重を置くものは少ない。だが、それゆえにそれらの主張全体が誤りや矛盾、客観性の欠如によって損なわれていると扱うのは、十分な根拠とは言えない。 |
| 2. Theoretical contradictions, lacunae, defects may indicate the ideological functioning of a science (or of a discourse with scientific pretensions) ; they may enable us to determine at what point in the structure this functioning takes effect. But the analysis of this functioning must be made at the level of the positivity and of the relations between the rules of formation and the structures of scientificity. | 2.
理論上の矛盾、欠落、欠陥は、科学(あるいは科学的権威を装う言説)のイデオロギー的機能を示唆しうる。それらは、この機能が構造のどの点で作用するかを
特定することを可能にする。しかし、この機能の分析は、肯定性および形成規則と科学的構造の関係性のレベルで行われねばならない。 |
| 3 . By correcting itself, by rectifying its errors, by clarifying its formulations, discourse does not necessarily undo its relations with ideology. The role of ideology does not diminish as rigour increases and error is dissipated. | 3.言説は自らを修正し、誤りを正し、表現を明確化することによって、必ずしもイデオロギーとの関係を解消するわけではない。厳密さが増し、誤りが解消されても、イデオロギーの役割は減じない。 |
| 4. To tackle the ideological functioning of a science in order to reveal and to modify it is net to uncover the philosophical presuppositions that may lie within it; nor is it to return to the foundations that made it possible, and that legitimated it: it is to question it as a discursive formation; it is to tackle not the formal contradictions of its propositions, but the system of formation of its objects, its types of enunciation, its concepts, its theoretical choices. It is to treat it as one practice among others. | 4.
科学のイデオロギー的機能を解明し修正するとは、その内部に潜む哲学的前提を暴くことでもない。また、その成立を可能にし正当化した基礎に立ち返ることで
もない。それは言説的形成物としての科学を問い直すことだ。その命題の形式的矛盾ではなく、対象形成のシステム、言説の類型、概念体系、理論的選択そのも
のに挑むことである。それは、他の実践の一つとして扱うことである。 |
☆L'Ordre du discours(言説の秩序)
| L'Ordre du discours est la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France, prononcée le 2 décembre 1970. Foucault présente l'hypothèse que dans toute société la production du discours est contrôlée, afin d'éliminer les pouvoirs et les dangers et contenir des événements aléatoires dans cette production. Ces procédures sont divisées en interne et externe. 1 |
『言説の秩序』は、ミシェル・フーコーが1970年12月2日にコレージュ・ド・フランスで行った就任講演である。 フーコーは、あらゆる社会において、権力や危険を排除し、言説の生成における不測の事態を抑制するために、言説の生成が統制されているという仮説を提示している。これらの手続きは、内部と外部に分けられる[1]。 |
| Citation « Je suppose que dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire, d'en esquiver la lourde, la redoutable matérialité. »[2 |
引用 「あらゆる社会において、言説の生成は、その力と危険性を回避し、その不確定な出来事を制御し、その重く恐ろしい物質性を回避する役割を担う、いくつかの手続きによって、同時に統制され、選択され、組織化され、再分配されているのだろう。」[2 |
| Table des procédures de contrôle des discours I. Externes 1. L'interdit 2. Le partage Raison-Folie 3. L'opposition Vrai-Faux II. Internes 1. Le commentaire 2. L'auteur 3. L'organisation des disciplines III. Régulatrices de l'accès 1. Le rituel 2. Les "sociétés de discours" 3. Les doctrines 4. L'appropriation sociale |
言論統制の手順表 I. 外部 1. 禁止 2. 理性・狂気の区分 3. 真・偽の対立 II. 内部 1. 解説 2. 著者 3. 分野の組織化 III. アクセス規制 1. 儀式 2. 「言説社会」 3. 教義 4. 社会的受容 |
| 1. (pt) Alex Pereira de Araújo,
« A ordem do discurso de Michel Foucault: 50 anos de uma obra que
revelou o jogo da rarefação dos sujeitos e a microfísica dos discursos
», Unidad Sociologica, juin-septempre, 2020, p. 14-23 (lire en ligne
[archive] Accès libre [PDF]) 2. Michel Foucault, L'ordre du discours : leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, Gallimard, 1971 (ISBN 2-07-027774-7 et 978-2-07-027774-2, OCLC 189732, lire en ligne [archive]) |
1. (pt)
アレックス・ペレイラ・デ・アラウージョ、「ミシェル・フーコーの言説の秩序:主体の希薄化と言説の微視的物理学を明らかにした著作の50年」、
Unidad Sociologica、2020年6月-9月、14-23ページ(オンラインで読む [アーカイブ] フリーアクセス [PDF]) 2. ミシェル・フーコー、『言説の秩序:1970年12月2日、コレージュ・ド・フランスにおける就任講演』、ガリマール、1971年(ISBN 2-07-027774-7 および 978-2-07-027774-2、OCLC 189732、オンラインで読む [アーカイブ]) |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ordre_du_discours |
|
| Die Ordnung des Diskurses
war das Thema der von Michel Foucault am 2. Dezember 1970 gehaltenen
Antrittsvorlesung zu seiner Berufung auf den eigens für ihn
eingerichteten Lehrstuhl zur „Geschichte der Denksysteme“ am Collège de
France. Die Vorlesung wurde in erweiterter Fassung 1971 als L’ordre du
discours in Paris bei Gallimard veröffentlicht. In diesem Vortrag zeigt Foucault Mechanismen auf, die den Diskurs kontrollieren. Auf dieser Grundlage skizziert er, welche Probleme er im Collège de France zu behandeln gedenkt. Der hier von ihm verwendete Diskursbegriff markiert einen Übergang zwischen seiner Archäologie des Wissens und den späteren machtanalytischen Arbeiten. |
言説の秩序は、1970年12月2日にミシェル・フーコーが、コレー
ジュ・ド・フランスで彼のために特別に設置された「思想体系の歴史」の教授職に就任した際の就任講演のテーマだった。この講演は、1971年にパリのガリ
マール社から『言説の秩序』として拡張版が刊行された。 この講演でフーコーは、言説を統制するメカニズムを明らかにしている。これを基に、コレージュ・ド・フランスで扱う予定の課題について概説している。ここで彼が用いている言説の概念は、彼の『知識の考古学』と、その後の権力分析に関する研究との過渡期を示すものである。 |
| Die Ordnung des Diskurses „Ich setze voraus, daß in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird – und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität zu umgehen.“[1] Foucault teilt die Prozeduren, durch die das geschieht, in drei Klassen ein. Ausschließungssysteme, die von ‚außen’ wirken und den Diskurs in seinem „Zusammenspiel mit der Macht und dem Begehren“[2] betreffen, also seine Kräfte zu kontrollieren suchen. Interne Prozeduren, mit denen Diskurse sich selbst durch „Klassifikations-, Anordnungs-, [und] Verteilungsprinzipien“[2] kontrollieren, um die Zufälligkeit von Ereignissen zu „bändigen“[2], ihre Entstehung und ihren Inhalt beherrschbar zu machen. Die Verknappung der sprechenden Subjekte, die über Bedingungen für die Teilnahme an Diskursen, und an Regeln, denen der spezielle Diskurs unterliegt, gebunden ist. |
言説の秩序 「私は、あらゆる社会において、言説の生成は、その力と危険性を抑制し、その予測不可能な出来事性を排除し、その重く脅威的な物質性を回避することを目的とした、特定の手続きによって、同時に統制、選択、組織化、および導かれると仮定する」[1] フーコーは、これを実現する手順を 3 つのカテゴリーに分類している。 「外部」から作用し、言説の「権力と欲望との相互作用」[2]、つまりその力を制御しようとする排除システム。 言説が「分類、順序付け、 [および] 分配の原則」[2] によって、出来事の偶然性を「抑制」[2] し、その発生と内容を制御可能にする内部手続き。 談話への参加条件、および特定の談話が従う規則に拘束される、発言する主体の減少。 |
| Ausschließungssysteme Das Verbot Nach Foucault gibt es drei Arten von Verboten: „Man weiß, daß man nicht das Recht hat, alles zu sagen, daß man nicht bei jeder Gelegenheit von allem sprechen kann, daß schließlich nicht jeder beliebige über alles beliebige reden kann.“[3] Er nennt diese drei Grundformen Tabu des Gegenstandes, Ritual der Umstände und bevorzugtes oder ausschließliches Recht des sprechenden Subjekts. Die Unterscheidung zwischen Wahnsinn und Vernunft Das nächste Ausschließungssystem ist „[…] kein [direktes] Verbot, sondern eine Grenzziehung und eine Verwerfung“[3]. Durch die Unterscheidung in Vernunft und Wahnsinn werden Teile des Diskurses verworfen und können nicht zirkulieren. Entweder gilt das Wort des Wahnsinnigen „[…] für null und nichtig, es hat weder Wahrheit noch Bedeutung […]“[4], oder man traut ihm „eigenartige Kräfte“[4] wie das Voraussagen der Zukunft oder das Aussprechen verborgener Wahrheiten zu. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem Zuhörenden, der einen Diskurs verfolgt – ihm aber willkürlich Relevanz zugestehen oder aberkennen kann – und dem Belauschten und seinem vom Zuhörer belauschten Diskurs. Der ‚belauschte’ Diskurs wird durch das Begehren des Zuhörers durchdrungen und funktionalisiert. Der Wille zur Wahrheit Schließlich nennt Foucault den Willen zur Wahrheit, einen von Friedrich Nietzsche übernommenen Begriff, als drittes Ausschließungssystem. Er führt an, dass es eine grundlegende Verwerfung in der Diskursgeschichte gab: An deren Anfang existierte nur ein wahrer Diskurs, bei dem man Achtung und Ehrfurcht vor denen hatte, die dazu legitimiert waren, ihn nach bestimmten Ritualen zu führen. Seit Platon „lag die höchste Wahrheit nicht mehr in dem, was der Diskurs war, oder in dem, was er tat, sie lag in dem, was er sagte“[5]. Träger des Wahrheitsanspruches ist nicht mehr der Diskurs selbst, sondern die einzelne Aussage, die sich über ihren Sinn, ihre Form, ihren Gegenstand und ihren referentiellen Bezug legitimiert und als wahr oder falsch erweist. Seit dem 17. Jahrhundert wird diese „platonische Grenzziehung“ ergänzt durch den Willen, ein bestimmtes technisches Niveau für die Verifizierung von Erkenntnissen vorzuschreiben („Wille zum Wissen“). Heute kommen immer weiter perfektionierte institutionelle Mechanismen der Absicherung von Wissen hinzu: Der Wille zur Wahrheit wird durch erkenntnistheoretische Fundierung sowie durch die selektive Bewertung, Sortierung und Verwendung von Wissen durch Institutionen – etwa in der Rechtsprechung – zementiert. Foucault hebt dabei den dialektischen Charakter von Wahrheit, in ihrer Bedeutung als Reichtum auf der einen, als Ausschließungsmechanismus auf der anderen Seite, hervor: Der Wille zur Wahrheit beinhaltet notwendig wahrheitsfremde Elemente, nämlich das Begehren und die Macht, er ist somit immer auch eine „Ausschließungsmaschinerie“. |
排除システム 禁止 フーコーによれば、禁止には3種類ある。「人は、何でも言う権利はないこと、あらゆる機会であらゆることを話すことはできないこと、結局のところ、誰もが 何でも好きなことを話せるわけではないことを知っている」[3]。彼は、この3つの基本的な形態を、対象物のタブー、状況の儀式、そして話す主体の優先的 または排他的な権利と呼んでいる。 狂気と理性の区別 次の排除システムは、「[…] 直接的な禁止ではなく、境界線の設定と拒絶」である[3]。 理性と狂気の区別によって、談話の断片は拒絶され、流通することができなくなる。狂人の言葉は「[…] 無効であり、真実も意味も持たない […]」[4] あるいは、未来を予言したり、隠された真実を口にするといった「特異な力」[4] を持っていると信じられるかのどちらかである。 その結果、談話を追っている聞き手(その談話の関連性を恣意的に認めたり否定したりできる)と、聞き手によって盗み聞きされている話者、そして聞き手が盗み聞きしている談話との間に緊張関係が生じる。盗み聞きされた談話は、聞き手の欲望に浸透され、機能化される。 真実への意志 最後に、フーコーは、フリードリヒ・ニーチェから引き継いだ概念である「真実への意志」を、3つ目の排除システムとして挙げている。彼は、談話の歴史には 根本的な拒絶があったと主張する。その始まりには、特定の儀式に従って談話を進める権限を持つ者たちに対する敬意と畏敬の念を抱く、唯一の真実の談話しか 存在しなかった。プラトン以来、「最高の真実は、言説そのものや、その言説が果たす役割ではなく、その言説が伝える内容にある」[5] ようになった。 真実性を主張するのは、もはや言説そのものではなく、その意味、形式、対象、参照関係によって正当化され、真か偽かが証明される個々の発言である。17 世紀以降、この「プラトニックな境界設定」は、知見の検証に一定の技術的レベルを規定しようとする意志(「知識への意志」)によって補完されている。 今日では、知識を保証するための、ますます完璧になった制度的メカニズムが加わっている。真実への意志は、認識論的根拠、および制度(例えば司法)による 知識の選択的評価、選別、利用によって固められている。フーコーは、真実の弁証法的性格、つまり、一方では富としての意味、他方では排除のメカニズムとし ての意味を強調している。真実への意志には、必然的に真実とは無関係な要素、すなわち欲望と権力が含まれているため、それは常に「排除のメカニズム」でも あるのだ。 |
| Interne Prozeduren Der Kommentar Der Diskurs wird durch den Kommentar in Primär- und Sekundärtexte gestuft. Einerseits ermöglicht der Kommentar das immer neue Konstituieren von neuen Diskursen, andererseits erhebt er den Anspruch das zu sagen, was immer schon implizit gesagt war: „Er muß […] zum ersten Mal das sagen, was doch schon gesagt worden ist, und muß unablässig das wiederholen, was eigentlich niemals gesagt worden ist.“[6] Die Zufälligkeit des Diskurses wird mit Hilfe des Kommentars beherrscht: „[…] er erlaubt zwar, etwas anderes als den Text selbst zu sagen, aber unter der Voraussetzung, daß der Text selbst gesagt und in gewisser Weise [durch den Kommentar, HvdL] vollendet werde.“[7] Der Autor Eine andere diskursregulierende Institution ist der Autor, als konstruiertes „Prinzip der Gruppierung von Diskursen, als Einheit und Ursprung ihrer Bedeutungen, als Mittelpunkt ihres Zusammenhalts“[7]. Durch das Prinzip des Autors wird der potenziellen Endlosigkeit und Grenzenlosigkeit möglicher Bedeutungen eine Referenz auf den legitimen Sinngehalt bestimmter Diskursbeiträge beigefügt. Die Disziplin Die Disziplin stellt eine ‚Konstruktionsanleitung’ zur Teilnahme an einem bestimmten Teil des Diskurses dar, es können endlos neue Sätze gebildet werden, „aber nach ganz bestimmten Spielregeln“[8]. Um zu einer Disziplin zu gehören, muss ein Satz bestimmten Bedingungen genügen: Der Satz muss sich auf eine definierte Gegenstandsebene beziehen und sich in einen bestimmten theoretischen Horizont einfügen. Foucault betont, dass man immer irgendwo die Wahrheit sagen kann, aber gleichzeitig innerhalb eines Diskurses außerhalb des Wahren sein kann. Die Grenzen der Disziplin werden durch ihre Identität geschaffen, die „die Form einer permanenten Reaktualisierung [ihrer] Regeln hat“[9]. |
内部手順 解説 談話は、コメントによって一次テキストと二次テキストに分類される。コメントは、一方で常に新しい談話を構築することを可能にする一方で、常に暗黙的に語 られていたことを語ると主張する。「彼は、すでに語られたことを初めて語らなければならず、実際には決して語られたことのないことを絶えず繰り返さなけれ ばならない」[6]。 談話の偶然性は、解説によって制御される。「[…] 解説は、テキスト自体以外のことを言うことを許すが、それは、テキスト自体が述べられ、ある意味で(解説によって、HvdL)完成されていることを前提とする」[7]。 著者 談話を規制するもう一つの制度は、著者である。著者は、「談話をグループ化する原則、その意味の統一性と起源、その結束の中心」として構築されている[7]。 著者の原則によって、潜在的な無限性および無限の可能性を持つ意味に、特定の談話への貢献の正当な意味内容への参照が付け加えられる。 規律 規律は、特定の言説の一部に参加するための「構築の手順」であり、無限に新しい文を形成することができるが、「非常に特定のルールに従って」[8] である。 ある規律に属するためには、文は特定の条件を満たさなければならない。文は、定義された対象レベルに関連し、特定の理論的視野に組み込まれる必要がある。 フーコーは、どこにでも真実を語ることができるが、同時に、談話の中では真実から外れている場合もあると強調している。規律の境界は、その「規則を絶えず更新する形」[9] というそのアイデンティティによって形成される。 |
| Verknappung der sprechenden Subjekte Das Ritual Das Ritual beschränkt den Zugang zu Diskursen über drei Instrumente: Die Qualifikation, das Zeichensystem und die Grenzen der Bedeutung, die eine innerhalb eines Rituals gemachte Äußerung hat. Unter diesen Bedingungen ist keine voraussetzungslose Teilhabe am Diskurs möglich und Akteure oder Gruppen von Akteuren werden ausgeschlossen. Die Diskursgesellschaften Diskursgesellschaften sind so organisiert, dass Diskurse produziert und aufbewahrt werden und in geschlossenen Räumen nach bestimmten Regeln organisiert und verteilt werden. Die Disziplin setzt dieser Produktion Grenzen – sie „diszipliniert“ sie – und aktualisiert fortwährend ihre Regeln. Maßgebliches Kriterium ist, dass die Inhaber nicht das Eigentum am Diskurs verlieren. Die Rollen des Hörenden und Sprechenden in Diskursgesellschaften sind nicht tauschbar. Die Doktrin Die Doktrin arbeitet mit dem Ziel, nur bestimmte Aussagetypen zuzulassen, diese Typen aber so zu vervielfältigen, dass der Diskurs von ihnen beherrscht wird. Individuen werden vom Diskurs unterworfen, der von der Gruppe der sprechenden Individuen unterworfen wird. |
発言主体の不足 儀式 儀式は、3つの手段によって談話へのアクセスを制限する。それは、資格、記号体系、そして儀式の中で発せられた発言の意味の限界だ。 こうした状況では、前提条件のない談話への参加は不可能であり、個人や集団が排除されることになる。 言説社会 言説社会は、言説が生み出され、保存され、閉ざされた空間で特定の規則に従って整理、分配されるように組織されている。規律は、この生成に制限を設け(つ まり「規律」を課し)、その規則を絶えず更新する。重要な基準は、所有者が言説の所有権を失わないことだ。談話社会における聞き手と話し手の役割は交換可 能じゃない。 教義 教義は、特定のタイプの発言のみを許可し、そのタイプを複製して談話を支配することを目標としてる。個人は、話し手グループによって支配される談話に服従するんだ。 |
| Die gesellschaftliche Aneignung der Diskurse Schließlich stellt die gesellschaftliche Aneignung der Diskurse eine Form der Verknappung dar. „Jedes Erziehungssystem ist eine politische Methode, die Aneignung der Diskurse mitsamt ihrem Wissen und ihrer Macht aufrechtzuerhalten oder zu verändern.“[10] Methodische Grundsätze Aus dieser Analyse von den Diskurs formenden Prinzipien folgert Foucault, dass seine zukünftigen Analysen methodischen Grundsätzen folgen sollen, die Umkehrung (die Erfassung des Ausgeschlossenen und der Mechanismen der Verknappung und Ausschließung, z. B. der Sprechverbote), Diskontinuität (die Bedeutung des Einzelereignisses in der zersplitterten Serie der Diskurse anstelle der Betonung einer imaginären Kontinuität), Spezifität (der Verzicht auf die Annahme vorgängiger Bedeutungen) und Äußerlichkeit (die Fokussierung der „äußeren Möglichkeitsbedingungen“ des Diskurses anstelle der Annahme einer „Mitte des Denkens“) berücksichtigen. Damit gibt Foucault den Grundsatz einer Kontinuität der Vernunft und ihrer Vollendung auf. Mit dem Versuch, dem „gespenstischen“ Schatten Hegels zu entrinnen, erweist er am Ende seiner Vorlesung seinem Lehrer Jean Hyppolite eine explizite Referenz. Kritik und Genealogie Unter den Begriffen Kritik und Genealogie, die Foucault in den folgenden Jahren weiter ausführt (vgl. Literatur), beschreibt er mögliche kritische und genealogische Forschungen zu Sexualität und Wahnsinn, die er für zukünftige Arbeiten im Collège de France anvisiert. Mit Kritik ist dabei die Erfassung der sich verändernden Formen der Ausschließung und der dadurch ausgeübten Zwänge gemeint. Mit Genealogie bezeichnet er das Wachstum von Diskursserien und die dabei geltenden Normen und Veränderungsbedingungen. |
社会による言説の吸収 結局のところ、社会による言説の吸収は、一種の希少化である。「あらゆる教育システムは、その知識と権力とともに言説の吸収を維持、あるいは変化させる政治的手法である」[10]。 方法論的原則 談話形成の原則に関するこの分析から、フーコーは、今後の分析は、以下の方法論的原則に従うべきであると結論づけている。 逆転(排除されたもの、および希少化と排除のメカニズム、例えば発言の禁止などを把握すること) 不連続性(想像上の連続性を強調する代わりに、断片化された言説の連鎖における個々の出来事の重要性)、特異性(先行する意味の仮定の放棄)、外部性(思 考の中心という仮定の代わりに、言説の「外部の可能性条件」に焦点を当てる)を考慮に入れるべきだと結論づけている。こうしてフーコーは、理性とその完成 の連続性の原則を放棄する。ヘーゲルの「幽霊のような」影から逃れようとした結果、彼は講義の最後に、師であるジャン・イポリットに明確な言及をしてい る。 批判と系譜学 フーコーがその後数年にわたってさらに展開した「批判」と「系譜学」という概念(参考文献を参照)の中で、彼は、コレージュ・ド・フランスでの今後の労働 として、セクシュアリティと狂気に関する批判的・系譜学的な研究の可能性について述べている。ここで言う批判とは、変化し続ける排除の形態と、それによっ て行使される強制の把握を意味する。系譜学とは、一連の言説の成長と、それに適用される規範や変化の条件を指す。 |
| Stellenwert im Gesamtwerk Beginnend mit der Ordnung des Diskurses ersetzen die methodischen Begriffe „Kritik“ und „Genealogie“ den von Foucault bis dahin für sein Vorgehen verwendeten Begriff „Archäologie“ (vgl. Archäologie des Wissens). In der Vorlesung von 1970 finden sich bereits interessante Anklänge an die Kritische Theorie, die Foucault damals nach eigenen Angaben noch nicht kannte. So bestimmen auch in Max Horkheimers Werk Mechanismen der „Hemmung, Disziplin und Verzicht die Praxis moderner Vernunftherrschaft“[11] Der Originaltitel L’ordre du discours bezeichnet im Französischen sowohl eine rein beschreibende Ordnung als auch eine normative Regel, ja einen Befehl. Diese Doppelbödigkeit durchzieht die Arbeit. Auch im soziologischen Kultur- und im Systembegriff sind sowohl deskriptive Elemente als auch normative Prozeduren der Ausschließung angelegt. Foucaults Diskursbegriff changiert zwischen beiden. |
全作品における重要性 言説の秩序から始まり、方法論的な概念である「批判」と「系譜学」が、フーコーがそれまでその手法に使用していた「考古学」という概念に取って代わった (知識の考古学を参照)。1970年の講義には、当時フーコー自身がまだ知らなかったと述べる批判理論への興味深い言及がすでにみられる。マックス・ホル クハイマー著作においても、「抑制、規律、放棄というメカニズムが、現代の理性支配の実践を決定づけている」[11] と述べられている。 原題の L’ordre du discours は、フランス語では、純粋に記述的な秩序と、規範的な規則、さらには命令の両方を意味する。この二重の意味は、この労働全体に流れている。社会学的文化概 念やシステム概念にも、記述的な要素と規範的な排除の手順の両方が組み込まれている。フーコーの言説概念は、この両者の間で揺れ動いている。 |
| Einzelnachweise 1. Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt 1991. S. 10 f. 2. vgl. Foucault 1991, S. 17 3. vgl. Foucault 1991, S. 11 4. vgl. Foucault 1991, S. 12 5. vgl. Foucault 1991, S. 14 6. vgl. Foucault 1991, S. 19 7. vgl. Foucault 1991, S. 20 8. vgl. Foucault 1991, S. 22 9. vgl. Foucault 1991, S. 25 10. vgl. Foucault 1991, S. 30 11. Ralf Konersmann, Der Philosoph mit der Maske, in: Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses, erw. Ausgabe Frankfurt 1991, S. 87 |
参考文献 1. ミシェル・フーコー『言説の秩序』フランクフルト、1991年、10ページ以降。 2. フーコー 1991、17ページを参照。 3. フーコー 1991、11ページを参照。 4. フーコー 1991、12ページを参照。 5. 参照:フーコー 1991、14 ページ 6. 参照:フーコー 1991、19 ページ 7. 参照:フーコー 1991、20 ページ 8. 参照:フーコー 1991、22 ページ 9. 参照:フーコー 1991、25 ページ 10. 参照:フーコー 1991、30 ページ 11. ラルフ・コナーズマン、仮面の哲学者、ミシェル・フーコー『言説の秩序』、増補版、フランクフルト、1991、87 ページ |
| Literatur Didier Eribon: Michel Foucault. Eine Biographie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-518-40335-4. Michel Foucault: Von der Subversion des Wissens. Fischer, Frankfurt am Main 1987 (enthält Aufsatz zur Genealogie). Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-596-10083-6. Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main 1971 (besonders S. 72 ff.). Michel Foucault: Was ist Kritik? Merve, Berlin 1992. Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003. |
文献 ディディエ・エリボン:ミシェル・フーコー。伝記。スールカンプ、フランクフルト・アム・マイン、1991年、ISBN 3-518-40335-4。 ミシェル・フーコー『知識の転覆』フィッシャー社、フランクフルト・アム・マイン、1987年(系譜に関する論文を含む)。 ミシェル・フーコー『言説の秩序』フィッシャー・タッシェンブフ出版社、フランクフルト・アム・マイン、1991年、ISBN 3-596-10083-6。 ミシェル・フーコー『事物の秩序』。フランクフルト・アム・マイン、1971年(特に72ページ以降)。 ミシェル・フーコー『批判とは何か』。メルヴェ、ベルリン、1992年。 ミシェル・フーコー『知識の考古学』。スールカンプ、フランクフルト・アム・マイン、2003年。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Ordnung_des_Diskurses |
★知の考古学の出版までのクロニクル
1962 『精神疾患と心理学』(神谷美恵子・訳、 みすず書房)Maladie mentale et Psychologie (Paris: PUF, 1962)
1963 『臨床医学の誕生』(神谷美恵子・訳、み すず書房)Naissance de la clinique: une archaologie du regard m仕ical (Paris: PUF, 1963).
1964 Traduction; Anthropologie du point de vue pragmatique, d'Emmanuel Kant. Vrin, 1964
1965 Professeur invité à la Faculté de Philosophie de São Paulo, 1965
1966 『言葉と物』(渡辺一民ほか訳、新潮社) Les Mots et les Choses. Une archaologie des sciences humaines. Paris 1966.
1966-1967 Professeur détaché à la Faculté des Lettres de Tunis, 1966-1967
1968 5月10日パリで「68年5月」は じまる(5月2日〜6月23日:Mai 68)
1968 モーリス・パンゲが東京大学での教職を辞した際に、フーコーはその後任を務めたいと申し出たが実現には至らなかった
1969-1970 Professeur à l'Université « expérimentale de Vincennes », 1969-1970(冬)
1969 『知の考古学』(中村雄一郎訳、河出書房 新社)L'Archaologie du savoir (Paris: Gallimard, March 1969).
1970 コレージュ・ド・フランス教授: Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire des systèmes de pensée », 1970(→「言説の秩序」)
1971 『言説表現の秩序』(中村雄一郎訳、河出
書房新社)L'ordre du discours (Paris, Gallimard, 1971):Participation à la
création d'un groupe d'observation des prisons, 1971
★Gaston Bachelard, 1884-1962
ガストン・バシュラール(Gaston Bachelard, * 1884年6月27日 in Bar-sur-Aube; † 1962年10月16日 in Paris)は、科学と詩の理論に取り組んだフランスの哲学者である。バシュラールは、科学と芸術的想像力を、新しいものの差異に心を開き、人間として成 長するための、異なるが等しく重要な2つの方法と考えた。科学哲学の分野では、彼の「認識論的障害(epistemological obstacle)」と「認識論的プロフィール(epistemological profile)」という用語が重要である。
★ジョルジュ・カンギレム(Georges Canguilhem, 1904-1995)
ジョルジュ・カンギレムは、
1904年6月4日にカステルノーダリーで生まれ、1995年9月11日にポルト・マルリーで亡くなったフランスの哲学者であり、レジスタンス運動家であ
る。エコール・ノルマル・シュペリウールの卒業生であり、医学博士の資格を持ちながら医師としての職務を拒否した彼は、1956年から1971年まで、ガ
ストン・バシュラールの後任として、科学技術史・哲学研究所(IHPST)の所長を務めた。
認識論と科学史、特に生物学、医学、心理学が科学としての地位を獲得した過程に焦点を当てたその著作、特に『正常と病理』および『生命の認識』は、生物を
その物理化学的または行動学的測定値に還元し、それによって科学には必要であるが個人にとっては不十分な規範を課すことを拒否する、倫理的、さらには英雄
的とも言える要求に基づくものである。フッサールの現象学を批判したジャン・カヴァイエにインスピレーションを得て、カール・マルクスによるドイツの科学
主義の批判を糧とし、ポストモダン世代、すなわち「フレンチ・セオリー」と呼ばれる抗議運動を率いた世代、特にミシェル・フーコーやピエール・ブルデュー
(カンギレムは彼らの博士論文の指導教官だった)に多大な影響を与えた。
最近のカンギレムに対する評価では、彼は「ヨーロッパ哲学のサブ潮流」である「バイタリスト・マルクス主義」[1]に分類されている
+++
リンク
文献
その他の情報

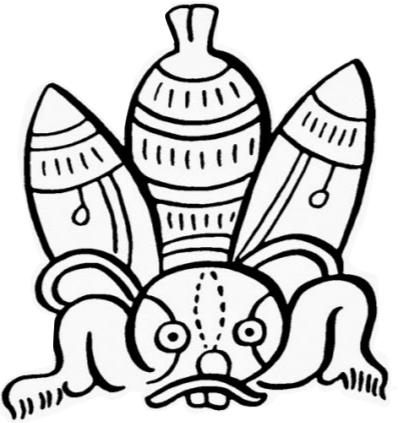
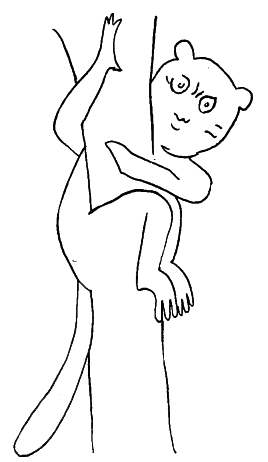
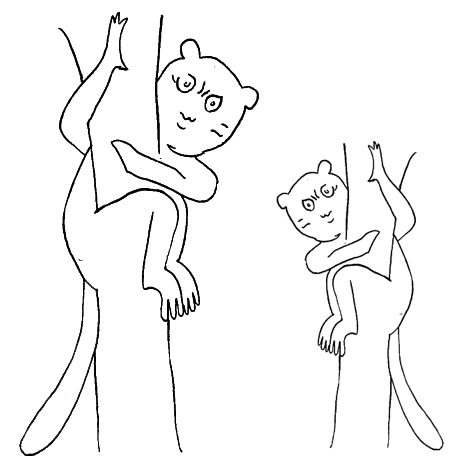
++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099