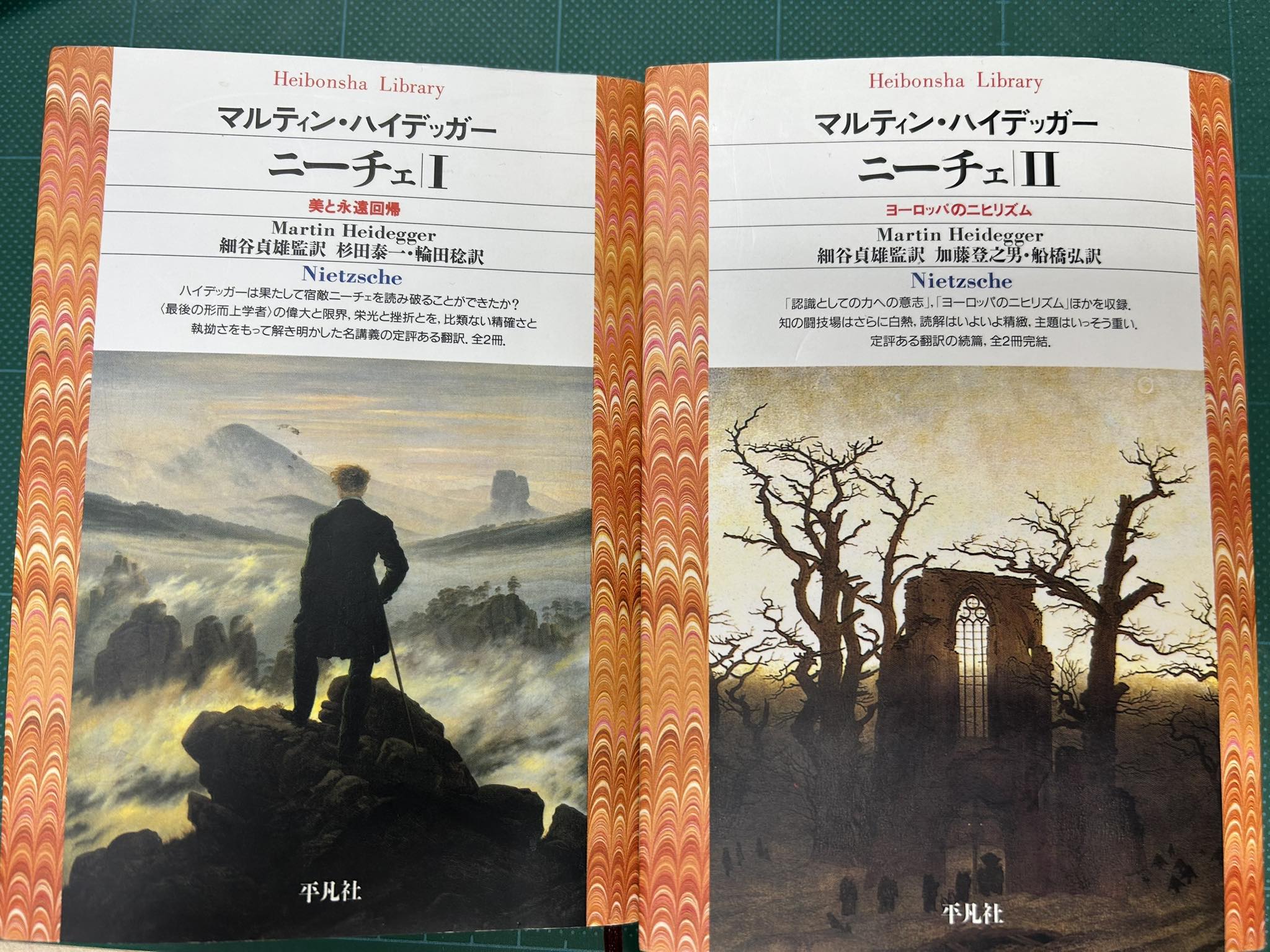
ハイデガーにとってのニーチェ
Heidegger's
Nietzsche
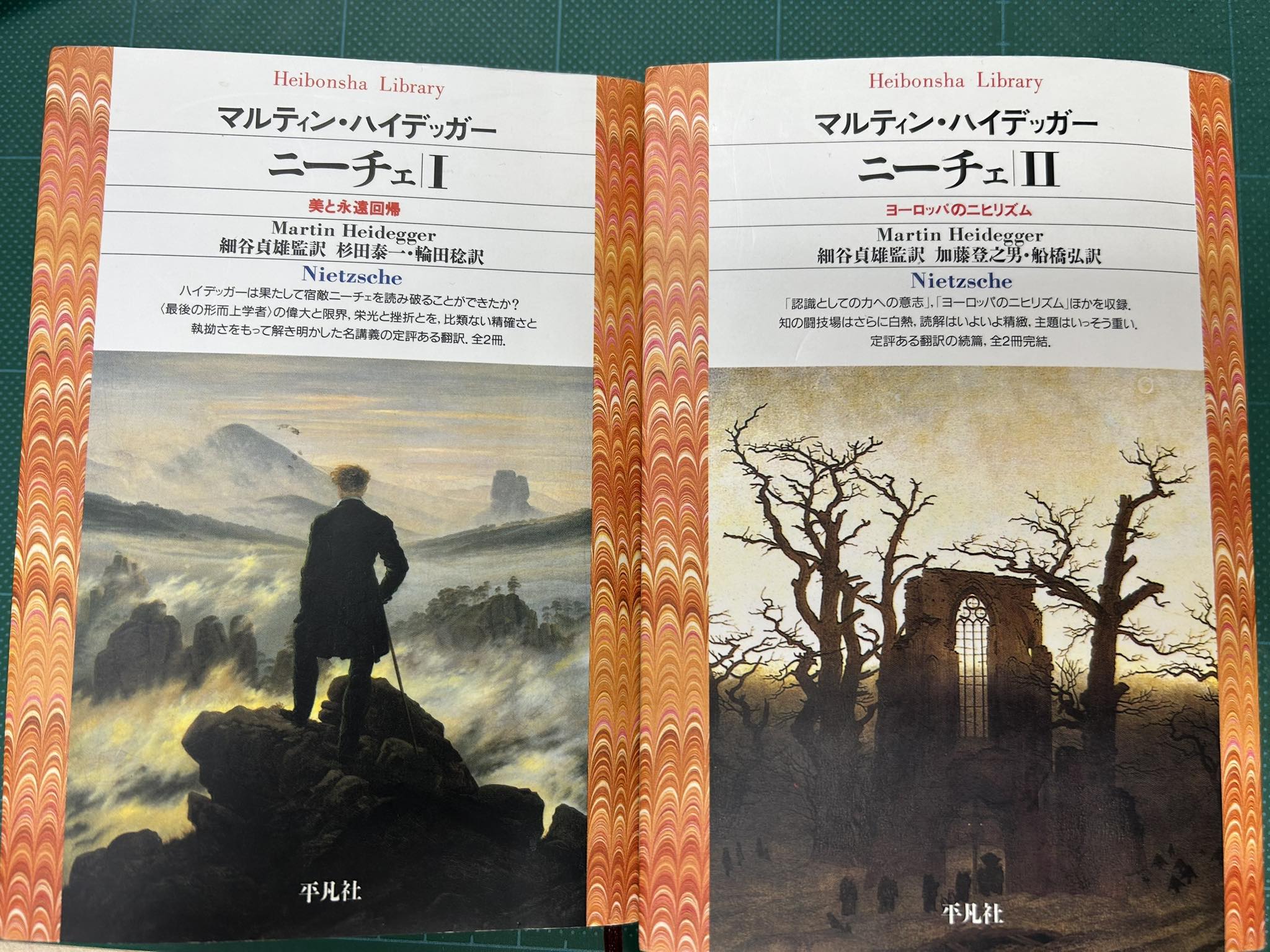
☆ マルチン・ハイデガーが〈最後の形而上学者〉と主張するフリードリヒ・ニー チェの「力への意志」の読解を中心として、ハイデガー自身の形而上学や存在論を 展開する。『存在と時間』の次の大著だと細谷貞雄は主張する。原文は全集にある講義録(1939年)。邦訳は、上中下の3冊の予定だったが、「美と永遠回 帰 」と「ヨー ロッパのニヒリズム」が翻訳されたのみ。理想社版の下巻(あるいは平凡社版のIII巻)に相当するものは、 薗田宗人により1986年に翻訳された(第6講から10講)。ニーチェの哲学的な影響の過程で、マルティン・ハイデガーは、ニーチェの「力への意志」を「存在の理由」という形而上学的な問いに対する答えとして捉え た。ニーチェとハイデガー、そしてその後アーレントは、権力という概念を、社会における人間という観点から、自分自身で「何かを作り出す」という根本的 な可能性へと還元することで、ニーチェのアプローチに肯定的な側面を見出した。
★講義録※
講義は終わり近くで中断、あと2回行う予定だったが、次の「等しいものの永劫回帰と力への意志」が、第1講のまとめを構成するとのこと。
第
2講 等しいものの永劫回帰(ニーチェの形而上学の根本思想としての永劫回帰説;回帰説の成立;ニーチェの回帰説の最初の告知 ほか)
第 3講 認識としての力への意志(形而上学の完成の思索家としてのニーチェ;ニーチェのいわゆる「主著」;新たなる価値定立の原理としての力への意志 ほ か)
第
4講 等しいものの永劫回帰と力への意志
「ヨー ロッパのニヒリズム」1940年講義-------------------------
第 5講 ヨーロッパのニヒリズム
第 6講 ニーチェの形而上学
第 7講 存在の歴史に即したニヒリズム規定(薗田訳は「存在」が「有」となる)
「存 在の歴史としての形而上学」1941年講義-------------------------
第 8講 存在の歴史としての形而上学
第
9講 形而上学としての存在の歴史に向けての諸草案
第10
講 形而上学の内への回想
★
年譜関係は「マルチン・ハイデガー」を参照のこと。
****
| 美と永遠回帰 /
マルティン・ハイデッガー著 ; 杉田泰一, 輪田稔訳, 平凡社 , 1997 . - (平凡社ライブラリー, 179 . ニーチェ ; 1) 1 芸術としての力への意志(形而上学的思索者としてのニーチェ;『力への意志』という書物;『本堂』のための計画と下描き;力への意志と永遠回帰と価値 転倒の統一性 ほか) 2 同じものの永遠なる回帰(ニーチェの形而上学の根本思想としての永遠回帰の教え;回帰説の成立;回帰説についてのニーチェの最初の伝達; 『Incipit tragoedia』 ほか) |
「認識としての力への意志」1939年講義 |
| ヨーロッパのニヒリズム /
マルティン・ハイデッガー著 ; 加藤登之男, 船橋弘訳, 平凡社 , 1997 . - (平凡社ライブラリー, 184 . ニーチェ ; 2) 3 認識としての力への意志(形而上学の完成の思索者としてのニーチェ;ニーチェのいわゆる『主著』;新たな価値定立の原理としての力への意志;真理の本 質に関するニーチェの根本思想における認識 ほか) 4 同じものの永遠なる回帰と力への意志 5 ヨーロッパのニヒリズム(ニーチェの思索における五つの主要名称;『最高の諸価値の無価値化』としてのニヒリズム;ニヒリズム、ニヒル、および無; ニーチェにおける宇宙論と心理学の概念 ほか) |
「ヨーロッパのニヒリズム」1940年講義 |
| ニーチェ III /
マルティン・ハイデガー [著] ; 薗田宗人訳, 白水社 , 1986 6講 ニーチェの形而上学 7講 ニヒリズムの存在史的規定 8講 存在の歴史としての形而上学 9講 形而上学としての存在の歴史—草案 10講 形而上学への回想 |
|
| Literatur zu Wille
zur Macht, Theorem von Nietzsche, Datenbank „Weimarer
Nietzsche-Bibliographie (WNB)“ Stefan Günzel: Tod ist bei Göttern immer nur ein Vorurtheil. Über den ›Willen zur Macht‹ als Gerechtigkeit und wie er sich mit Derrida in Heideggers Nietzsche anders verstehen lässt als ihn Gadamer verstanden hat. (Memento vom 6. März 2014 im Internet Archive) Stefan Günzel: Wille zur Differenz. Gilles Deleuzes Nietzsche-Lektüre. (Memento vom 8. Oktober 2009 im Internet Archive) Patrick Thor: »Eine fortgesetzte Zeichen-Kette von immer neuen Interpretationen« – Friedrich Nietzsches ›Wille zur Macht‹ und die Semiotik von Charles S. Peirce. In: Muenchner Semiotik – Zeitschrift des Forschungskolloquiums an der LMU (2018) Der „Wille zur Macht“ – kein Buch von Friedrich Nietzsche, eine Auswahl aus Nietzsches Nachlass, mit Texten zum philosophischen Konzept „Wille zur Macht“ sowie zu den nicht umgesetzten Buchprojekten gleichen Namens, herausgegeben von Bernd Jung auf der Grundlage der Digitalen Kritischen Gesamtausgabe, 2012/13 ARTE-Dokumentation „Nietzsche: Zwischen Genie und Wahnsinn“ von 2017, https://www.youtube.com/watch?v=izMsClefo-I |
Wille
zur Macht |
★第1講 芸術としての力への意志
| 1.1. 形而上学的な思索者としてのニーチェ |
|
| 1.2. 『力への意志』という書物 |
|
| 1.3. 本堂のための計画と下書き |
|
| 1.4. 力への意志と永遠回帰と価値転倒の統一性 |
|
| 1.5. 本堂の構成 |
|
| 1.6. 伝統的形而上学における意志としての存在者の存在 |
|
| 1.7 力への意志としての意志 |
|
| 1.8 情動・情熱・感情としての意志(65) |
|
| 1.9 ニーチェの意志論の観念論的解釈 |
|
| 1.10 意志と力、力の本質 |
|
| 1.11 哲学の根本問題と先導問題 |
|
| 1.12 芸術についての5つの命題 |
|
| 1.13. 美学の歴史にみられる6つの根本的事実 |
|
| 1.14 美的状態としての陶酔 |
|
| 1.15 美についてのカントの教え——ショーペンハウアーとニーチェによるこの教えの誤解 |
|
| 1.16 形式創造の力としての陶酔 |
|
| 1.17 偉大な様式 |
|
| 1.18 芸術についての5つの命題の根拠づけ |
|
| 1.19 真理と芸術のあいだの刺激的な離間 |
|
| 1.20 プラトニズムと実証主義における真理——ニーチェがニヒリズムの根本経験からプラトニズムの逆転を試みたこと |
|
| 1.21 芸術と真理の関係に向けられたプラトンの省察の範囲と連関 |
|
| 1.22 プラトンの「国家」——芸術の真理からの距離 |
|
| 1.23 プラトンのパイドロス論——幸福をもたらす離間における美と真理 |
|
| 1.24 ニーチェのプラトニズム逆転 |
|
| 1.25 感性の新解釈と、芸術と真理の間の刺激的離間 |
★第2講 同じものの永遠なる回帰
| 2.1 ニーチェの形而上学の根本思想としての永遠回帰の教え |
|
| 2.2 回帰説の成立 |
|
| 2.3 回帰説についてのニーチェの最初の伝達 |
|
| 2.4 Incipit tragoedia |
|
| 2.5 回帰説の第二の伝達 |
|
| 2.6 幻影と謎について |
|
| 2.7 ツァラトゥストラの動物たち |
|
| 2.8 回復しつつある者 |
|
| 2.9 回帰説の第三の伝達 |
|
| 2.10 手許に保留された覚書における回帰思想 |
|
| 2.11 1881年8月の4つの手記 |
|
| 2.12 思想の総括的叙述——生としての、力としての、存在者の全体、混沌としての世界 |
|
| 2.13 存在者の人間化の懸念 |
|
| 2.14 回帰説のためのニーチェの証明 |
|
| 2.15 証明の手続きにおけるいわゆる自然科学的方法——哲学と科学 |
|
| 2.16 回帰説の証明の性格 |
|
| 2.17 信仰としての回帰思想 |
|
| 2.18 回帰思想と自由 |
|
| 2.19 悦ばしき学問の時期の手記の回顧 |
|
| 2.20 ツァラトゥストラ期の手記 |
|
| 2.21 力への意志の時期の手記 |
|
| 2.22 回帰説の形態 |
|
| 2.23 回帰思想の領域——ニヒリズム克服としての回帰説 |
|
| 2.24 瞬間と永遠回帰 |
|
| 2.25 形而上学的な根本境涯の本質——西洋哲学の歴史におけるそれぞれの可能性 |
|
| 2.26 ニーチェの形而上学的な根本的境涯 |
※以上、平凡社版「美と永遠回帰」(ニーチェ 第1巻)
★第3講 認識としての力への意志
| 3.1 形而上学の完成の思索者としてニーチェ |
|
| 3.2 ニーチェのいわゆる主著 |
|
| 3.3 新たな価値定立の原理としての力への意志 |
|
| 3.4 真理の本質に関するニーチェの根本思想における認識 |
|
| 3.5 価値評価としての真理=正しさの本質 |
|
| 3.6 ニーチェのいわゆる生物学主義 |
|
| 3.7 論理学としての西洋形而上学 |
|
| 3.8 真理と真なるもの |
|
| 3.9 真の世界と仮象の世界の対立——価値関係への還元 |
|
| 3.10 生成としての世界と生 |
|
| 3.11 実践的欲求に即する渾沌の図式化としての認識 |
|
| 3.12 渾沌の概念 |
|
| 3.13 図式欲求としての実践的欲求——地平形成と遠近法的展望 |
|
| 3.14 了解と打算 |
|
| 3.15 理性の創作的本質 |
|
| 3.16 ニーチェによる認識の働きの生物学的解釈 |
|
| 3.17 存在の原理としての矛盾律(アリストテレス) |
|
| 3.18 命令としての矛盾律(ニーチェ) |
|
| 3.19 真理、真の世界と仮象の世界の区別 |
|
| 3.20 形而上学的に把握された真理の極限的な転化 |
|
| 3.21 正義としての真理 |
|
| 3.22 力への意志の本質——生成の臨在性への持続化 |
★第4講 等しいものの永劫回帰と力への意志(同じものの永遠なる回帰と力への意志)
| I |
|
| II |
|
| III |
|
| IV |
|
| V |
|
| VI |
★第5講 ヨーロッパのニヒリズム
| 5.1 ニーチェの思索における5つの主要名称 |
|
| 5.2 最高の諸価値の無価値化としてのニヒリズム |
|
| 5.3 ニヒリズム、ニヒル、および無 |
|
| 5.4 ニーチェにおける宇宙論と心理学の概念 |
|
| 5.5 ニヒリズムの由来 |
|
| 5.6 カテゴリーとしての至上価値 |
|
| 5.7 ニヒリズムと西欧的歴史の人間 |
|
| 5.8 新たな価値定立 |
|
| 5.9 歴史としてのニヒリズム |
|
| 5.10 価値定立と力への意志 |
|
| 5.11 ニーチェの歴史解釈における主体性 |
|
| 5.12 形而上学についてののニーチェの道徳的解釈 |
|
| 5.13 形而上学と擬人化 |
|
| 5.14 プロタゴラスの命題 |
|
| 5.15 近代における主体の支配 |
|
| 5.16 cogito me cogitare としてのデカルトの cogito |
|
| 5.17 デカルトの cogito sum |
|
| 5.18 デカルトとプロタゴラスの形而上学的な根本的境涯 |
|
| 5.19 デカルトに対するニーチェの態度表明 |
|
| 5.20 デカルトとニーチェの根本的境涯の内的関連 |
|
| 5.21 人間の本質規定と真理の本質 |
|
| 5.22 形而上学の終末 |
|
| 5.23 存在者への関わりあいと存在への関与——存在論的差異 |
|
| 5.24 ア・プリオリとしての存在 |
|
| 5.25 イデアとしての、アガトンとしての、条件としての存在 |
|
| 5.26 存在をイデアとする存在解釈と価値思想 |
|
| 5.27 力への意志としての存在の投企 |
|
| 5.28 存在と存在者の区別と人間の自然(本性) |
|
| 5.29 空虚と豊饒としての存在 |
※以上、平凡社版「ヨーロッパのニヒリズム」(ニーチェ 第2巻)
★第6講 ニーチェの形而上学
| 0. 序説 |
|
| 1. 力への意志 |
|
| 2. ニヒリズム |
|
| 3. 同一物の永劫回帰 |
|
| 4. 超人 |
|
| 5. 正義 |
★第7講 ニヒリズムの存在史的規定
| (章分けなし) |
|
★第8講 存在の歴史としての形而上学
| 8.1 形而上学の本質開始における何-存在と事実-存在、イデアとエネルゲイア |
|
| 8.2 エネルゲイアから現実性への変移 |
|
| 8.3 真理の確実性への変移 |
|
| 8.4 ヒュポケイメノンの基体への変移 |
|
| 8.5 ライプニッツ、現実性と表象作用の共属性 |
|
| 8.6 基体性(スビエクティタート)と主体性(スブジャクテキヴィタート) |
|
| 8.7 ライプニッツの「24の命題」 |
★第9講 形而上学としての存在の歴史(草案)
| 9.1 存在の歴史より |
|
| 9.2 近代形而上学の本質規定 |
|
| 9.3 対称性、超越性、一体性、存在(カント「純粋理性批判」16節) |
|
| 9.4 存在——対象性(意志) |
|
| 9.5 対象性としての存在、存在と思惟、一体性と一者 |
|
| 9.6 対象性と反省、反省と否定性 |
|
| 9.7 反省と現在化 |
|
| 9.8 反省と対象と主体性 |
|
| 9.9 先験的なもの(ア・プリオリなもの) |
|
| 9.10 現在化と反省 |
|
| 9.11 現在、現実性、意志 |
|
| 9.12 存在と意識、存在史的経験に立って |
|
| 9.13 意志としての現実性、カントの存在概念 |
|
| 9.14 存在 |
|
| 9.15 形而上学の完成 |
|
| 9.16 存在すること |
|
| 9.17 実在(実存) |
|
| 9.18 存在と実存概念の局限 |
|
| 9.19 シェリングとキルケゴール |
|
| 9.20 シェリング |
|
| 9.21 実存と実存的なもの |
★第10講 形而上学への回想
| (章立てなし) |
|
★
★
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆