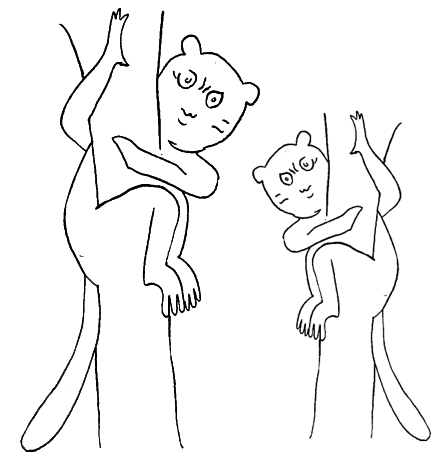
哲学にみられる人種主義
Racism in Philosophy
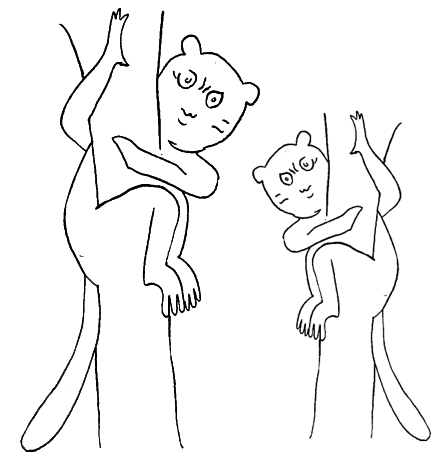
☆哲学における人種主義(レイシズム)を批判する
★ヒュームとレイシズム
| David Hume is
generally regarded as one of the most acute critics of superstition and
prejudice during the Enlightenment. However, a footnote added to his
essay “Of National Characters” has been cited by both racists and
anti-racists, and his view has had considerable influence on subsequent
racism. Starting with Richard Popkin, many researchers have revealed
the relationship between Hume and modern racism, and provided various
arguing points on the matter. In this article, I survey previous
research and clarify what to examine now. First, I examine a series of
theses published by Popkin , the first instance of these
investigations. I especially consider his understanding of the history
of ideas regarding racism, as it is the basis for his interpretation of
Hume’s racism. Popkin argues that modern racism is derived from
polygenetic theory, or pre-Adamite theory, and that Hume’s notorious
footnote suggests his implied polygenetic position, which is of
non-theological or naturalistic form. However, polygenetic theory in
itself can be neutral toward racism. Thus we must reconsider what we
can criticise Hume for as well as the meaning of the word “racism.”
Second, although Popkin’s interpretation played an important role in
research on Hume’s racism, some objections have been raised against it.
Among these, John Immewahr’s objection is particularly significant.
Immewahr shows that when Popkin argued Hume never modified his
contention in the subsequent editions of his essays despite some
attacks, especially from James Beattie, Popkin overlooked the revisions
of the note in question in the 1777 edition. In fact, despite having
deleted or concealed his polygenetic opinion, Hume’s racial prejudice
against Black people remained in the revised footnote. Therefore,
Immewahr concludes that Hume’s racism was a considered and deliberate
position. As this conclusion is now widely accepted, then we must
question the relationship, if any, between Hume’s racism and his entire
philosophy. Then, I examine this relationship in several respects, such
as induction and prejudice, which have been discussed by numerous
researchers. For instance, Popkin states that as Hume ignored
counterexamples he could access, he was “a poor empirical researcher.”
Hence, we must consider the reason and manner in which Hume arrived at
such a conclusion, which we must examine. Likewise, Hume’s racial
prejudice has been pointed out. Meanwhile, Hume himself criticised
prejudice in “Of the Standard of Taste”. We must reconcile both
statements. Consequently, the complex and complied arguments regarding
Hume’s racial view are delineated and clarified. |
デイヴィッド・ヒュームは啓蒙時代において、迷信や偏見に対する最も鋭
い批判者の一人と見なされている。しかし彼の論文『国民性について』に付された脚注は、人種主義者と反人種主義者の双方によって引用され、その後の人種主
義に多大な影響を与えた。リチャード・ポプキンを起点に、多くの研究者がヒュームと現代人種主義の関係を明らかにし、この問題について様々な論点を提示し
てきた。本稿では先行研究を概観し、現在検証すべき点を明確化する。まず、こうした研究の先駆けであるポプキンの一連の論文を検討する。特に、ヒュームの
人種主義解釈の基盤となる、人種主義に関する思想史の理解に焦点を当てる。ポプキンは、現代人種主義は多起源説(プレアダム説)に由来し、ヒュームの悪名
高い脚注が非神学的・自然主義的な多起源説の立場を示唆していると主張する。しかし多起源説自体は人種主義に対して中立的であり得る。したがって我々は、
ヒュームを批判できる点と「人種主義」という言葉の意味を再考しなければならない。第二に、ポプキンの解釈はヒュームの人種主義研究において重要な役割を
果たしたが、これに対していくつかの異議が提起されている。中でもジョン・イムワーの反論は特に重要である。イムワーは、ポプキンが「ヒュームは特に
ジェームズ・ビーティーからの批判にもかかわらず、エッセイの改訂版で主張を修正しなかった」と論じた際、1777年版における当該注釈の改訂を見落とし
ていたことを示した。実際、多起源説の意見を削除または隠蔽したにもかかわらず、黒人に対するヒュームの人種的偏見は改訂された脚注に残っていた。した
がってイムワーは、ヒュームの人種主義は熟慮された意図的な立場であったと結論づける。この結論が現在広く受け入れられている以上、我々はヒュームの人種
主義と彼の哲学全体との間に、もしあるならば、どのような関係があるのかを問わねばならない。そこで本稿では、多くの研究者が論じてきた帰納法と偏見と
いった観点から、この関係を多角的に検証する。例えばポプキンは、ヒュームがアクセス可能な反例を無視した点から「貧弱な経験的研究者」と評している。故
に我々は、ヒュームが如何なる理由と方法でこの結論に至ったかを考察せねばならない。同様に、ヒュームの人種的偏見も指摘されてきた。一方でヒューム自身
は「趣味の基準について」で偏見を批判している。この二つの主張を整合させる必要がある。結果として、ヒュームの人種観に関する複雑で矛盾した議論が明確
に整理される。 |
| https://x.gd/8JEOz |
西内亮平「ヒュームと人種主義」京都大学大学院人間・環境学研究科『人間存在論』刊行会 |
★出典は、Philosophy’s systemic racism by Avram Alpert, https://aeon.co/essays/racism-is-baked-into-the-structure-of-dialectical-philosophy
| 近
代の偉大な哲学者たちが人種差別的な見解を持っていたことは、今ではよく知られている。ジョン・ロック(1632~1704年)、デイヴィッド・ヒューム
(1711~76年)、イマニュエル・カント(1724~1804年)、G・W・F・ヘーゲル(1770~1831年)、その他多くの人々は、世界中の黒
人や先住民族は野蛮であり、劣っており、ヨーロッパ人の啓蒙によって矯正される必要があると信じていた。今日、こうした明確な人種差別的見解を擁護するま
ともな哲学者はいないが、正当な理由があって、彼らはこれらの著者の著作を研究し続けている。哲学的洞察を保持するために、学者たちは個々の人種主義と哲
学体系を区別する傾向がある。ヘーゲルはアフリカ人などに対する人種差別的な著作については間違っていたかもしれないが、だからといって彼の思弁的形而上
学については何もわからない。 あるいは、そういう議論もある。しかし、過去数十年の間に人種主義について私たちが学んだことがあるとすれば、それは、個々の人種主義的な発言に焦点を当 てると、人種主義がシステムの中で存続し続けている方法が見えなくなってしまうということである。例えば、米国の法律はもはや有色人種の権利をあからさま に剥奪するものではなくなったかもしれないが、集団投獄を通じて抑圧を可能にしていることに変わりはない。哲学者の個人的人種主義を非難することに注力す るあまり、哲学的人種主義がシ ステム的にそのまま維持されることを許してしまっているのではないか。 近代思想における最も体系的な哲学の創造者であるヘーゲルのケースを、少し詳しく考えてみよう。ヘーゲルは確かに露骨な人種差別主義者であった。例えば彼 は、アフリカの黒人は「ナイーブな状態に浸ったままの子供の種族」だと考えていた。さらに彼は、先住民族は「野蛮で不自由な状態」に生きていると書いた。 そして、『権利の哲学』(1821年)の中で、彼は、ヨーロッパ人の啓蒙の進歩のためにこれらの人々を植民地化する「英雄の権利」があると主張した。 しかし、こうした人種差別的な発言がヘーゲルの哲学体系に痕跡を残していることは、すぐにはわからない。ヘーゲルは、形而上学、美学、歴史学、政治学、さ らには植物学や磁気学に関する百科全書的な著作の中で、弁証法的変容の普遍的な過程がいかに存在するかを示そうと努めていた。ヘーゲルの弁証法は複雑なこ とで有名だが、大まかに定義すれば、物事間の矛盾が最終的にどのように分解され、より真理的で包括的な思想の創造につながるかを示すために、対立するもの を一つにまとめることである。よく引用される例として、「主人と奴隷の弁証法」と呼ばれるものがある。これは、ヘーゲルがさまざまな著作の中で取り上げた、二人の 人間の対等な関係への道筋についての議論である。これらの文章でヘーゲルは、主人と奴隷の対立がいかに耐えがたく不安定な状況を助長し、やがてそれを打破 して反乱を引き起こし、願わくば対等なシステムを作り上げなければならないかを示している。 この例から、ヘーゲルの哲学体系が人種差別的であったはずがないと合理的に結論づけられるかもしれない。批評理論家のスーザン・バック・モースは、ヘーゲ ルは主人と奴隷の弁証法を通じてハイチ革命を自分の哲学に書き込んでいたとまで主張している(→「ヘーゲルとハイチ」)。たとえ人種差別的な見解を持っていたとしても、ヘーゲルは哲学的に真 理を追求した結果、革命闘争を通じて普遍的な正義を主張するようになった。もしそうだとすれば、彼の哲学体系は人種主義と矛盾すると考えるのが妥当かもし れない。このような不協和があるからこそ、論者はヘーゲルの明確な人種主義と彼の哲学体系の意味を区別することを正当化するのである。 しかし、この区別は、ヘーゲルの弁証法という考え方がどこから生まれたのかをより深く考察すれば、崩れる。そうすることで、植民地人種主義が弁証法の概念 そのものに直接影響を与えていることに気づくだろう。今日の世界における体系的人種差別のように、哲学の体系的人種主義を理解するには、単に一個人や一組 の信念を見るだけではできない。私たちは、思想の歴史的背景を理解し、人種主義がどのようにその発端に影響を与えたか、そして、その人種主義が、私たちが 十分に気づいていないかもしれない方法で、今日の私たちの思考をどのように構成し続けているかを理解しなければならない。 Philosophy’s systemic racism by Avram Alpert |
|
| 弁
証法の歴史全体が人種差別的思考に染まっているというのは間違いだろう。例えば、ソクラテスの弁証法は、対話を通じて導き出される必要のある概念の内部矛
盾と可能性について主に論じている。また、「仏教弁証法」と呼ばれるものもあり、ナーガールジュナ(紀元150~250年頃)の著作のチベット語解釈と関
連づけられることが多いが、これは、従来実在していたすべての実体の究極的な空虚さ(本質の欠如)を示すものである。このテーマに関するヘーゲルの考え方
のルーツには、プラトンや新プラトン主義(そしておそらくインド哲学)の読解や、秩序ある自然界を構成する対極の考え方である磁気学の研究がある。実際、
ヘーゲルにとって弁証法的プロセスはあらゆるところで働いている。現在の刑務所制度のすべてが人種主義によって理解できるわけではないように、ヘーゲルの
哲学はこれ以上のものである。しかし、人種主義を抜きにして、監獄制度やヘーゲルのシステムを理解することはできないということも、同様に真実である。 弁証法におけるヘーゲルの直接の先行者であるジャン=ジャック・ルソー(1712-78)とフリードリヒ・シラー(1759-1805)の二人に注目すれ ば、弁証法そのものがプラトンや磁気と同様に植民地史の影響を受けていたことがわかる。ルソーはヘーゲルに多大な影響を与えた。ルソーもヘーゲルと同様、 植民地時代の民族誌家や宣教師たちの記録を貪欲に読んでいた。しかしヘーゲルとは異なり、彼は牧歌的な生活を送る人々について読んでいると思っていた。ル ソーは『人間の不平等の起源と基礎に関する講話』(1755年)の中で、アンティル諸島などの宣教師の証言をもとに、アメリカ大陸の先住民がいかに完璧に 近い平等と平穏の中で暮らしているかを描写した。ヨーロッパ人が疎外感と不公平感を募らせる一方で、ルソーはアメリカ大陸では気楽な平等が自然な生活様式 であると考えた。 しかし彼は、ヨーロッパ人がこの自然な生活様式に戻るべきであり、ヨーロッパとの接触が起こった今、アメリカ大陸の人々が本来あるべき自然な状態のままで いられるとは信じていなかった。ルソーの言う「カリブ人」はより理性的に、ヨーロッパ人はより本能的にならなければならない。(カリブ人」は植民地時代の 民族誌上のカテゴリーで、アンティル諸島のさまざまな集団を統合したものであるため、より正しい用語に置き換えるのは難しい。説明されている人々の多く は、自分たちをカリナゴと呼んでいただろう)。言い換えれば、カリブ人とヨーロッパ人は、本能と理性という相反する要素を結合させ、本能によって理性的に なるという、新しい第三の存在様式でそれぞれの問題を克服する新しい在り方で結合させなければならないのである。ルソーはこれを「都市に住むように作られ た野蛮人」の創造と呼んだ。聞き覚えがあるだろうか?一見正反対に見える2つのものが組み合わさって新しいものを生み出す。 |
|
| ルソーは、このような作り出された人間を羨望すると同時に批判している。 後に弁証法の体系に抽象化されることになる人種差別の論理をより詳細に見るには、ルソーの『談話』から、朝ハンモックをフランスの植民地支配者と交換し、夜になるとそれを返せと言う男についての有名な逸話を考えてみよう。ルソーはこう書いている: 彼(カリブ人)の魂は、何ものにも動かされることなく、自分自身の現在の存在の感情だけに支配されている。カリブの先見の明はそのようなものだ。朝、彼は綿のベッドを売り、夕方には泣きながらそれを買い戻しに戻ってくる。 この逸話は、宣教師ジャン=バティスト・デュ・テルトル(Jean-Baptiste du Tertre) が1667年に発表したアンティル諸島の人々に関する記述に基づくものである。デュ・テルトルは現在のグアドループを拠点としていた。デュ・テルトルの説 で注目すべきは、ルソーにはない背景を語っていることである。デュ・テルトルによれば、問題は彼が出会った人々が未来を考えることができないことではな く、単純に、より論理的に言えば、彼らがフランス人とは異なる交換の概念を持っていることなのだ。フランス人にとって取引は最終的なものだが、彼らにとっ ては一時的なものにすぎない。カリブ人は、カリブ人が自分たちの間で持っている態度をフランス人にも持ってほしいと願っている。つまり、フランス人は自分 たちに要求されるものはすべて気前よく与えるべきだということだ」と書いている。この説明では、昼間、ほとんど役に立たないハンモックと交換するフランス 人が愚かなのだ。また、カリブの土地でカリブの寛大さに応えないフランス人は、単に野暮である。 ルソーの記述からは、このような背景がすべて消えている。交換と贈与という洗練された倫理観を持つ他の人間たちは、時間の概念を持たない一面的な登場人物 になってしまう。弁証法の歴史にとって重要なのは、ルソーがこの人種差別的誤謬に基づいて、哲学的に何をしたかということである。ルソーは、このような作 り出された人間を羨望すると同時に批判する。彼は、人間の不幸の大部分は、まさに未来に思いを馳せることから生じると考えている: 先見の明である!先見の明、それはわれわれを絶え間なく自分自身を越えて連れて行き、しばしばわれわれが決して到着することのない場所にわれわれを置く......人間よ、自分の存在を自分の内側に引き寄せよ、そうすればもはや惨めな思いをすることはない......」。 カリブ人が幸福で「何ものにも動かされない」と言うのは、彼がカリブ人には先見の明がないと信じているからである。 しかしルソーは、未来志向の思考がなければ、計画も進歩もありえないことも知っている。社会契約論』(1762年)で彼が言うように、社会生活は「正義を 本能に代える」ことを要求する。ルソーによれば、どうにかして、私たちに安らぎと喜びをもたらしてくれる現在という感覚を失うことなく、正義を可能にする 未来思考を持つ方法を見つけなければならない。言い換えれば、本能と理性という一見相反するものを組み合わせることで、未来をないがしろにするほど現在に 存在せず、幸福を破壊するほど現在から疎外されることもない、世界における存在のあり方を統合することを学ばなければならない。つまり、フランス人とカリ ブ人の間に弁証法的なプロセスが必要なのだ。そして、このような考え方全体、弁証法的思考の下地は、ルソーの人種差別的思考に根本的な起源がある。ルソー は、アンティル諸島の人々はあまりにも愚かで、朝になれば、夕方には寝るためのハンモックが必要だということを知らないのだ。 |
|
| お
そらく懐疑的な読者は、それはルソーの問題だと言うかもしれない。弁証法とは何の関係もないし、ヘーゲルが書いている人種差別主義的なこととも明確な関係
はない。しかし、弁証法がルソーからドイツ思想に移っていく歴史をたどれば、次第に一般化されていくとはいえ、植民地人種主義が弁証法に付随していること
はすぐにわかる。ヘーゲル以前の弁証法的プロセスの主要な表現者の一人は、詩人であり哲学者であったシラーである。シラーは、ヘーゲルの弁証法哲学にとっ
て非常に重要なテキストである『人間の美学教育に関する書簡』(1795年)の中で、文化を超えて本能と理性を結びつける方法を見出そうとするルソーの課
題を明確に取り上げている。 シラーはルソーと同様、「自然人」の本能的な生活とヨーロッパ人の理性的な生活との間にギャップが形成されていると考えていた。そして、ルソーと同様に、本能の中にある良いものと合理性の中にある良いものを結びつける方法を見つけたいと考えた。これを達成するためには 人間の肉体的な性格からその恣意性を、道徳的な性格からその自由性を抽出し、第一の性格を法則に適合したものにし、第二の性格を感覚的な印象に依存したものにし......第三の性格を誕生させることを目的として......組み合わせることである。 シラーの言葉はルソーよりも抽象的だが、彼の人種差別の前提は同じである。本能に浸りすぎた民族(無法な「野蛮人」)と、理性を失いすぎた民族(無感情なヨーロッパ人)が存在し、それぞれの最良の部分を組み合わせる一方で、最悪の部分を否定することが目的なのである。 ヘーゲルは、シラーがこの否定による結合のプロセスを表現するのに使った言葉に魅了された。ドイツ語のAufhebung(アウフヘーヴング)は、しばし ば「昇華」と訳されるが、これは打ち消すと同時に保存することを意味する。ヘーゲルの著作では、昇華の定義はしばしば緻密で抽象的である。(例えば、存在 と無の昇華について、「存在は存在であり、無は無であるが、それは互いに矛盾するという点においてのみである。) とはいえ、そうした抽象的なものが、上に描いた植民地史とどのように関係しているのかは、はっきりとわかる。ルソーがカリブ人に対して行いたかったのは 「昇華」という行為であり、彼らの先見の明の欠如を取り消し、現在性を維持し、それによって彼らを幸福で平等主義的であり続ける、より秩序だった生活様式 へと引き上げることだった。彼はヨーロッパ人に対しても同じことを望んだ。彼らの過剰な先見性をキャンセルし、正義への集中を維持し、それによって彼らを 秩序と理性を維持した、より幸福な生活形態へと引き上げることだった。このプロセスには、最終的にそれぞれの文化の要素を組み合わせる必要があった: シラーの「第三の性格」、すなわち「都市に住むようにされた野蛮人」である。 自己意識は、奴隷制が克服され、対等な二人が互いを認め合うときにのみ可能となる。 ヘーゲルが弁証法的止揚の体系を発展させる際に、磁力とプラトンが念頭にあったことは確かかもしれないが、人間相互作用に関する彼の弁証法的哲学は、彼が それを抽象的かつ体系的なものにしたとはいえ、彼が継承し支持した人種主義と不可分であるという事実から逃れることはできない。彼の主従弁証法に立ち戻れ ば、この過程が働いていることがわかる。この物語のあるバージョンでは、ヘーゲルはこの物語を使って自己意識の起源を説明しようとしている。ヘーゲルはこ の物語を、ルソーのカリブ人が行き詰まったとされる「自然状態」という文脈の中に明確に設定する。彼は、「自己意識が、欲望と特異性に没頭していた状態か ら、その普遍性へと移行する」過程を理解したいと考えている。言い換えれば、ルソーのカリブのような人々から始まった人類という種は、どのようにしてル ソー、シラー、ヘーゲルのような哲学者になったのか。彼らはどのようにして、現在に囚われていた状態から、いつの時代にも普遍的な真理を語ることができる ようになったのだろうか? ヘーゲルによれば、ある時点で、それまで荒野で孤独だった2人の人間が突然対峙したとき、その没入感は破られるという。他の人間を見ることで、自分が客体 として見られる可能性が出てくる。自分の主体性を主張し、相手の客体になるのを食い止めるために、まず相手を客体にしようとする。これが支配と隷属の起源 であり、闘争に勝った者が最初の支配者となる。しかし時が経つにつれ、他者を客体にすることで、勝者は自らの主体性の本質、つまり他者に認められる可能性 を失っていく。真の自己意識は、奴隷化が克服され、対等な二人が互いを認め合うことができるようになって初めて可能になる。この過程において、否定的な特 質は取り消され、主観性の洞察は維持され、両者は対等なものとして新たな自己意識へと引き上げられる。 問題は、ヘーゲルが黒人や先住民は弁証法が「休止」しており、自然から抜け出せず、自己意識の自由に向けた弁証法的プロセスを開始することができないと信 じていることである。これが、彼が植民地化する「英雄の権利」があると言う理由である。ヨーロッパによる植民地化によってのみ、他者が人間の自由の行進の 一部になることができるのだ。したがって、バック=モルスのペースによれば、ヘーゲルにとってのハイチ革命とは、ヨーロッパの理想が植民地化を通じて他者 の自由を達成したことにほかならない: ハイチでは、彼ら(黒人)はキリスト教の原理に基づいて国家さえ形成した。ハイチでは、彼ら(黒人)はキリスト教の原則に基づいて国家さえ形成している。 彼らの祖国[アフリカ]では、最も衝撃的な専制主義が蔓延している......彼らの精神はまったく休眠状態にあり、自らの内に沈んだままで、何の進歩も ない......」。 ここには、植民地人種主義、弁証法体系、そしてヘーゲルが自己意識、進歩、自由といった「抽象的」概念をどのように理論化しているのかが、表裏一体であることがはっきりと見て取れる。 平等な自由という結果は良いことかもしれないが、この目的に向けたヘーゲルのシステムの全体的な動きは、ルソーの人種差別思想と、ヨーロッパ人が到着する まで「自然の状態」に閉じ込められていたとされる先住民の思想の欠如についての彼の主張から始まる。弁証法的思考は一般的な体系となり、ヘーゲルの成熟し た著作においては、文明人と未開人への言及よりも、存在と無といった抽象的なカテゴリーによって定義されるようになる。しかし、哲学の体系的人種主義を理 解するための課題は、露骨な人種主義から構造的人種主義への動きを追うことである。ヘーゲルを擁護する人々が言うのとは反対に、ヘーゲルの人種差別的な思 想を普遍的な思想体系へと抽象化することこそが問題なのである。この歴史を認めずに弁証法を使うことは、人種主義を私たちの概念に、ひいては私たちの信念 や実践に、無意識のうちに持ち込んでしまう危険性がある。普遍的平等についての弁証法的洞察に至る反人種主義的な道はあるのだろうか。 |
|
第二次世界大戦後、哲学者であり、詩人であり、マルティニークを長年リードしてきた政治家エメ・セゼール(1913-2008)は、ヘーゲルの哲学的傑作 『精神現象学』(1807)を読み終えた。読み終えると、彼は友人のレオポルド・センゴール(1906-2001)——同じく哲学者であり詩人でもあり、 セネガルの長年の指導者でもあった——に熱心にこの本を見せた。セゼールはヘーゲルの抽象哲学に、1930年代にセンゴールとセゼールがパリで創設に貢献 した黒人思想と美学を擁護する運動であるネグリチュードのプロジェクトにおける哲学的共犯者を見出していた。ヘーゲルの哲学は、黒人性を受け入れることは 普遍的な人類の進歩の一部であり、狭いアイデンティティに屈服することではないという、彼らの主張と同じことを言っていた。 セゼールとセンゴールは、反植民地主義思想家の中で、ヘーゲルの著作、とりわけ「普遍」と「特殊」といった一見相反するものが、新たな総合によって共通の 基盤を見出すことができる弁証法的哲学に意味を見出した唯一の人物ではなかった。革命指導者であり作家であるフランツ・ファノン(1925-61)、C・ L・R・ジェイムズ(1901-89)、アミルカル・カブラル(1924-73)もまた、ヘーゲルの作品に意味を見出すことになる。セニョール、セゼー ル、ファノンらにとって、弁証法の使用において、私が敷いた歴史は何を意味するのだろうか。彼らはヘーゲルの人種主義を偶然に自分の思考に持ち込んだのだ ろうか。 私はそうは思わない。これらの思想家たちは、ルソーにさかのぼる弁証法の人種差別的な歴史に直接言及はしなかったが、それでもヘーゲル思想の中心的な問題 を把握していた。弁証法的思考の価値を維持しながら、その根底にある人種差別的論理を批判しているのである。これはもちろん、弁証法の人種主義を扱う非常 に弁証法的な方法である。歴史を実際に前進させることができる新しい思考法を創造するために、弁証法の核心にある人種差別的矛盾を否定しようとするのであ る。ヘーゲルが信じていたのとは逆に、歴史から抜け出せないのは、アフリカ人やカリブ人ではなく、人種差別的な世界観を持つヘーゲル自身なのだ。歴史を前 進させるということは、人種主義に積極的に反対することである。これは弁証法そのものの昇華であり、ヘーゲルの洞察を維持し、取り消し、高揚させるための 反人種主義的な道を創造するものである。 |
|
| 弁証法的思考は、反レイシズムのためとはいえ、この人種差別的な歴史を私たちの思考に持ち込む危険をはらんでいる。 セニョール、セゼール、ファノンは、ルソーの人種差別的民族誌の基礎を拒否することによって、この弁証法的運動を成し遂げた。彼らは、宣教師デュ・テルト ルでさえ知っていたのに、哲学者たちが知らなかったこと、つまり、アメリカ大陸とアフリカの人々には独自の複雑な生活と論理があるということを回復したの である。セゼールはこう言う: われわれがヨーロッパを非難するのは、ヨーロッパが、まだその可能性を十分に発揮していない文明の勢いを断ち切ったこと、つまり、彼らが発展し、その中にある豊かな形態を完全に実現することを許さなかったことである。 そしてセンゴールは言う: 私は信じている......『ネグリチュードは弁証法的である』と。より正確には、私は......それが......本質的な貢献のアンサンブルを構成していると信じている。 とファノン: 私の自由の支えとして必然性を導入する弁証法は、私を自分自身から追放する。そうなのだ。黒人は一人ではなく、多くの黒人がいる。 ルソーやヘーゲルが、黒人や先住民はそれ自体では弁証法的でないと仮定 したのに対し、センゴール、セゼール、ファノンは、弁証法は、すべての民族の内的な複雑性を理解することによってのみ、正しく考えることができると主張し ている。それが達成されれば、文化的差異という植民地的論理から、セゼールとセンゴールが文化間の「授受のランデブー」と呼んだものへと移行することがで きる。例えば、フランスが自分たちの貿易モデルをアンティル諸島に押し付けるのではなく、両民族が互いに異なるモデルを学び合うことができ たはずだ。ヨーロッパから他の国へとしか持ち込めない弁証法的なプロセスではなく、このような代替的なモデルによって、人間の生活をどのようにアレンジす るかについて、より豊かで進化し続ける可能性が可能になるのである。このシステムにおける奴隷制度、人種主義、憎悪は決して正当化されることはないが、自 由と平等をより大きくするための弁証法的進歩は維持される。 このように、これらの作家が示すように、弁証法的思考は本質的に人種差別的なものではなく、また、他の哲学的歴史理解の名の下に、必ずしも捨て去られるべ きものでもない。とはいえ、哲学者たちは、弁証法的思考の近代的起源が、ルソーやヘーゲルといった哲学者たちの露骨な人種主義に直接たどりつくものである ことを認める必要がある。この明白な人種主義は、よくあることだが、これらの哲学者が発展させた概念に抽象化されたときに、暗黙のものとなった。今日、私 たちが弁証法的思考を用いるとき、たとえ反人種主義に奉仕するときであっても、この人種差別の歴史を認め、それと折り合いをつけなければ、私たちの思考に この人種差別の歴史を持ち込む危険性がある。 アメリカにおけるニューディールを類推することで、私が言いたいことが明確になるかもしれない。歴史家のアイラ・カッツネルソンが詳しく述べているよう に、ニューディールは、それが支援した地域社会にとって、とてつもない経済的成功を収めた。しかし、ニューディール政策にはかなりの程度、黒人が含まれて いなかった。先住民族との関係も複雑で、もちろん日系アメリカ人との関係は最悪だった。その結果、近代アメリカの福祉国家は、一般的な経済的不平等をへこ ませる一方で、人種的不平等を悪化させた。この遺産に対処することは、人種的不公正を是正することであり、経済的進歩を放棄することではない。同様に、弁 証法においても、その目的は人種的不公正を根絶し、その概念をより確かなものにすることであり、全体として放棄することではない。 哲学における反人種主義に真に取り組むのであれば、個々の思想家の人種主義や、哲学カリキュラムの多様性の欠如、哲学教員や学生の多様性の欠如に対処する 必要があるのは確かである。しかし、私たちの概念や思想に影響を与えている人種主義の微妙な形態についても、厳しい目を向けなければならないだろう。人種 主義によって発展した概念は弁証法だけではない。自律性、美学、そして自由の概念もまた、ヨーロッパ人の生活が野蛮人とみなされた人々といかに異なるかを 示す同じプロセスを通じて生み出された。セニョール、セゼール、ファノンが示しているように、だからといって、これらの概念が捨て去られなければならない わけではない。その結果、西洋の正典が失われるのではなく、哲学的思考が実際に改善されるのである。哲学体系は、現在の蹂躙から未来の賠償へと私たちを導 く強力な道具となりうる。しかし、そのためには、まず体系的な人種主義との折り合いをつけなければならない。 |
|
| https://aeon.co/essays/racism-is-baked-into-the-structure-of-dialectical-philosophy |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099