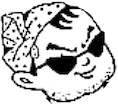
メキシコの時間(Carlos Fuentes)
Tiempo mexicano, por Carlos Fuentes, 1972
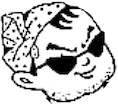
☆ げんちゃんはこちら(genchan_tetsu.html) 【翻訳用】海豚ワイドモダン(00-Grid-modern.html) (★ワイドモダンgenD.png)
| Desde la Conquista
hasta hoy, la historia de México es una segunda
búsqueda de la identidad, de la apariencia, una búsqueda nuevamente
tendida entre la necesidad y la libertad: más que conceptos, signos
vivos de un destino que, una vez, se resolvió en el encuentro de la
pura
fatalidad y el puro azar. Fatal para el indígena. Azaroso para el
español.
Más trágico que Edipo, México no acaba de reconocerse en su máscara. A
la fatalidad y al azar, opone el "albur", temible negación de los demás
que nos conduce al suicidio de no poder reconocernos fuera de .
nosotros mismos. El "albur", en México, es una operación del
lenguaje
que consiste en desviar el sentido llano de las palabras a fin de
dotarlas
de una intención insultante, agresiva, negadora de la personalidad de
los interlocutores. El "albur" imposibilita todo diálogo. Por ejemplo:
nadie puede decir, sencilla y rectamente, "Mi mujer está enferma", sin
que esto suscite una serie de "albures" verbales en torno a la
menstruación, la procreación, la luna, la cuaresma y la probable edad
de la señora. Las elaboradísimas fórmulas de la cortesía verbal en
México, el uso
del subjuntivo, la constante apelación al diminutivo, son protecciones
contra el "albur" y sus secuelas violentas. Se dice "Ésta es su casa''
a fin de que el invitado la respete como respetaría la casa propia; la
fórmula
encierra un temor al extraño, al ratero, al vándalo, al violador: las
casas mexicanas se esconden detrás de altísimos muros coronados por
vidrios rotos. Se dice "Si usted tuviese la bondad de prestarme ..."
porque
si se dice, secamente, "Préstame tal cosa'', la respuesta sería: "Y tú,
préstame a tu hermana''. Se dice "mamacita" porque la escueta expresión
"madre" puede desencadenar decenas de bromas, burlas, frases de doble
sentido y aun la más temible invitación edípica de México, país en
el que todos, menos el que habla, son hijos de la chingada: cada
mexicano es un hijo de la virgen rodeado por millones de tenebrosos
hijos
de puta. Lenguaje e identidad: la masa del pueblo indígena, pueblo
vencido, debió aprender la lengua de los amos y olvidar la lengua
nativa. El castellano es la lengua del otro, del conquistador. En sus
extremos, esta lengua se emplea para servir, humildemente, al patrón;
es
lengua de esclavos, cortés, susurrada, diminutiva, obsequiosa, dulce; y
se emplea para gritar, venido el momento, las temibles palabras de la
rebelión, el amor y la borrachera. Pero en su curso central, es el
lenguaje, simplemente, de la falta de identidad, del "albur" ofensivo y
de la
retórica hipócrita, tan hipócrita como los abrazos entre hombres en
México, cuya función original es saber si el otro viene empistolado. |
征
服から今日に至るまで、メキシコの歴史は、アイデンティティと外観を求める第二の探求であり、必然性と自由との間で再び引き伸ばされた探求である。先住民
にとっては運命だった。スペイン人にとってはアザロソである。オイディプスよりも悲劇的なメキシコは、その仮面から自分自身を認識することができない。運
命と偶然に対して、メキシコは 「アルブール 」を対立させる。「アルブール
」とは、他者に対する恐怖の否定であり、自分自身を外から認識することができないという自殺へと導くものである。メキシコにおける 「アルバー
」とは、言葉の平明な意味を逸脱させ、侮辱的で攻撃的な意図を持たせ、対話者の人格を否定することである。アルブール」はすべての対話を不可能にする。た
とえば、「妻が病気なんだ」と単純かつ正確に言うことはできない。そうすれば、月経、子作り、月、四旬節、女性の年齢に関する一連の「アルブール」が引き
起こされるからだ。メキシコの丁寧な言葉遣い、接続法の使用、些細な表現への絶え間ない訴えかけは、「アルブール」とその暴力的な余波から身を守るための
ものだ。メキシコの家は、割れたガラスで覆われた非常に高い塀の後ろに隠されている。メキシコの家屋は、割れたガラスに覆われた非常に高い塀の中に隠され
ている。私たちは「Si usted tuviese la bondade de prestarme ...」と言う。mamacita
「と言うのは、」mother
"という簡潔な表現が、何十ものジョーク、嘲笑、二重表現、そしてメキシコという国の最も恐ろしいエディプス的誘惑の引き金になるからである。言語とアイ
デンティティ:敗戦国民である先住民の大衆は、主人の言語を学び、母国語を忘れなければならなかった。スペイン語は他者、征服者の言語である。極端な言い
方をすれば、この言語は謙虚に主人に仕えるために使われ、奴隷の言語であり、礼儀正しく、ささやくように、矮小で、卑屈で、甘美な言葉であり、時が来れ
ば、反抗、愛、酩酊の恐ろしい言葉を叫ぶために使われる。そして、いざとなれば、反抗、愛、酩酊の恐ろしい言葉を叫ぶために使われる。しかし、その中心的
な過程においては、それは、単に、アイデンティティの欠如、攻撃的な「アルブル」、メキシコの男同士の抱擁のように偽善的なレトリックの言語であり、その
本来の機能は、相手が銃を持っているかどうかを知ることである。 |
| Esta profunda inquietud acerca
de su propia identidad -acerca de
su necesidad y de su libertad probables- es lo que hace de México un
país peligroso, un país apasionado. A fin de descubrirlo sin engaños,
México -como una calavera de Posada, como un monstruo de Cuevas- tiene
que saltar con un grito desgarrante de la orilla de la necesidad a la
orilla de la libertad: libertad política, cultural, personal,
económica. ¿Es de extrañar que la historia oficial de nuestro país sea
un
ejercicio de enmascaramiento positivista con el propósito de evadir esa
tensión, de volverla inocua? ..... |
メ
キシコが危険な国であり、情熱的な国である所以は、メキシコ自身のアイデンティティー、つまり、メキシコが必要としているであろうことと、メキシコが自由
であろうことについての、この深い不安である。欺くことなくそれを発見するために、メキシコは、ポサダの頭蓋骨のように、クエバスの怪物のように、必要性
の岸辺から自由の岸辺へ、政治的、文化的、個人的、経済的自由へと、突き刺すような叫び声とともに跳躍しなければならない。
我が国の公式の歴史が、この緊張を回避し、無害なものにすることを目的とした実証主義的仮面の練習であることが不思議でならない。 |
| Los carcomidos muros de adobe de
los jacales en el campo mexicano ostentan, con asombrosa regularidad,
anuncios de la Pepsi-Cola, De Quetzalcóatl a Pepsicóatl: al tiempo
mítico del indígena se sobrepone el
tiempo del calendario occidental, tiempo del progreso, tiempo lineal. |
メキシコの田園地帯にある、虫食いの泥壁の小屋の壁には、驚くほど規則的にペプシコーラの広告が貼られている。ケツァルコアトルからペプシコアトルへ:先住民の神話的な時間の上に、西洋の暦の時間、進歩の時間、直線的な時間が重なっている。 |
| ¿Por qué conductos llegó a
México este nuevo tiempo? Collingwood, en su Idea de la historia,
recuerda que Heródoto veía en la divinidad que ordena el curso de la
historia un poder "que se regocija en
trastornar y desordenar las cosas". Toda cultura cercana al origen vive
en el terror: habiendo conocido una cercana catástrofe en el pasado,
teme un Apocalipsis cercano en el futuro. La recientísima comunidad
helénica veía al mundo como cambio incesante; y lo que cambiaba mas
violentamente era la vida humana. Los dioses estaban identificados con
el terror y el cambio: Zeus o el trueno, Apolo o la pestilencia,
Poseidón
o el temblor de tierra. Pero esto también era cierto de la recientísima
comunidad azteca, fundada apenas doscientos años antes de la
Conquista. El recuerdo del origen se identifica con el temor del
futuro: la sociedad azteca, su religión, su política, su arte, son
exorcismos,
aplazamientos de la catástrofe temida; cada cincuenta y dos años, al
cumplirse el ciclo más vasto, lo anterior debe ser cancelado, negado,
destruido o recubierto como las siete sucesivas pirámides del centro
ceremonial ele Cholula; los hombres son sacrificados para aplazar la
catástrofe; los poetas cantan para recordar la brevedad de la vida.
Pero
Grecia, como señala Collingwood, se enfrenta y se reconcilia al hecho
de que la permanencia es imposible: Grecia es el reconocimiento de la
necesidad del cambio. Si por un lado la cultura griega trata de saívar
lo
sustancial, lo esencial, del azaroso mundo del cambio a través del
pensamiento de Parménides y Platón, por el otro se enfrenta a la
peripetia,
reconoce que las cosas pasan instantáneamente de la afirmación a la
negación, de la posición a la oposición, de la pequeñez a la grandeza,
del orgullo a la humillación, de la felicidad a la miseria: cambio,
historia y tragedia van unidos. Afrodita destruye instantáneamente el
orgullo de Fedra y 1;1. castidad de Hipólito: el cambio histórico es
aceptado
pero, al mismo tiempo, es salvado y humanizado por la forma trágica.
¿Por qué pudo Grecia pasar del testimonio del cambio a su comprensión
histórica y a su sublimación trágica, y el México indígena no?
Quizás porque Grecia era sociedad abierta y el mundo indígena mexicano
una sociedad cerrada. Grecia debió poner a prueba sus concepciones
propias enfrentándose con el exterior: Troya, Persia. El mundo
asiático, al negar y conformar a Grecia, la obliga a la crítica y a la
autocrítica. En México hubo una completa ausencia de crítica en la
sucesión guerrera, imperial, del mundo azteca: hubo gesta y mito, no
, tragedia. Cuando el México indígena conoció la tragedia, era
demasiado tarde: la confrontación con el mundo exterior equivalió a la
muerte; el mundo indígena no tuvo tiempo de criticarse; perdió de un
golpe
todos los instrumentos de su cultura. La tradición griega, en cambio,
es la de la tensión entre cambio y permanencia: el río de Heráclito se
vierte en el mar de Parménides, y en esa desembocadura brillan dos
islas de oro: la conciencia trágica y la aspiración comunitaria. |
こ
の新しい時代は、どのような経路でメキシコに伝わったのか?コリングウッドは『歴史の概念』の中で、ヘロドトスが、歴史の流れを支配する神性に「物事を混
乱させ、無秩序にすることに喜びを感じる力」を見出していたことを想起している。起源に近い文化は、恐怖の中で生きている。過去に近い大災害を経験してい
るため、近い将来、終末が訪れることを恐れているのだ。ごく最近のヘレニズム社会は、世界を絶え間ない変化と捉えていた。そして、最も激しく変化するのは
人間の生活だった。神々は恐怖と変化と同一視されていた。ゼウスは雷、アポロは疫病、ポセイドンは地震だった。しかし、これは征服のわずか 200
年前に設立されたごく最近のアステカ社会にも当てはまった。起源の記憶は未来への恐怖と結びついている。アステカ社会、その宗教、政治、芸術は、恐れる破
滅を追い払うための呪術であり、延期だ。52年ごとに、最も長い周期が満了すると、それまでのものはすべて取り消され、否定され、破壊され、または、チョ
ルラの儀式用中心地に立つ7つのピラミッドのように覆い隠される。人々は、大災害を延期するために犠牲にされ、詩人たちは、人生の短さを思い起こさせる歌
を歌う。しかし、コリングウッドが指摘するように、ギリシャは永続が不可能であるという事実と向き合い、和解している。ギリシャは変化の必要性を認識して
いるのだ。一方では、ギリシャ文化はパルメニデスやプラトンの思想を通じて、変化の偶然に満ちた世界から本質的なものを引き出そうとしている。他方では、
逆境に立ち向かい、物事は肯定から否定へ、立場から反対へ、小ささから大きさへ、誇りから屈辱へ、幸福から悲惨へと瞬時に変化することを認識している。変
化、歴史、悲劇は結びついている。アフロディーテは、フェドラの誇りとヒポリトの貞操を瞬時に破壊する。歴史的変化は受け入れられるが、同時に、悲劇的な
形によって救われ、人間化される。なぜギリシャは変化の証からその歴史的理解、そして悲劇的な昇華へと至ることができたのに、先住民メキシコはそうできな
かったのか?おそらく、ギリシャは開かれた社会であり、先住民メキシコは閉じた社会だったからだ。ギリシャは、トロイ、ペルシャといった外部と対峙するこ
とで、自らの概念を試す必要があった。アジアの世界は、ギリシャを否定し、形作ることによって、ギリシャに批判と自己批判を迫ったのだ。メキシコでは、ア
ステカ帝国の戦争と帝国の継承において、批判がまったく存在しなかった。英雄伝説と神話があっただけで、悲劇はなかった。先住民メキシコが悲劇を知った時
には、すでに手遅れだった。外の世界との対立は死を意味し、先住民社会は自らを批判する時間もなく、文化のあらゆる手段を一挙に失った。一方、ギリシャの
伝統は、変化と永続の緊張関係にある。ヘラクレイトスの川はパルメニデスの海に注ぎ込み、その河口には二つの黄金の島が輝いている。それは、悲劇的意識と
共同体への憧れだ。 |
| La llegada de la cultura
española a México significó varias cosas. Primero, que la herencia
original de Grecia se presentó mutilada por la herencia de Roma; la
apertura ante el cambio fue convertida por Roma
en idea de la continuidad, y la permanencia fue suplantada por el
principio de legitimidad: el sustancialismo ha triunfado sobre el
cambio:
sólo lo incambiable es cognoscible. Las ideas romanas de la continuidad
y la legitimidad imperiales son apropiadas por España en cuanto
convienen a su propio proyecto imperial, pero siempre en estado de
conciliación con la herencia medieval: ese proyecto debe coincidir con
la trascendencia divina, con el proyecto de Dios que se impone al mundo
sin consultar la voluntad de los hombres. |
ス
ペイン文化のメキシコへの到来は、いくつかのことを意味した。まず、ギリシャの本来の遺産は、ローマの遺産によって損なわれた。変化への開放性は、ローマ
によって継続性の思想に変えられ、永続性は正当性の原則に取って代わられた。実質主義が変化に勝利し、不変のものだけが認識可能となった。ローマの継続性
と帝国の正当性の思想は、スペインの帝国プロジェクトに都合が良い限り、スペインによって採用されたが、それは常に中世の遺産と調和した形であった。その
プロジェクトは、神の意志に反して人間に課せられた、神の超越性、神の計画と一致しなければならない。 |
| Sin embargo, el traslado a
México de este organicismo medieval
como sostén de la legitimidad imperial coincide con la revuelta moderna
del individualismo crítico, por un lado, y el utopismo colectivo, por
el otro. El primero tiene sus raíces romanas e hispánicas en el
estoicismo y el epicureísmo: representa la decisión de salvar a la
persona y sus valores ante la imposibilidad de transformar al mundo
circundante, y es el origen de una actitud constante de las elites de
Hispanoamérica. El segundo tiene las suyas en la herejía medieval
antiagustiniana de Pelagio: el dogma y la vida sólo son conciliables a
través de la libertad humana, agente directo de la gracia divina. Esta
proposición reabre la posibilidad política en la comunidad cristiana;
replantea el tema de la ciudad, de la organización de la polis, lugar
donde se concilian el plan divino y el plan humano. U Topos:No hay
tal lugar, dice Tomás Moro, y su negación es una aparición: su Utopía
es ante todo un deseo y América, antes de ser, es deseada. No hay tal
lugar y sí hay tal lugar: no es otra la raíz más secreta y profunda de
la
cultura hispanoamericana; Topía y Utopía son los países superpuestos
que están en dos lugares, en dos mundos, el Viejo y el Nuevo: son los
países, al cabo, de Pablo Neruda y Jorge Luis Borges, de Octavio Paz
y Julio Cortázar, de Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, de
Wifredo Lam y José Luis Cuevas. Pues detrás de las carabelas de Colón
llegó a las costas americanas la nave de los locos, el barco de la
estulticia, the ship of fools: Erasmo venía al timón, Moro era el
vigía,
Campanella el cartógrafo y en las galeras viajaban Jerónimo Bosco y
los fantasmas nonatos de Don Quijote y Don Juan. El espacio arruinado
de la Ciudad de Dios había sido invadido por la razón humana;
pero Erasmo de Rotterdam instala, en el corazón de la racionalidad, el
discurso de la locura: la locura erasmista dialoga con el mundo, se
elogia para limitar la locura de la razón, habla de las otras
posibilidades
del hombre: habla de la utopía. No hay tal lugar y sí hay tal lugar:
Campanella, en La ciudad del sol ubica la Utopía en América y la Utopía
es cumplir dos designios de Dios viviendo en una comunidad libre
y bajo una sola ley. La gran empresa conciliadora y comunitaria de
Moro, Campanella, Erasmo, Vives y Valdés es la esperanza del nuevo
mundo y Vasco de Quiroga la encarna fugazmente en las comunidades
michoacanas: "Porque no en vano sino con mucha causa y razón
éste de acá se llama Nuevo Mundo y eslo Nuevo Mundo, no porque
se halló de nuevo sino porque es en gentes y cuasi en todo como fue
aquel de la edad primera y de oro ..." |
し
かし、この中世の有機体論が帝国の正当性の基盤としてメキシコに移転したことは、一方では批判的個人主義の現代的な反乱、他方では集団的ユートピア主義の
台頭と時期を同じくしている。前者は、ローマとスペインのストイシズムとエピクロス主義にルーツを持ち、周囲の世界を変えることが不可能であるならば、個
人とその価値観を救うという決断を表しており、スペイン系アメリカ人のエリート層の絶え間ない姿勢の源となっている。後者は、中世の反アウグスティヌス派
のペラギウス派の異端にその根源がある。教義と生活は、神の恵みの直接的な媒介者である人間の自由を通じてのみ調和できる。この主張は、キリスト教共同体
における政治的可能性を再開放し、都市、ポリス(共同体)の組織、すなわち神の計画と人間の計画が調和する場所というテーマを再考する。U
Topos:そのような場所はない、とトマス・モアは言う。その否定は出現であり、彼のユートピアはまず第一に願望であり、アメリカは存在する前に願望と
して存在していた。そのような場所はない、そしてそのような場所はある:これは、ヒスパニック・アメリカ文化の最も秘密で深い根源に他ならない。トピアと
ユートピアは、2つの場所、2つの世界、旧世界と新世界に重なり合う国だ。結局のところ、それらはパブロ・ネルーダとホルヘ・ルイス・ボルヘス、オクタ
ヴィオ・パスとジュリオ・コルタサール、アレホ・カルペンティエルとガブリエル・ガルシア・マルケス、ウィフレド・ラムとホセ・ルイス・クエバスなどの国
々なのだ。コロンブスの船の後に、アメリカ大陸の海岸に「狂人の船」、愚か者の船、the ship of fools
が到着した。エラスムスが舵を取り、モロが見張り、カンパネッラが航海士を務め、船室にはジェロニモ・ボスコと、ドン・キホーテとドン・ファンの未熟児た
ちの幽霊たちが乗っていた。神の都の荒廃した空間は、人間の理性によって侵略されていた。しかし、エラスムス・デ・ロッテルダムは、理性の中心部に狂気の
言説を植え付けた[邦訳
p.38]。エラスムスの狂気は世界と対話し、理性の狂気を制限するために自らを称賛し、人間の他の可能性について語る。つまり、ユートピアについて語る
のだ。そのような場所はない、しかしそのような場所はある:カンパネッラは『太陽の都市』で、ユートピアをアメリカに置き、ユートピアとは、自由な共同体
の中で、一つの法律の下で、神の二つの計画を実現することだとする。モロ、カンパネッラ、エラスムス、ビベス、バルデスの偉大な調和と共同体の事業は、新
しい世界の希望であり、バスコ・デ・キロガはミチョアカン州の共同体でそれを一瞬だけ体現する。「なぜなら、この地が新世界と呼ばれるのは、無駄ではな
く、多くの理由と根拠があるからだ。それは、この地が新たに発見されたからではなく、この地の人々と、ほぼすべてが、最初の黄金時代と同じだからだ……」 |
| Pero esta empresa de los que
Alfonso Reyes llamó "los padres izquierdistas de América" se frustró;
la "edad primera y de oro", según
el propio Quiroga, "por nuestra malicia y gran codicia de nuestra
nación ha venido a ser de hierro y peor". La empresa espiritual de
Erasmo fracasa en América; si el humanista de Rotterdam intenta la
suprema conciliación del misterio religioso y la razón práctica gracias
a la conciencia irónica uel yo, relativizando tanto al dogma como al
poder, España, con la contrarreforma, absolutiza por igual, y
trasplanta a tierras americanas, dogma y poder. Nuevamente, la "locura"
erasmista debe superar, en América Latina, el tardío pero oportuno
florecimiento de nuestros arte y literatura modernos. Pero en el siglo
XVI, como indica Eugenio Imaz, Moro fue martirizado y su martirio
consistió en ser testigo de la Utopía ante la Topía, de la razón ante
la
razón de Estado: Maquiavelo vence a Moro, acaparando la racionalidad
como proyecto pragmático del Estado; Felipe II vence a Moro y a
Maquiavelo, identificando la razón del imperio español con el proyecto
divino. El virreinato, el poder absolutista de los Austrias, la
Contrarreforma y la Inquisición nos separan durante cuatro siglos de la
aventura moderna de Europa: España se cierra y nos encierra. Una
intensa esquizofrenia política, moral e intelectual se apodera de la
América española: el trasplante español nos ofrece lo peor y nos niega
lo mejor de España; Cuba puede ser una Andalucía más graciosa que
la propia Andalucía, pero México es una Castilla más sombría que la
propia Castilla; los fermentos combatidos, pero existentes; en España
-tradicionalistas, como las comunidades, germanías y hermandades;
renovadores, como alumbrados y eramistas- no logran pasar las barreras
de las aduanas del espíritu en América; las tradiciones de gobierno
propio que abundan en España no encuentran equivalente en
América; el cabildo es una institución ficticia y la universidad se va
reduciendo, escolásticamente, a la parquedad del trivio y el cuadrivio;
la revisión crítica del tiempo moderno en todos sus órdenes -Bodino
y el nuevo Estado; Copérnico, Kepler, Galileo y la nueva concepción
física del universo; Erasmo, Bruno y el nuevo régimen intelectual, no
llegan sino sordamente a nuestro mundo; y ni siquiera con sordera
aparecen en él la teoría o la práctica del nuevo capitalismo expansivo,
individualista, fundado en la identificación del orden natural
(evidente) y del orden providencial (revelado). Pero la suprema
paradoja de la colonización española es que fuimos colonizados
por un país que
pronto se convirtió en país colonizado por las potencias mercantiles
del norte de Europa. La fuga del tesoro americano a los Países Bajos,
y de allí a Inglaterra y Alemania para pagar las importaciones
españolas financió, en efecto, buena parte de la expansión industrial
de esas
regiones. España fue las Indias de la Europa capitalista. |
し
かし、アルフォンソ・レイエスが「アメリカの左派の父たち」と呼んだこの企業は挫折した。クイロガ自身によると、「最初の黄金時代」は、「私たちの悪意
と、私たちの国の大きな貪欲によって、鉄の時代、さらに悪い時代になってしまった」のだ。エラスムスの精神的な事業はアメリカで失敗に終わった。ロッテル
ダムの人文主義者が、皮肉な自己意識によって宗教的謎と実践的理性を最高に調和させようとしたのに対し、スペインは反宗教改革によって、教義と権力を同様
に絶対化し、それらをアメリカ大陸に移植した。再び、エラスムスの「狂気」は、ラテンアメリカにおいて、遅ればせながら適切な時期に開花した私たちの現代
芸術と文学を乗り越えなければならない。しかし16世紀、エウジェニオ・イマズが指摘するように、モロは殉教し、その殉教は、トピア(現実)の前にユート
ピアを、国家の理性に理性を目撃することだった。マキャヴェリはモロを打ち負かし、国家の現実的なプロジェクトとして合理性を独占した。フェリペ2世はモ
ロとマキャヴェリを打ち負かし、スペイン帝国の理性を神のプロジェクトと同一視した。副王領、ハプスブルク家の絶対主義、反宗教改革、異端審問は、私たち
を4世紀にわたってヨーロッパの近代的な冒険から隔てた。スペインは閉鎖し、私たちを閉じ込めた。激しい政治的、道徳的、知的分裂がスペイン領アメリカを
覆う。スペインの移植は、スペインの最悪の部分をもたらし、その最良の部分を否定する。キューバはアンダルシアよりも優雅なアンダルシアかもしれないが、
メキシコはカスティーリャよりも陰鬱なカスティーリャだ。抑圧されながらも存在する発酵。スペインでは、伝統主義者たち(コミュニティ、ゲルマニア、兄弟
団など)
革新派(イルムラードやエラミスタ)は、アメリカにおける精神の関門を突破できない。スペインに豊富にある自治の伝統は、アメリカには見当たらない。カビ
ルドは架空の制度であり、大学は、トリヴィオとクアドリヴィオの貧弱さに、学問的に縮小している。近代をあらゆる面で批判的に見直す動き(ボドノと新しい
国家、
コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、そして新しい宇宙観、エラスムス、ブルーノ、そして新しい知的体制は、私たちの世界にはほとんど影響を与えていない。
そして、自然秩序(明白なもの)と摂理(啓示されたもの)の同一性に基づく、拡大主義的で個人主義的な新しい資本主義の理論や実践は、まったく影響を与え
ていない。しかし、スペインの植民地化の最大のパラドックスは、私たちが、すぐに北ヨーロッパの商業大国によって植民地化された国によって植民地化された
ことだ。アメリカ大陸からオランダ、そしてイギリスとドイツへと流出した財宝は、スペインの輸入代金を支払うために、これらの地域の産業拡大の大部分を
賄った。スペインは、資本主義ヨーロッパのインディアスだったのだ。 |
| Este rechazo de la modernidad a
partir del Concilio de Trento conduce a España y a sus colonias a la
decadencia y al descontento. ¿Es de
extrañar que, al obtener la independencia, la América Latina haya
optado por la fórmula del éxito, haya rechazado por igual la mezcla
inoperante del catolicismo medieval con centralismo absolutista y la
promesa frustrada de la utopía renacentista, corrompida por la épica de
la Conquista y la praxis de la colonización, para optar por el
modelo triunfante, el modelo del progreso, el empirismo, el pragmatismo
y el
pacto social lockiano? La Independencia se propuso recuperar el tiempo
perdido, digerir en unos cuantos años la experiencia europea a
partir del Renacimiento, asemejarnos cuanto antes a los modelos
deslumbrantes del progreso: Francia, Inglaterra, los Estados Unidos.
Pero
-y éste es un inmenso pero- esta opción nos condujo a una nueva
esquizofrenia: atruibuimos al progreso moderno las cualidades de
nuestro utopianismo frustrado; convertimos en nuestras utopías modernas
los hacinamientos de Londres y Nueva York y las fábricas de
Pittsburgh y Manchester, es decir, todo aquello que derivando del
mundo sensible del ser, niega al mundo ideal del deber ser. El
pragmatismo del mundo capitalista había triunfado sobre el utopismo del
mundo renacentista; nosotros, al independizarnos de España, pretendímos
disfrazar el progreso de utopía, crear la polis comunitaria, ideal,
con cuanto la negaba. No es lo mismo la ciudad de Campanella y
Moro, comunidad auténtica que disuelve los contrarios, que la ciudad
de Locke, que atomiza a una polis que no tiene más razón de ser que
la protección de la propiedad privada, llamándola "democracia" en su
aplicación interna e "imperalismo" en su aplicación externa. La
paradoja de Amércia Latina es que ha optado por la ideología de sus
explotadores, rindiendo pleitesía al positivismo liberal y al tiempo
antiutópico
del progreso, del ser, contra el tiempo moral del deber ser. Aquél se
mide; éste se desea y se imagina. En otras palabras: no hay vedadera
revolución sin referencia a la utopía. "Vio bien Campanella: la razón
de
Estado prefiere la parte al todo, el individuo al género humano, la
sociedad a la comunidad" (Ímaz, Topíay utopía). La utopía, como la
revolución, invierte esas preferencias. México y América Latina, en
cambio,
optaron por la ideología de la razón de estado, que era la del éxito,
la
del progreso, la de la defensa de la propiedad privada, y la
justificaron
con la teoría rousseauniana, incorporada a todas nuestras
constituciones, de la voluntad general. Pero no se percataron de que,
en la práctica europea y norteamericana, la voluntad general, lejos de
ser la
voluntaria comunidad de todos, era el disfraz moral de la clase
burguesa, de su particular interés económico travestido de interés
general y
hasta universal. Y el interés universal del capitalismo se llama
imperialismo. Y nosotros somos sus víctimas. |
ト
レント公会議以降、近代化を拒否したことは、スペインとその植民地を衰退と不満へと導いた。独立を獲得したラテンアメリカが、中世のカトリックと絶対主義
的中央集権主義の機能不全な混合、そして征服の叙事詩と植民地化の現実によって腐敗したルネサンスのユートピアの挫折を同様に拒否し、勝利したモデル、進
歩のモデル、経験主義、
ロックの社会契約という成功の公式を選んだことは、不思議なことだろうか?独立は、失われた時間を取り戻し、ルネサンス以降のヨーロッパの経験を数年で消
化し、フランス、イギリス、アメリカといった、輝かしい進歩のモデルにできるだけ早く近づこうとしたものだった。しかし、この選択は私たちを新たな分裂へ
と導いた。私たちは、現代の進歩に、私たちの挫折したユートピア主義の特質を見出し、ロンドンやニューヨークの過密状態、ピッツバーグやマンチェスターの
工場、つまり、感覚的な存在の世界から派生し、理想的な存在の世界を否定するあらゆるものを、私たちの現代のユートピアに変えてしまったのだ。資本主義世
界の現実主義は、ルネサンス世界のユートピア主義に勝利した。私たちは、スペインから独立する際に、進歩をユートピアで覆い隠し、それを否定する理想的な
共同体、ポリスを創り出そうとした。カンパネッラとモロの都市、つまり対立を解消する真の共同体と、ロックの都市、つまり私有財産の保護以外に存在理由の
ないポリスを細分化し、その内部では「民主主義」と呼び、外部では「帝国主義」と呼ぶ都市とは、まったく異なるものなんだ。ラテンアメリカのパラドックス
は、その搾取者のイデオロギーを選択し、自由主義的実証主義と、道徳的な「あるべき」時間に対して、進歩の反ユートピア的な「ある」時間に服従したこと
だ。前者は測定可能であり、後者は願望であり、想像だ。言い換えれば、ユートピアを参照しない真の革命は存在しない。「カンパネッラは正しく見抜いてい
た。国家の理は、全体よりも部分、人類よりも個人、社会よりも共同体を優先する」(イマズ、『トピアとユートピア』)。ユートピアは、革命と同様に、これ
らの優先順位を逆転させる。一方、メキシコとラテンアメリカは、成功、進歩、私有財産の防衛という国家の理性のイデオロギーを選択し、それを、すべての憲
法に組み込まれたルソーの「一般意志」の理論で正当化した。しかし、彼らは、ヨーロッパやアメリカの現実において、一般意志は、すべての人の自発的な共同
体ではなく、ブルジョア階級の道徳的仮装であり、その特定の経済的利益を一般利益、さらには普遍的利益と偽装したものにすぎないことに気づかなかった。そ
して、資本主義の普遍的利益は帝国主義と呼ばれている。そして、私たちはその犠牲者なのだ。 |
| No niego que esta opción haya
sido natural. La filosofía de la Ilustración, como Jano, tenía dos
caras. Mirando al pasado, afirmaba: todo, antes de nosotros, ha sido
bárbaro, irracional y supersticioso.
Mirando hacia el futuro proclamaba: de aquí en adelante, sólo habrá
un progreso ilimitado. Nada, en apariencia, convenía más a países que
querían negar totalmente el pasado indígena y colonial e incorporarse
a la marcha optimista del progreso. Sin embargo, la Ilustración fundaba
sus ideas en un concepto universal e incambiable de la naturaleza
humana; pero esa naturaleza humana no era la nuestra, sino la de los
europeos de fines del siglo XVIII. De allí la pregunta de Momesquieu:
"¿Cómo es posible ser persa?", que de hecho implicaba preguntarse:
¿cómo es posible ser mexicano o argentino? El eurocentrismo de este
pensamiento culmina en cierto modo con la afirmación del romántico
alemán Herder: el sistema solar es el centro del universo físico; la
tierra es el centro del sistema solar; Europa es el centro de la
tierra; sólo
en nuestros días se ha vuelto evidente que existe una pluralidad de
culturas que suponen una pluralidad de valores: todos somos centrales
porque todos somos excéntricos. |
こ
の選択肢が自然だったことは否定しない。啓蒙主義の哲学は、ヤノスのように二つの顔を持っていた。過去を振り返り、次のように主張した:私たち以前に存在
したものはすべて、野蛮で、非合理的で、迷信的だった。未来を見つめ、次のように宣言した:これからは、無限の進歩しか存在しない。表面上は、先住民や植
民地時代の過去を完全に否定し、進歩の楽観的な流れに飛び込みたいと願う国々にとって、これほどふさわしいものはなかった。しかし、啓蒙主義は、普遍的で
不変の人間の性質という概念にその思想の基盤を置いていた。しかし、その人間の性質は、私たちのものではなく、18世紀末のヨーロッパ人のものだった。そ
こからモメスキエの「ペルシャ人であることは可能か」という疑問が生まれた。これは、実際には「メキシコ人であることは可能か、アルゼンチン人であること
は可能か」という疑問を意味していた。この考え方のヨーロッパ中心主義は、ドイツのロマン派哲学者ヘルダーの主張で頂点に達する。太陽系は物理的な宇宙の
中心であり、地球は太陽系の中心であり、ヨーロッパは地球の中心である。しかし、今日になって初めて、多様な文化が存在し、それらが多様な価値観を前提と
していることが明らかになった。私たちは皆、中心である。なぜなら、私たちは皆、偏心しているからだ。 |
| Muchos sectores urbanos de
México, en 1971, han logrado realizar el suefio del progreso moderno y,
casi, vivir en Monterrey como en
Milán, en Guadalajara como en Lyon o en la ciudad de México como
en Los Angeles. Esta meta, sin embargo, se ha alcanzado, nuevamente,
a destiempo: ha coincidido con las revueltas, dentro de las
civilizaciones industriales, contra la tecnocracia, la destrucción del
medio ambiente, la contaminación, los guetos urbanos y la falsificación
de los
medios modernos de comunicación: contra el pacto fáustico, en suma,
del trueque del alma por bienes de consumo frágiles e innecesarios. Ha
coincidido, además, con el desenmascaramiento de las justificaciones
ideológicas que, a partir de Locke, Rousseau y Adam Smith, constituían
la base de la eficacia pragmática y de la buena conciencia moral
de Occidente. El genocidio y el fracaso militar en Vietnam y las
revelaciones de los documentos del Pentágono sobre el modus operandi
del
poder han desnudado para siempre a la filosofía ético-positivista del
industrialismo capitalista. El asesinato de la democracia socialista en
Checoslovaquia, por otra parte, ha dejado sin máscara a la
tecnoburocracia soviética que, como sus congéneres del Occidente lo
hacían con
los filósofos de la Ilustración, se enmascaraba con la herencia
libertaria
de Marx, Engels y Lenin. |
1971
年、メキシコの多くの都市部は、近代的な発展の夢を実現し、モンテレイでミラノのように、グアダラハラでリヨンのように、メキシコシティでロサンゼルスの
ように暮らすことがほぼ可能になった。しかし、この目標は再び時期尚早に達成された。それは、産業文明内部におけるテクノクラシー、環境破壊、汚染、都市
のスラム化、現代のメディアの偽造に対する反乱と重なったからだ。要するに、魂を壊れやすい不要な消費財と交換するという、ファウストの契約に対する反乱
だった。さらに、ロック、ルソー、アダム・スミス以来、西洋の実用主義的効率性と道徳的良心の基盤を成していたイデオロギー的正当化の虚構が暴かれた時期
とも重なっている。ベトナムでの虐殺と軍事的失敗、そしてペンタゴン文書による権力の運営手法の暴露は、資本主義的産業主義の倫理的・実証主義的哲学を永
遠に暴き出した。一方、チェコスロバキアにおける社会主義民主主義の暗殺は、西側の同類が啓蒙思想家たちに対して行ったように、マルクス、エンゲルス、
レーニンの自由主義的遺産を覆い隠していたソビエトのテクノ官僚制の仮面を剥ぎ取った。 |
| Nuestro drama es que hemos
accedido a la sociedad urbana e industrial sólo para preguntarnos si el
esfuerzo valió la pena; si el modelo que venimos persiguiendo desde el
siglo XIX es el que más nos
conviene; si a lo largo del pasado siglo y medio no hemos seguido
actuando como entes colonizados, copiando acríticamente los prestigios
materiales de la sociedad capitalista; si no hemos sido capaces, en
fin,
de inventar nuestro propio modelo de desarrollo. |
私
たちのドラマは、都市化・工業化社会に参入したにもかかわらず、その努力が価値があったのか、19世紀から追求してきたモデルが私たちに最も適したものな
のか、この150年間、植民地としての行動を取り続け、資本主義社会の物質的な栄華を無批判に模倣してきたのではないか、結局、私たち自身の開発モデルを
考案することができなかったのではないか、と疑問を抱くようになったことにある。 |
| No podemos regresar a
Quetzalcóatl; Quetzalcóatl tampoco regresará a nosotros. Como Godot,
Quetzalcóatl se fue para siempre y sólo
regresó disfrazado de conquistador espafiol o de príncipe austriaco.
¿Debemos, por ello, enajenarnos a Pepsicóatl? Sería el camino más
fácil, pero no el más feliz. México se encuentra actualmente en un
grado de desarrollo capitalista intermedio: el que el teórico de la
subordinación imperialista, W W Rostow, llama "la etapa del despegue".
Pero ese desarrollo, una vez que la burguesía mexicana aprovechó
para sí las reformas revolucionarias, sepultando de paso la ideología
revolucionaria, carece hoy de metas verdaderas en el orden de la
justicia y, también, en el de la imaginación: se trata de un desarrollo
por el
desarrollo mismo que al cabo, nos hace persistir en el atraso y nos
convierte en depositarios del excedente plástico, descafeinado y
korequizado de la gran industria norteamericana: somos el Bajo
Chaparral de la
producción y el consumo de la metrópoli yanqui. Quetzalcóatl nos
prometía el Sol; Pepsicóatl nos promete una lavadora Bendix pagable
a plazos. Los atractivos del estilo de vida norteamericana
transplantados a México generan, a través de los medios de difusión, un
segundo
problema; el de la aglomeración irracional en las urbes mayores. Cinco
mil personas llegan diariamente del campo a la ciudad de México,
atraídas en gran medida por el espejismo nylon que les ofrecen la
radio, el cine, los anuncios y la televisión (y expulsadas del campo,
en
medida aún mayor, por las condiciones de injusticia que en él privan).
Son los hijos de Zapata que se convertirán en hijos de Sánchez. |
私
たちはケツァルコアトルに戻ることはできない。ケツァルコアトルも私たちのもとには戻ってこない。ゴドーのように、ケツァルコアトルは永遠に去り、征服者
やオーストリアの王子に扮して戻ってきただけだった。だからといって、ペプシコアトルに身を委ねるべきだろうか?それは最も簡単な道だが、最も幸せな道で
はない。メキシコは現在、資本主義発展の中間段階、つまり帝国主義的従属の理論家
W・W・ロストウが「離陸段階」と呼ぶ段階にある。しかし、メキシコブルジョアジーが革命改革を自分たちに有利に利用し、その過程で革命思想を葬り去った
結果、今日のこの発展は、正義の面でも想像力の面でも、真の意味での目標を欠いている。それは、結局、私たちを後進性に留まらせ、北米の大企業の余剰生産
物の受け皿にしてしまう、開発のための開発にすぎない。私たちは、ヤンキーの首都の生産と消費の「バホ・チャパラル」なんだ。ケツァルコアトルは私たちに
太陽を約束したが、ペプシコアトルは分割払いで買えるベンディックス製の洗濯機を約束している。メキシコに移植されたアメリカ的なライフスタイルの魅力
は、マスメディアを通じて、大都市への不合理な人口集中という第二の問題を引き起こしている。毎日5000人が、ラジオ、映画、広告、テレビが提供するナ
イロン製の幻想に惹かれて、農村からメキシコシティにやって来る(そして、農村での不公正な状況によって、さらに多くの人々が農村から追放されている)。
彼らは、サパタの子供たちであり、サンチェスの子供たちとなるだろう。 |
| https://laresolana.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/8-1-fuentes-tiempo-mexicano.pdf |
☆カルロス・フエンテス
| Carlos Fuentes Macías (/ˈfwɛnteɪs/;[1] Spanish: [ˈkaɾlos ˈfwentes] ⓘ; November 11, 1928 – May 15, 2012) was a Mexican novelist and essayist. Among his works are The Death of Artemio Cruz (1962), Aura (1962), Terra Nostra (1975), The Old Gringo (1985) and Christopher Unborn (1987). In his obituary, The New York Times described Fuentes as "one of the most admired writers in the Spanish-speaking world" and an important influence on the Latin American Boom, the "explosion of Latin American literature in the 1960s and '70s",[2] while The Guardian called him "Mexico's most celebrated novelist".[3] His many literary honors include the Miguel de Cervantes Prize as well as Mexico's highest award, the Belisario Domínguez Medal of Honor (1999).[4] He was often named as a likely candidate for the Nobel Prize in Literature, though he never won.[5] | カルロス・フエンテス・マシアス(/ˈfwɛnteɪs/;[1]
スペイン語: [ˈkaɾlos ˈfwentes] ⓘ; 1928年11月11日 -
2012年5月15日)は、メキシコの小説家、エッセイスト。主な作品に『アルテミオ・クルスの死』(1962年)、『オーラ』(1962年)、『テラ・
ノストラ』(1975年)、『オールド・グリンゴ』(1985年)、『クリストファー・アンボーン』(1987年)などがある。『ニューヨーク・タイム
ズ』の訃報記事では、フエンテスは「スペイン語圏で最も尊敬される作家の一人」であり、1960年代から70年代にかけてのラテンアメリカ文学の爆発的
ブーム「ラテンアメリカ・ブーム」に重要な影響を与えた人物と評された[2]。一方、『ガーディアン』は彼を「メキシコで最も称賛される小説家」と称し
た。[3]
彼の多くの文学賞には、ミゲル・デ・セルバンテス賞およびメキシコ最高の栄誉であるベリサリオ・ドミンゲス栄誉賞(1999年)が含まれる。[4]
彼はノーベル文学賞の有力候補としてたびたび挙げられたが、受賞はなかった。[5] |
| Life and career Fuentes was born in Panama City, the son of Berta Macías and Rafael Fuentes, the latter of whom was a Mexican diplomat.[2][6] As the family moved for his father's career, Fuentes spent his childhood in various Latin American capital cities,[3] an experience he later described as giving him the ability to view Latin America as a critical outsider.[7] From 1934 to 1940, Fuentes' father was posted to the Mexican Embassy in Washington, D.C.,[8] where Carlos attended English-language school, eventually becoming fluent.[3][8] He also began to write during this time, creating his own magazine, which he shared with apartments on his block.[3] In 1938, Mexico nationalized foreign oil holdings, leading to a national outcry in the U.S.; he later pointed to the event as the moment in which he began to understand himself as Mexican.[8] In 1940, the Fuentes family was transferred to Santiago, Chile. There, he first became interested in socialism, which would become one of his lifelong passions, in part through his interest in the poetry of Pablo Neruda.[9] He lived in Mexico for the first time at the age of 16, when he went to study law at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) in Mexico City with an eye toward a diplomatic career.[3] During this time, he also began working at the daily newspaper Hoy and writing short stories.[3] He later attended the Graduate Institute of International Studies in Geneva.[10] In 1957, Fuentes was named head of cultural relations at the Secretariat of Foreign Affairs.[8] The following year, he published Where the Air Is Clear, which immediately made him a "national celebrity"[8] and allowed him to leave his diplomatic post to write full-time.[2] In 1959, he moved to Havana in the wake of the Cuban Revolution, where he wrote pro-Castro articles and essays.[8] The same year, he married Mexican actress Rita Macedo.[3] Considered "dashingly handsome",[6] Fuentes also had high-profile affairs with actresses Jeanne Moreau and Jean Seberg, who inspired his novel Diana: The Goddess Who Hunts Alone.[8] His second marriage, to journalist Silvia Lemus, lasted until his death.[11] Fuentes served as Mexico's ambassador to France from 1975 to 1977, resigning in protest of former President Gustavo Díaz Ordaz's appointment as ambassador to Spain.[2] He also taught at Cambridge, Brown, Princeton, Harvard, Columbia, University of Pennsylvania, Dartmouth, and Cornell.[11][12] His friends included Luis Buñuel, William Styron, Friedrich Dürrenmatt,[8] and sociologist C. Wright Mills, to whom he dedicated his book The Death of Artemio Cruz.[13] Once good friends with Nobel-winning Mexican poet Octavio Paz, Fuentes became estranged from him in the 1980s in a disagreement over the Sandinistas, whom Fuentes supported.[2] In 1988, Paz's magazine Vuelta carried an attack by Enrique Krauze on the legitimacy of Fuentes' Mexican identity, opening a feud between Paz and Fuentes that lasted until Paz's 1998 death.[8] In 1989, he was the subject of a full-length PBS television documentary, "Crossing Borders: The Journey of Carlos Fuentes," which also aired in Europe and was broadcast repeatedly in Mexico.[14] Fuentes fathered three children, only one of whom survived him: Cecilia Fuentes Macedo, born in 1962.[2] A son, Carlos Fuentes Lemus, died from complications associated with hemophilia in 1999 at the age of 25. A daughter, Natasha Fuentes Lemus (born August 31, 1974), died of an apparent drug overdose in Mexico City on August 22, 2005, at the age of 30.[15] |
人生とキャリア フエンテスは、ベルタ・マシアスとラファエル・フエンテスの息子としてパナマシティで生まれた。父親はメキシコ外交官だった。[2][6] 父親の転勤に伴い、フエンテスは幼少期をラテンアメリカのさまざまな首都で過ごした。[3] この経験は、後にラテンアメリカを批判的な部外者の視点で見ることができるようになったと彼は述べている。[7] 1934年から1940年まで、フエンテスの父はメキシコ大使館に赴任し、ワシントンD.C.に駐在した。[8] カルロスは英語学校に通い、最終的に流暢に話すようになった。[3][8] この時期に執筆活動を始め、自身の雑誌を制作し、近所のアパートの住人と共有した。[3] 1938年、メキシコは外国の石油資産を国有化し、これは米国で国民的な抗議運動を引き起こした。彼は後に、この出来事を、自分がメキシコ人としてのアイ デンティティを認識し始めた瞬間だと指摘している[8]。1940年、フエンテス一家はチリのサンティアゴに転居した。そこで、彼は、パブロ・ネルーダの 詩に興味を持ったこともあって、生涯の情熱のひとつとなる社会主義に初めて興味を持った。[9] 16歳のとき、外交官を志してメキシコシティのメキシコ国立自治大学(UNAM)で法学を勉強するために、初めてメキシコに住んだ。[3] この間、日刊紙「Hoy」で働き始め、短編小説も書き始めた。[3] その後、ジュネーブ国際問題研究所(Graduate Institute of International Studies)に通った。[10] 1957年、フエンテスは外務省文化関係部長に任命された[8]。翌年、彼は『Where the Air Is Clear』を出版し、一躍「国民的有名人」となり[8]、外交官の職を辞して作家に専念することになった[2]。1959年、キューバ革命を受けてハバ ナに移住し、カストロ支持の記事やエッセイを執筆した。[8] 同年、メキシコ人女優リタ・マセドと結婚した。[3] 「端正な美貌」と評されたフエンテスは、女優ジャンヌ・モローとジャン・セバーグとの高名な恋愛関係も持ち、その経験は小説『ディアナ:孤独な狩りの女 神』の着想源となった。[8] 2度目の結婚はジャーナリストのシルビア・レムスとのもので、彼の死まで続いた。[11] フエンテスは、1975年から1977年までメキシコ駐フランス大使を務めたが、グスタボ・ディアス・オルダス前大統領がスペイン大使に任命されたことに 抗議して辞任した。[2] また、ケンブリッジ、ブラウン、プリンストン、ハーバード、コロンビア、ペンシルベニア、ダートマス、コーネルの各大学で教鞭をとった。[11][12] 彼の友人には、ルイス・ブニュエル、ウィリアム・スタイロン、フリードリヒ・デュレンマット[8]、社会学者 C. ライト・ミルズなどがおり、彼は『アルテミオ・クルスの死』をミルズに捧げた。[13] かつてはノーベル賞受賞のメキシコ人詩人オクタヴィオ・パスと親しい友人だったフエンテスは、1980年代、フエンテスが支持していたサンディニスタにつ いて意見が分かれたことで、パスと疎遠になった。[2] 1988年、パスの雑誌『ヴエルタ』にエンリケ・クラウゼによるフエンテスのメキシコ人としてのアイデンティティの正当性を攻撃する記事が掲載され、パス の死まで続く対立が勃発した。[8] 1989年には、PBS テレビのドキュメンタリー番組「Crossing Borders: The Journey of Carlos Fuentes」が、ヨーロッパでも放送され、メキシコでも繰り返し放送された。 フエンテスは 3 人の子供を持ち、1962年に生まれたセシリア・フエンテス・マセドだけが彼より長生きした。[2] 息子カルロス・フエンテス・レムスは、1999年に血友病の合併症で25歳で死去した。娘ナターシャ・フエンテス・レムス(1974年8月31日生まれ) は、2005年8月22日にメキシコシティで薬物の過剰摂取による死亡が確認され、30歳で死去した。[15] |
| Writing Carlos Fuentes has been called "the Balzac of Mexico". Fuentes himself cited Miguel de Cervantes, William Faulkner and Balzac as the most important writers to him.[16] He also named Latin American writers such as Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti, Miguel Angel Asturias and Jorge Luis Borges. European modernists James Joyce, Virginia Woolf and Marcel Proust have also been cited as important influences on his writing, with Fuentes applying the influence from them on his main theme; Mexican history and identity.[16] Fuentes described himself as a pre-modern writer, using only pens, ink and paper. He asked, "Do words need anything else?" Fuentes said that he detested those authors who from the beginning claim to have a recipe for success. In a speech on his writing process, he related that when he began the writing process, he began by asking, "Who am I writing for?"[17] Early works Fuentes' first novel, Where the Air Is Clear (La región más transparente), was an immediate success on its publication in 1958.[2] The novel is built around the story of Federico Robles – who has abandoned his revolutionary ideals to become a powerful financier – but also offers "a kaleidoscopic presentation" of vignettes of Mexico City, making it as much a "biography of the city" as of an individual man.[18] The novel was celebrated not only for its prose, which made heavy use of interior monologue and explorations of the subconscious,[2] but also for its "stark portrait of inequality and moral corruption in modern Mexico".[19] A year later, he followed with another novel, The Good Conscience (Las Buenas Conciencias), which depicted the privileged middle classes of a medium-sized town, probably modeled on Guanajuato. Described by a contemporary reviewer as "the classic Marxist novel", it tells the story of a privileged young man whose impulses toward social equality are suffocated by his family's materialism.[20] Latin American boom Fuentes was regarded as a leading figure of the Latin American boom in the 1960s and 1970s along with Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa and Julio Cortázar.[16] Fuentes' novel, The Death of Artemio Cruz (La muerte de Artemio Cruz) appeared in 1962 and is "widely regarded as a seminal work of modern Spanish American literature".[9] Like many of his works, the novel used rotating narrators, a technique critic Karen Hardy described as demonstrating "the complexities of a human or national personality".[8] The novel is heavily influenced by Orson Welles' Citizen Kane, and attempts literary parallels to Welles' techniques, including close-up, cross-cutting, deep focus, and flashback.[9] Like Kane, the novel begins with the titular protagonist on his deathbed; the story of Cruz's life is then filled in by flashbacks as the novel moves between past and present. Cruz is a former soldier of the Mexican Revolution who has become wealthy and powerful through "violence, blackmail, bribery, and brutal exploitation of the workers".[21] The novel explores the corrupting effects of power and criticizes the distortion of the revolutionaries' original aims through "class domination, Americanization, financial corruption, and failure of land reform".[22] A prolific writer, Fuentes subsequent work in the 1960s include the novel Aura (1962), the short story collection Cantar de Ciego (1966), the novella Zona Sagrada (1967) and A Change of Skin (1967), an ambitious novel that attempts to define a collective Mexican consciousness by exploring and reinterpreting the country's myths.[23] Fuentes' 1975 Terra Nostra, perhaps his most ambitious novel, is described as a "massive, Byzantine work" that tells the story of all Hispanic civilization.[9] Terra Nostra shifts unpredictably between the sixteenth century and the twentieth, seeking the roots of contemporary Latin American society in the struggle between the conquistadors and indigenous Americans. Like Artemio Cruz, the novel also draws heavily on cinematic techniques.[9] The novel won the Xavier Villaurrutia Award in 1976[24] and the Venezuelan Rómulo Gallegos Prize in 1977.[25] It was followed by La Cabeza de la hidra (1978, The Hydra Head), a spy thriller set in contemporary Mexico and Una familia lejana (1980, Distant Relations), a novel that explores many themes including the relations between the Old world and the New.[26][27] |
執筆 カルロス・フエンテスは「メキシコのバルザック」と呼ばれている。フエンテス自身は、ミゲル・デ・セルバンテス、ウィリアム・フォークナー、バルザックを 自分にとって最も重要な作家として挙げている[16]。また、アレホ・カルペンティール、フアン・カルロス・オネッティ、ミゲル・アンヘル・アストゥリア ス、ホルヘ・ルイス・ボルヘスなどのラテンアメリカ作家も挙げている。ヨーロッパのモダニストであるジェームズ・ジョイス、ヴァージニア・ウルフ、マルセ ル・プルーストも、彼の作品に重要な影響を与えた人物として挙げられており、フエンテスは、彼らの影響を受けて、彼の主なテーマであるメキシコの歴史とア イデンティティを作品に表現している。[16] フエンテスは、自分自身を、ペン、インク、紙だけを使う前近代的な作家だと表現している。彼は、「言葉には、それ以上のものは必要か?」と問いかけた。フ エンテスは、最初から成功の秘訣を主張する作家たちを嫌悪していると述べている。彼の執筆プロセスに関する講演で、彼は執筆を始める際に「私は誰のために 書いているのか」と自問から始める、と語っている。[17] 初期作品 フエンテスの最初の小説『澄んだ空気の地域』(La región más transparente)は、1958年の出版直後から大成功を収めた。[2] この小説は、革命の理想を捨てて強力な金融家となったフェデリコ・ロブレスの物語を中心に展開するが、メキシコシティの断片的な描写を「万華鏡のような表 現」で描き、個人だけでなく「都市の伝記」としても機能している。[18] この小説は、内面の独白や潜在意識の探求を多用した散文[2]だけでなく、「現代メキシコの不平等と道徳的腐敗の厳しい描写」でも高い評価を受けた。 [19] 1年後、彼は別の小説『良心(Las Buenas Conciencias)』を発表。これは、おそらくグアナフアトをモデルにした中規模の町の特権的な中産階級を描いた作品だ。同時代の批評家から「古典 的なマルクス主義小説」と評されたこの作品は、社会的な平等を求める衝動が、家族の物質主義によって抑圧される特権的な青年の物語だ。[20] ラテンアメリカ・ブーム フエンテスは、ガブリエル・ガルシア・マルケス、マリオ・バルガス・リョサ、フリオ・コルタサルとともに、1960年代から1970年代にかけてのラテンアメリカ・ブームの代表的人物とみなされていた。[16] フエンテスの小説『アルテミオ・クルスの死』(La muerte de Artemio Cruz)は 1962 年に出版され、「現代スペイン語アメリカ文学の画期的な作品」と広く評価されている。[9] 彼の多くの作品と同様、この小説も複数の語り手を交代させる手法を採用しており、批評家のカレン・ハーディは、この手法を「人間や国家の複雑な性格」を表 現したものだと評している。[8] この小説は、オーソン・ウェルズの『市民ケーン』の影響を強く受けており、クローズアップ、クロスカット、ディープフォーカス、フラッシュバックなど、 ウェルズの技法と文学的な類似性を試みています。[9] ケーンと同様に、この小説は、死の床にある主人公から始まります。その後、小説は過去と現在を行き来しながら、クルスの人生がフラッシュバックで描かれて いきます。クルスは、メキシコ革命の元兵士で、「暴力、恐喝、贈収賄、そして労働者の残酷な搾取」によって富と権力を手に入れた人物だ。[21] この小説は、権力の腐敗の影響を探求し、「階級支配、アメリカ化、金融腐敗、土地改革の失敗」によって革命家の当初の目標が歪められたことを批判してい る。[22] 多作な作家であるフエンテスの1960年代の主な作品には、小説『アウラ』(1962年)、短編小説集『カンタール・デ・シエゴ』(1966年)、中編小 説『ゾナ・サグラダ』(1967年)、そしてメキシコの神話を再解釈することで集団的なメキシコ意識を定義しようとする野心的な小説『ア・チェンジ・オ ブ・スキン』(1967年)がある。[23] フエンテスの1975年の『テラ・ノストラ』は、おそらく彼の最も野心的な小説であり、ヒスパニック文明全体の物語を描いた「大規模でビザンチン的な作 品」と評されている。[9] 『テラ・ノストラ』は、16世紀と20世紀の間を予測不可能な形で行き来し、征服者と先住民アメリカ人の闘争の中に、現代ラテンアメリカ社会のルーツを探 求している。アルテミオ・クルスと同様に、この小説も映画的手法を多用している。[9] この小説は、1976年にザビエル・ヴィラウルティア賞[24]、1977年にベネズエラのロムロ・ガリエーゴス賞を受賞した。[25] その後、現代メキシコを舞台にしたスパイスリラー『La Cabeza de la hidra』(1978年、英題『The Hydra Head』)や、旧世界と新世界の関係など多くのテーマを探求した小説『Una familia lejana』(1980年、英題『Distant Relations』)を発表した。[26][27] |
| Later works His 1985 novel The Old Gringo (Gringo viejo), loosely based on American author Ambrose Bierce's disappearance during the Mexican Revolution,[11] became the first U.S. bestseller written by a Mexican author.[5] The novel tells the story of Harriet Winslow, a young American woman who travels to Mexico, and finds herself in the company of an aging American journalist (called only "the old gringo") and Tomás Arroyo, a revolutionary general. Like many of Fuentes' works, it explores the way in which revolutionary ideals become corrupted, as Arroyo chooses to pursue the deed to an estate where he once worked as a servant rather than follow the goals of the revolution.[28] In 1989, the novel was adapted into the U.S. film Old Gringo starring Gregory Peck, Jane Fonda, and Jimmy Smits.[5] A long profile of Fuentes in the U.S. magazine, "Mother Jones," describes the filming of "The Old Gringo" in Mexico with Fuentes on the set.[29] In the mid-1980s Fuentes began to conceptualize his total fiction, past and future, in fourteen cycles called "La Edad del Tiempo", explaining that his total work is a lengthy reflection on time. The plan for the cycle first appeared as a page in the Spanish edition of his satirical novel Christopher Unborn in 1987, and as a page in his subsequent books with minor revisions to the original plan.[30][31] In 1992 he published The Buried Mirror: Reflections on Spain and the New World, an historical essay that attempts to cover the entire cultural history of Spain and Latin America. The book was a complement to a Discovery Channel and BBC television series by the same name.[32] Fuentes work of nonfiction also include La nueva novela hispanoamericana (1969; “The New Hispano-American Novel”), which is his chief work of literary criticism, and Cervantes; o, la critica de la lectura (1976; “Cervantes; or, The Critique of Reading”), an homage to the Spanish writer Miguel de Cervantes.[23] His 1994 book Diana: The Goddess Who Hunts Alone is an autobiograpichal novel that portrays the actress Jean Seberg who Fuentes had a love affair with in the 1960s.[16] It was followed by The Crystal Frontier, a novel in nine stories. In 1999 Fuentes published the novel The Years With Laura Diaz. A companion book to The Death of Artemio Cruz, the characters are from the same period, but the story is told by a woman exiled from her province after the revolution. The novel includes some of Fuentes own family history in Veracruz and has been called "a vast, panoramic novel" dealing with "questions of progress, revolution and modernity" and "the ordinary life of the individual that struggles to find its place".[33][34] His later novels include Inez (2001), The Eagle's Throne (2002) and Destiny and Desire (2008). His writing also include several collections of stories, essays and plays.[23] Fuentes' works have been translated into 24 languages.[5] He remained prolific to the end of his life, with an essay on the new government of France appearing in Reforma newspaper on the day of his death.[35] Mexican historian Enrique Krauze was a vigorous critic of Fuentes and his fiction, dubbing him a "guerrilla dandy" in a 1988 article for the perceived gap between his Marxist politics and his personal lifestyle.[36] Krauze accused Fuentes of selling out to the PRI government and being "out of touch with Mexico", exaggerating its people to appeal to foreign audiences: "There is the suspicion in Mexico that Fuentes merely uses Mexico as a theme, distorting it for a North American public, claiming credentials that he does not have."[6][37] The essay, published in Octavio Paz's magazine Vuelta, began a feud between Paz and Fuentes that lasted until Paz's death.[8] Following Fuentes' death, however, Krauze described him to reporters as "one of the most brilliant writers of the 20th Century".[38] |
後の作品 1985年の小説『The Old Gringo (Gringo viejo)』は、メキシコ革命中に失踪したアメリカの作家アンブローズ・ビアスの生涯をモデルにしており[11]、メキシコ人作家による初のアメリカで のベストセラーとなった。[5] この小説は、メキシコへ旅立った若いアメリカ人女性ハリエット・ウィンズロウが、老いたアメリカ人ジャーナリスト(単に「オールド・グリンゴ」と呼ばれ る)と革命軍将校トマス・アロヨと共に過ごす物語だ。フエンテスの多くの作品同様、この小説も革命の理想が腐敗していく過程を描いており、アロヨは革命の 目標を追う代わりに、かつて使用人として働いていた別荘の所有権を追求する道を選ぶ。[28] 1989年、この小説はグレゴリー・ペック、ジェーン・フォンダ、ジミー・スミス主演でアメリカ映画『オールド・グリンゴ』として映画化されました。 [5] アメリカの雑誌『マザー・ジョーンズ』に掲載されたフエンテスの長編プロフィールでは、メキシコでの『ザ・オールド・グリンゴ』の撮影現場にフエンテスが 立ち会った様子が描かれている。[29] 1980年代半ば、フエンテスは過去と未来を網羅する総括的なフィクションを14のサイクル「ラ・エダド・デル・ティエンポ」として構想し始めた。彼は自 身の総括的な作品は時間に関する長大な考察だと説明している。このサイクルの計画は、1987年にスペイン語版で出版された風刺小説『クリストファー・ア ンボーン』の一ページとして初めて登場し、その後の著作にも元の計画を若干修正した形で掲載された。[30][31] 1992年には、スペインとラテンアメリカの文化史全体を網羅した歴史エッセイ『The Buried Mirror: Reflections on Spain and the New World』を出版した。この本は、ディスカバリーチャンネルとBBCの同名のテレビシリーズを補完する作品だった。[32] フエンテスのノンフィクション作品には、文学批評の代表作『ラ・ヌエバ・ノベラ・イスパノアメリカーナ』(1969年;「新しいヒスパノアメリカ小説」) と、スペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスへのオマージュ『セルバンテス;または、読書の批判』(1976年;「セルバンテス;または、読書の批判」) がある。[23] 1994年の『ダイアナ:孤独の女神』は、フエンテスが1960年代に恋愛関係にあった女優ジャン・セバーグを描いた自伝的小説だ。[16] その後、9つの物語で構成される小説『クリスタル・フロンティア』が発表された。 1999年、フエンテスは小説『ローラ・ディアスとの年』を発表した。アルテミオ・クルスの死』の続編で、登場人物は同じ時代の人物だが、物語は革命後に 故郷を追われた女性が語る。この小説には、フエンテスのベラクルスでの家族の歴史も一部盛り込まれており、「進歩、革命、現代性」や「自分の居場所を探す ために奮闘する個人の平凡な生活」を題材にした「広大でパノラマ的な小説」と評されている。[34] 彼の後の小説には、『イネス』(2001年)、『鷲の王座』(2002年)、『運命と欲望』(2008年)などがある。また、短編小説、エッセイ、戯曲などの作品も数多くある。[23] フエンテスの作品は24カ国語に翻訳されている。[5] 彼は生涯、多作で、亡くなった日に、フランスの新政権に関するエッセイがレフォルマ紙に掲載された。[35] メキシコの歴史家エンリケ・クラウゼは、フエンテスとその小説を激しく批判し、1988年の記事で、彼のマルクス主義の政治観と個人的なライフスタイルと のギャップを指摘し、彼を「ゲリラのダンディ」と揶揄した。[36] クラウゼは、フエンテスが PRI 政府に売ったと非難し、外国の読者にアピールするためにメキシコの人々を誇張して描いていると批判した。「メキシコでは、フエンテスはメキシコを題材とし てのみ利用し、北米の人々に迎合するためにメキシコを歪曲し、自分にはない資格を主張しているとの疑惑がある」と述べた。[6][37] このエッセイはオクタビオ・パスの雑誌『ヴエルタ』に掲載され、パズとフエンテスの間の対立が始まり、パズの死まで続いた。[8] しかし、フエンテスの死後、クラウゼは記者団に対し、彼を「20世紀で最も brilliant な作家の一人」と形容した。[38] |
| Political views The Los Angeles Times described Fuentes' politics as "moderate liberal", noting that he criticized "the excesses of both the left and the right".[6] Fuentes was a long-standing critic of the Institutional Revolutionary Party (PRI) government that ruled Mexico between 1929 and the election of Vicente Fox in 2000, and later of Mexico's inability to reduce drug violence. He has expressed his sympathies with the Zapatista rebels in Chiapas.[2] Fuentes was also critical of U.S. foreign policy, including Ronald Reagan's opposition to the Sandinistas,[8] George W. Bush's anti-terrorism tactics,[2] U.S. immigration policy,[5] and the role of the U.S. in the Mexican Drug War.[6] His politics caused him to be blocked from entering the United States until a Congressional intervention in 1967.[2] Once, after being denied permission to travel to a 1963 New York City book release party, he responded "The real bombs are my books, not me".[2] Much later in his life, he commented that "The United States is very good at understanding itself, and very bad at understanding others."[3] The U.S. State Department and the Federal Bureau of Investigation closely monitored Fuentes during the 1960s, purposefully delaying — and often denying — the author's visa applications.[39] Fuentes' FBI file, released on June 20, 2013, reveals that the FBI's upper echelons were interested in Fuentes’ movements, because of the writer's suspected communist-leanings and criticism of the Vietnam War. Long-time FBI Associate Director Clyde Tolson was copied on several updates about Fuentes.[39] Initially a supporter of Fidel Castro's Cuban Revolution, Fuentes turned against Castro after being branded a "traitor" to Cuba in 1965 for attending a New York conference[8] and the 1971 imprisonment of poet Heberto Padilla by the Cuban government.[3] The Guardian described him as accomplishing "the rare feat for a leftwing Latin American intellectual of adopting a critical attitude towards Fidel Castro's Cuba without being dismissed as a pawn of Washington."[3] Fuentes also criticized Venezuelan President Hugo Chávez, dubbing him "a tropical Mussolini."[2] Fuentes' last message on Twitter read, "There must be something beyond slaughter and barbarism to support the existence of mankind and we must all help search for it."[40] |
政治的見解 ロサンゼルス・タイムズ紙は、フエンテスの政治姿勢を「穏健なリベラル」と表現し、彼が「左派と右派の双方の行き過ぎ」を批判していると指摘している [6]。フエンテスは、1929年から2000年にビセンテ・フォックスが当選するまでメキシコを統治した制度革命党(PRI)政権、そして後にメキシコ が麻薬による暴力を削減できないことを長年にわたり批判してきた。彼はチアパス州のサパティスタ反乱軍への同情を表明している。[2] フエンテスはまた、ロナルド・レーガン大統領のサンディニスタ政権への反対[8]、ジョージ・W・ブッシュ大統領のテロ対策[2]、米国の移民政策 [5]、およびメキシコ麻薬戦争における米国の役割[6]など、米国の外交政策を批判した。彼の政治的立場により、1967年に議会の介入があるまでアメ リカ合衆国への入国が禁止されていた。[2] 1963年にニューヨーク市での書籍発売パーティーへの参加を拒否された際、彼は「本当の爆弾は私ではなく、私の本だ」と応じた。[2] 晩年、彼は「アメリカ合衆国は自分自身を理解することは非常に得意だが、他者を理解することは非常に苦手だ」とコメントしている。[3] アメリカ国務省と連邦捜査局(FBI)は、1960年代にフエンテスを厳重に監視し、意図的にビザ申請を遅らせたり、拒否したりした。[39] 2013年6月20日に公開されたフエンテスのFBIファイルによると、FBIの上層部は、作家の共産主義傾向とベトナム戦争批判を理由に、フエンテスの 動向に関心を示していた。FBIの長期にわたる副長官クライド・トールソンは、フエンテスに関する複数の報告書のコピーを受け取っていた。[39] 当初、フィデル・カストロのキューバ革命を支持していたフエンテスは、1965年にニューヨークで開催された会議に出席したこと[8]、および1971年 に詩人ヘベルト・パディージャがキューバ政府によって投獄されたことを受け、キューバの「裏切り者」と烙印を押され、カストロに背を向けた。[3] ガーディアン紙は、フエンテスを「フィデル・カストロのキューバに対して批判的な態度を取りながら、ワシントンの手先として一蹴されることなく、ラテンア メリカの左翼知識人としては珍しい偉業を成し遂げた人物」と評している。[3] フエンテスは、ベネズエラのウーゴ・チャベス大統領も「熱帯のムッソリーニ」と批判した。[2] フエンテスのツイッターでの最後のメッセージは、「人類の存在を支えるものは、虐殺と野蛮さを超えた何かがあるはずで、私たちは皆、それを探し求める手助けをしなければならない」[40] だった。 |
| Death On May 15, 2012, Fuentes died in Angeles del Pedregal hospital in southern Mexico City from a massive hemorrhage.[11][41] He had been brought there after his doctor had found him collapsed in his Mexico City home.[11] Mexican President Felipe Calderón wrote on Twitter, "I am profoundly sorry for the death of our loved and admired Carlos Fuentes, writer and universal Mexican. Rest in peace."[7] Nobel laureate Mario Vargas Llosa stated, "with him, we lose a writer whose work and whose presence left a deep imprint".[7] French President François Hollande called Fuentes "a great friend of our country" and stated that Fuentes had "defended with ardour a simple and dignified idea of humanity".[42] Salman Rushdie tweeted "RIP Carlos my friend".[42] Fuentes received a state funeral on May 16, with his funeral cortege briefly stopping traffic in Mexico City. The ceremony was held in the Palacio de Bellas Artes and was attended by President Calderón.[42] |
死 2012年5月15日、フエンテスはメキシコシティ南部のアンヘレス・デル・ペドレガル病院で大量出血により死去した。[11][41] 彼は、メキシコシティの自宅で倒れているところを発見され、医師によって同病院に搬送されていた。[11] メキシコ大統領フェリペ・カルデロンはツイッターで、「愛され、尊敬されていた作家であり、世界的なメキシコ人であるカルロス・フエンテスの死を深く悼 む。安らかに眠ってくれ」と述べた。[7] ノーベル賞受賞者のマリオ・バルガス・リョサは、「彼と共に、その作品と存在が深い足跡を残した作家を失った」と述べた。[7] フランスのフランソワ・オランド大統領はフエンテスを「我が国の偉大な友人」と呼び、フエンテスが「単純で尊厳ある人間性の理念を熱烈に擁護した」と述べ た。[42] サルマン・ラシュディはツイッターで「安らかに眠れ、私の友人カルロス」と投稿した。[42] フエンテスは5月16日に国葬が行われ、メキシコシティでは彼の葬列が交通を一時的に遮断した。式典はパラシオ・デ・ベラス・アルテスで開催され、カルデロン大統領も出席した。[42] |
| List of works Novels La región más transparente (Where the Air Is Clear) (1958) ISBN 978-970-58-0014-6 Las buenas conciencias (The Good Conscience) (1961) ISBN 978-970-710-004-6 Aura (1962) ISBN 978-968-411-181-3 La muerte de Artemio Cruz (The Death of Artemio Cruz) (1962) ISBN 978-0-374-52283-4 Cambio de piel (A Change of Skin) (1967) Zona sagrada (Holy Place) (1967) Cumpleaños (Birthday) (1969) Terra Nostra (1975)[43] La cabeza de la hidra (The Hydra Head) (1978) Una familia lejana (Distant Relations) (1980) Gringo viejo (The Old Gringo) (1985) Cristóbal Nonato (Christopher Unborn) (1987) Ceremonias del alba (1991) La campaña (The Campaign) (1992) Diana o la cazadora solitaria (Diana: the Goddess Who Hunts Alone) (1995) La frontera de cristal (The Crystal Frontier: A Novel of Nine Stories) (1996) Los años con Laura Díaz (The Years With Laura Diaz) (1999) Instinto de Inez (Inez) (2001) La silla del águila (The Eagle's Throne) (2002) Todas las familias felices (Happy Families) (2006), ISBN 987-04-0557-6 La voluntad y la fortuna (Destiny and Desire) (2008), ISBN 978-1400068807 Adán en Edén (2009) Vlad (2010) Federico en su Balcón (2012) (posthumous) Aquiles o el guerrillero y el asesino (2016) (posthumous) Short stories Los días enmascarados (1954) Cantar de ciegos (1964) Chac Mool y otros cuentos (1973) Agua quemada (Burnt Water) (1983) ISBN 968-16-1577-8 Constancia and other Stories For Virgins (1990) Dos educaciones (1991) ISBN 84-397-1728-8 El naranjo (The Orange Tree) (1994) Inquieta compañía (2004) Happy Families (2008) Las dos Elenas (1964) El hijo de Andrés Aparicio Essays La nueva novela hispanoamericana (1969) ISBN 968-27-0142-2 El mundo de José Luis Cuevas (1969) Casa con dos puertas (1970) Tiempo mexicano (1971) Miguel de Cervantes o la crítica de la lectura (1976) Myself With Others (1988) El Espejo Enterrado (The Buried Mirror: Reflections on Spain and the New World) (1992) ISBN 84-306-0265-8 Geografía de la novela (1993) ISBN 968-16-4044-6 Tres discursos para dos aldeas ISBN 950-557-195-X Nuevo tiempo mexicano (A New Time for Mexico) (1995) ISBN 968-19-0231-9 Retratos en el tiempo, with Carlos Fuentes Lemus (2000) Los cinco soles de México: memoria de un milenio (2000) ISBN 84-322-1063-3 En esto creo (2002) ISBN 970-58-0087-1 Contra Bush (2004) ISBN 968-19-1450-3 Los 68 (2005) ISBN 0307274152 Personas (2012) ISBN 0307274152 Theater Todos los gatos son pardos (1970) El tuerto es rey (1970). Los reinos originarios: teatro hispano-mexicano (1971) Orquídeas a la luz de la luna. Comedia mexicana. (1982) Ceremonias del alba (1990) Screenplays ¿No oyes ladrar los perros? (1974) Pedro Páramo (1967) Los caifanes (1966) Un alma pura (1965) (episode from Los bienamados) Tiempo de morir (1965) (written in collaboration with Gabriel García Márquez) Las dos Elenas (1964) El gallo de oro (1964) (written in collaboration with Gabriel García Márquez and Roberto Gavaldón, from a short story by Juan Rulfo) |
作品一覧 小説 La región más transparente (Where the Air Is Clear) (1958) ISBN 978-970-58-0014-6 Las buenas conciencias (The Good Conscience) (1961) ISBN 978-970-710-004-6 オーラ (1962) ISBN 978-968-411-181-3 アルテミオ・クルスの死 (1962) ISBN 978-0-374-52283-4 『皮の交換』(1967年) 『聖域』(1967年) 『誕生日』(1969年) 『テラ・ノストラ』(1975年)[43] 『ヒドラの頭』(1978年) 遠い親戚(Distant Relations)(1980年 古いグリント(The Old Gringo)(1985年 クリストバル・ノナト(Christopher Unborn)(1987年 夜明けの儀式(Ceremonias del alba)(1991年 キャンペーン(The Campaign)(1992年 ディアナ、孤独な狩人(Diana: the Goddess Who Hunts Alone)(1995年) クリスタル・フロンティア(The Crystal Frontier: A Novel of Nine Stories)(1996年) ローラ・ディアスとの年月(The Years With Laura Diaz)(1999年) イネスの本能(Inez)(2001年) 『鷲の玉座』(2002年) 『幸せな家族たち』(2006年)、ISBN 987-04-0557-6 『運命と欲望』(2008年)、ISBN 978-1400068807 アダン・エン・エデン(2009年 ヴラド(2010年 フェデリコ・エン・ス・バルコン(2012年)(死後出版 アキレス、あるいはゲリラと殺人者(2016年)(死後出版 短編 仮面の時代(1954年 カンタル・デ・シエゴス (1964) チャック・ムールとその他の短編 (1973) Agua quemada (Burnt Water) (1983) ISBN 968-16-1577-8 Constancia and other Stories For Virgins (1990) Dos educaciones (1991) ISBN 84-397-1728-8 El naranjo (オレンジの木) (1994) Inquieta compañía (2004) Happy Families (2008) Las dos Elenas (1964) El hijo de Andrés Aparicio エッセイ La nueva novela hispanoamericana (1969) ISBN 968-27-0142-2 El mundo de José Luis Cuevas (1969) Casa con dos puertas (1970) Tiempo mexicano (1971) Miguel de Cervantes o la crítica de la lectura (1976) Myself With Others (1988) El Espejo Enterrado (The Buried Mirror: Reflections on Spain and the New World) (1992) ISBN 84-306-0265-8 Geografía de la novela (1993) ISBN 968-16-4044-6 Tres discursos para dos aldeas ISBN 950-557-195-X メキシコの新しい時代(1995年) ISBN 968-19-0231-9 時間の中の肖像、カルロス・フエンテス・レムスと共著(2000年) メキシコの五つの太陽:千年の記憶(2000年) ISBN 84-322-1063-3 私はこれ信じる (2002) ISBN 970-58-0087-1 ブッシュに反対 (2004) ISBN 968-19-1450-3 『68年』(2005年) ISBN 0307274152 『人物たち』(2012年) ISBN 0307274152 演劇 『すべての猫は茶色だ』(1970年 『片目の王様』(1970年 『原初の王国:ヒスパニック・メキシコ演劇』(1971年 月明かりのオーキデア。メキシコ喜劇。(1982) 夜明けの儀式 (1990) 脚本 犬が吠えるのが聞こえないか? (1974) ペドロ・パラモ (1967) ロス・カイファネス (1966) 『純粋な魂』(1965年)(『愛される者たち』からのエピソード) 『死ぬ時』(1965年)(ガブリエル・ガルシア・マルケスとの共作) 『二つのエレナ』(1964年) 『黄金の雄鶏』(1964年)(ガブリエル・ガルシア・マルケス、ロベルト・ガバルドンとの共作、フアン・ルルフォの短編小説を原作) |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fuentes |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆