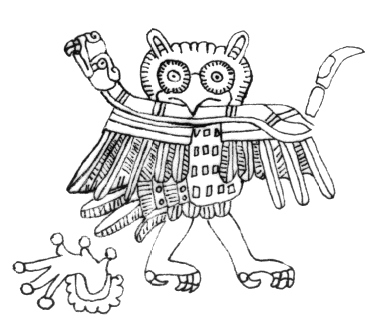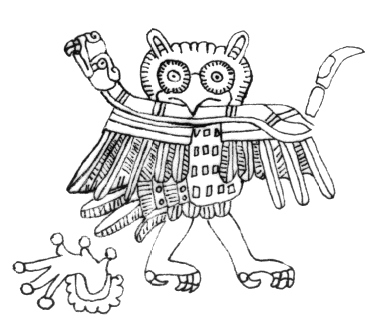池田光穂
多文化主義は、人間における文化のあり方を複数でと
らえることを前提に、複数の文化が共存する状態を「善し」とする見解や実践の原理のことをさす。マルチカルチャリズム
(multiculturalism)とも呼ぶ。以下では、アンドレア・センプリーニ『多文化主義と
は何か』(三浦信孝・長谷川秀樹訳、白水社、2003年)をテキストに、多文化主義について講義する形式をとる。
センプリーニは、この書の目的を3つ掲げる
- 1.ヨーロッパでは問題化されていない面もあるために、米国の展開を論述し、かつ政治経済的な関係を明らかにする。
- 2.多文化主義論争において、複雑かつ矛盾した理論的問題が露呈したことを記述する。
- 3.多文化主義の諸相は、ポスト工業化社会にみられる現在進行中の変化の一環のひとつである。
この書の章立ては以下のとおりである。
- 序
- 1.多文化主義の歴史的起源と現在の枠組み
- 2.多文化主義論争
- 3.ポリティカリー・コレクト
- 4.認識論上の難問(=ゴルディオスの結び目)
- 5.エスニシティ・個人主義・公共空間
- 6.公共空間と多文化的空間
- 7.多文化主義と近代性の危機
以下、詳述する。
- 序
- 1.多文化主義の歴史的起源と現在の枠組み
- インディアン問題
- 奴隷制と人種隔離政策
- 宗教移民
- アングロサクソンの母型
- 押し寄せる移民と人口構成の変動
- アメリカ社会の拡大
- 経済変動
- アイデンティティと政治
- 「避けられない」葛藤
- 2.多文化主義論争
- 差異の政治的読解と文化主義的読解
- 教育問題
- 「男女間戦争」
- アイデンティティの要求
- 3.ポリティカリー・コレクト
- ある表現の不運
- PCと言語理論
- 新しい完全言語
- 適当な距離の模索
- 4.認識論上の難問(=ゴルディオスの結び目)
- 5.エスニシティ・個人主義・公共空間
- 諸個人からなる社会へ?
- 対話的自我と承認
- 個人主義から主観性へ
- 社会文化空間へ
- 記号論的領域としての社会文化空間
- 6.公共空間と多文化的空間
- 多文化主義の政治的係争
- 多文化主義の4モデル(古典的自由主義政治モデル/多文化的自由主義モデル/「マキシマリスト(最大限要求型)多文化主義モデル/
コーポレイト多文化主義モデル)
- 多文化公共空間は可能か?
- フランスの事例
- 7.多文化主義と近代性の危機
- 差異とアイデンティティ
- 政治的パラダイムから倫理的パラダイムへ
- 合理主義と相対主義
- 結論
議論のポイント
- 先住民の文化の《本質性》について語る権利は誰にあるのか?——先住民なのか?研究者なのか?それとも両方か?それとも誰にもないのか?
- 先住民の文化が《社会構築的》であったとしても、先住民に自己の文化について語る権利があるとすれば、それはどのような根拠に由来するの
か?
- 「研究者は、事実に対して客観的で正確でなければならず、先住民運動家は政治的な目標をもちプラグマティストだから、研究者に求められる
ような正確さは不要だ」という議論は、なにが問題があるのか?——この種の二分法がいけないのなら、その代替案を考えよ!
- 先住民の知識人のすべてが《本質主義》に囚われているという(一部)の人類学者のマニ教的な主張はあたらないだろう。他方、すべての人類
学者が古典的な意味での《柔軟な本質主義者》でもないし、またその反対に《頑迷な社会構築主義者》でもないだろう。そのような《戦線の膠着状況》のなかで
対話を続けてゆくことは重要である。理想的な対話理論とは裏腹に、現実の対話の中には、交渉・宥め・要求・妥協・発話的変節などさまざまなものがあり、対
話を続けてゆくことのなかに偶発的な創発効果もあるだろう。
多文化主義に関するガヤトリ・スピヴァックの批判
ポストコロニアル批評家のガヤトリ・スピバック(ないしはスピヴァック:Gayatri
Chakravorty Spivak, 1942- )は、その代表格であろう。彼女は言う「多元論とは、中心的権威が反対意見を受け入れる
かのよう に見せかけて実は骨抜きにするために用いる方法論のことである」と。
「たとえばひとはそうですね、フランスで産み出
されている理論的な事柄の一部は、アフリカや、インドや、こうしたいわゆる自然な場所からきた人々には、自然に手に入ると言われています。もしひとが啓蒙
主義以後の理論の歴史を吟味してみれば、これまでの主要な問題は自伝の問題であったのです。つまり主体的構造が事実、客観的真実を与えることができるので
す。こうした同じ世紀の間、こうした他の場所に見いだされた「土着の情報提供者」の書いたものは、疑いもなく民族誌学、比較言語学、比較宗教学など、いわ
ゆる諸科学の創始のための客観的証拠として扱われました。だから再び、理論的問題は知識のある人にのみ関連してきます。知識のある人は自我にまつわるすべ
ての問題を持っています。世間に知られている人は、どういうわけか問題性のある自我をもっていないように思われます」(スピヴァック,1992:119-
120)『ポスト植民地主義の思想』彩流社。
これは、文化相対主義ならびに多
文化共生社会(=日本語独特の用語)あるいは多
文化主義に対する鋭い批判的論拠になっている。
マルチカルチャリズムが隠蔽する文化の本質主義
ナンシー・フレイザー(2003:280-281)
は、マルチカルチャリズムが潜在的にもつ、差異を本質主義化し、差異をポジティブで、本来「文化的」なものとして見なして称揚することの欺瞞性に対してき
わめて批判的である。これは、アイデンティティの
実体化であり、集団を一枚岩としてみなすことになる。これがなぜ問題かというと、その集団構成員の間の不平等(経済、ジェンダー、発言権、異なるものにな
る可能性や潜在性などの不平等)や、集団内の権力関係とりわけ支配と従属などを無視したり、(知りながらも)やり過ごすことにつながるからである。
グローバル資本主義下における多文化主義へのスラヴォイ・ジジェクによる批判
ポイントは(経済がもつ普遍的価値への包摂を
促進させるかにみえる)グローバルな状況においても、それぞれの文化が固有の価値をもつことを
称揚するが、その文化的差異は、人種主義(あるいは人種差別思想)が持つような、支配者が被支配者の差異があったまま、その差異を固定化させるようなイデ
オロギーとして作用しているのだ、ということである。(詳細はリンク先「ジジェク教授による厄介な多文化主義批判」へ)
リンク集
文献
- Linnekin, Jocelyn S., 1983. Defining tradition: variations on
the Hawaiian identity. American Ethnologist 10(2):241-252. DOI:
10.1525/ae.1983.10.2.02a00020 (-> Abstruct
)
- Trask, Haunani-Kay, 1991.Natives and Anthropologists: The
Colonial Struggle. The Contemporary Pacific, Volume 3, Number 1, Spring
1991, 145–177(この論文はpdfで入手できます)
- Jolly,
Margaret. 1992. Specters of Inauthenticity. The Contemporary
Pacific, Volume 4, Number I, Spring I992, 49-72
- フレイザー、ナンシー『中断された正義:「ポスト社会主義的」条件をめぐる批判的考察』仲正昌樹監訳、お茶の水書房、2003年
文
献