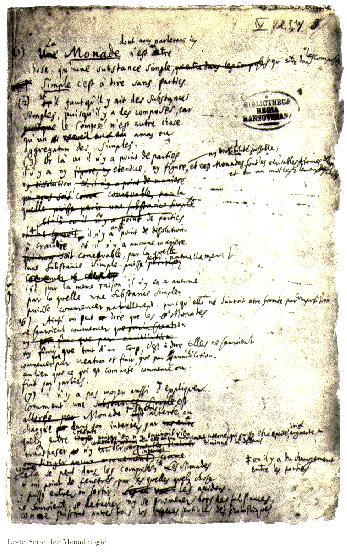
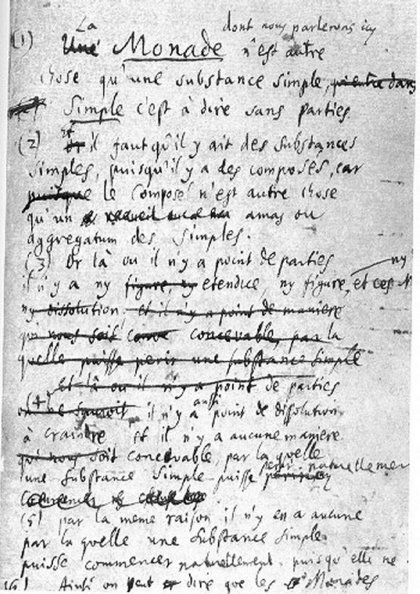
モナド論/モナドロジー
Monadology
☆
『単子論』(フランス語: La Monadologie,
1714年)は、ゴットフリート・ライプニッツの後期哲学における最も有名な著作の一つである。この短いテキストは、約90の段落で、単純な実体、すなわ
ち単子に関する形而上学を提示している。
| The Monadology
(French: La Monadologie, 1714) is one of Gottfried Leibniz's best known
works of his later philosophy. It is a short text which presents, in
some 90 paragraphs, a metaphysics of simple substances, or monads. |
『単子論』(フランス語: La Monadologie,
1714年)は、ゴットフリート・ライプニッツの後期哲学における最も有名な著作の一つである。この短いテキストは、約90の段落で、単純な実体、すなわ
ち単子に関する形而上学を提示している。 |
Text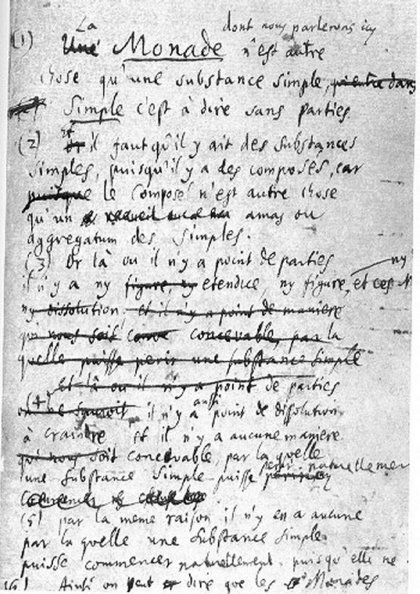 The first manuscript page of the Monadology During his last stay in Vienna from 1712 to September 1714, Leibniz wrote two short texts in French which were meant as concise expositions of his philosophy. After his death, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, which was intended for prince Eugene of Savoy, appeared in French in the Netherlands. Christian Wolff and collaborators published translations in German and Latin of the second text which came to be known as The Monadology. Without having seen the Dutch publication of the Principes they had assumed that it was the French original of the Monadology, which in fact remained unpublished until 1840. The German translation appeared in 1720 as Lehrsätze über die Monadologie and the following year the Acta Eruditorum printed the Latin version as Principia philosophiae.[1] There are three original manuscripts of the text: the first written by Leibniz and glossed with corrections and two further emended copies with some corrections appearing in one but not the other.[2] Leibniz himself inserted references to the paragraphs of his Théodicée ("Theodicy", i.e. a justification of God), sending the interested reader there for more details. |
テキスト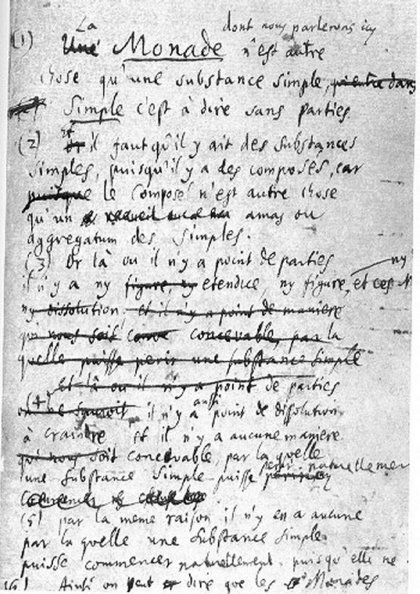 『モナドロジー』の最初の原稿ページ 1712年から1714年9月までのウィーン滞在中、ライプニッツは自身の哲学を簡潔に説明したフランス語の短文を二篇書いた。死後、サヴォイア公ユージ ン宛てに書かれた『理性に基づく自然と恩寵の原理』がオランダでフランス語版として出版された。クリスティアン・ヴォルフらは第二の文章をドイツ語とラテ ン語に翻訳し、これが後に『単子論』として知られるようになった。彼らはオランダ語版の『自然および恩寵の原理』を目にしていなかったため、このフランス 語文書が『単子論』の原典だと誤認した。実際、ドイツ語訳は1840年まで未発表だった。 ドイツ語訳は1720年に『モナドロジーに関する教説』として刊行され、翌年には『アクタ・エルディトールム』誌がラテン語版を『哲学原理』として掲載し た[1]。この著作には三つの原稿が存在する。一つはライプニッツ自筆で修正注釈が加えられ、さらに二つの修正版写本があり、一方にのみ記載された修正点 も存在する。[2] ライプニッツ自身は、自身の『神義論』(すなわち神の存在を正当化する論考)の段落への参照を挿入し、詳細を知りたい読者をそちらへ誘導している。 |
| Metaphysics Context The monad, the word and the idea, belongs to the Western philosophical tradition and has been used by various authors.[3] Leibniz, who was exceptionally well-read, could not have ignored this, but he did not use it himself until mid-1696 when he was sending for print his New System.[4] Apparently he found with it a convenient way to expound his own philosophy as it was elaborated in this period. What he proposed can be seen as a modification of occasionalism developed by latter-day Cartesians. Leibniz surmised that there are indefinitely many substances individually 'programmed' to act in a predetermined way, each substance being coordinated with all the others. This is the pre-established harmony which solved the mind-body problem, but at the cost of declaring any interaction between substances a mere appearance. |
形而上学 背景 モナド、言葉、そして観念は西洋哲学の伝統に属し、様々な著者によって用いられてきた[3]。非常に博識であったライプニッツがこれを無視することはあり えなかったが、彼自身がこの用語を使い始めたのは1696年半ば、彼の『新体系』を印刷に回す際であった[4]。どうやら彼はこの時期に構築された自身の 哲学を説明するのに、この用語が便利な手段であると見出したようだ。彼が提案したものは、後期のデカルト主義者が発展させた機会主義の修正と見なせる。ラ イプニッツは、あらかじめ決められた方法で行動するよう個別に「プログラム」された物質が無限に存在し、各物質が他の全てと調和していると推測した。これ が心身問題を解決した「予め定められた調和」であるが、その代償として物質間の相互作用を単なる見掛け上の現象と宣言することを余儀なくされた。 |
| Summary The rhetorical strategy adopted by Leibniz in The Monadology is fairly obvious as the text begins with a description of monads (proceeding from simple to complicated instances), then it turns to their principle or creator and finishes by using both to explain the world. (I) As far as Leibniz allows just one type of element in the building of the universe his system is monistic. The unique element has been 'given the general name monad or entelechy' and described as 'a simple substance' (§§1, 19). When Leibniz says that monads are 'simple,' he means that "which is one, has no parts and is therefore indivisible".[5] Relying on the Greek etymology of the word entelechie (§18),[6] Leibniz posits quantitative differences in perfection between monads which leads to a hierarchical ordering. The basic order is three-tiered: (1) entelechies or created monads (§48), (2) souls or entelechies with perception and memory (§19), and (3) spirits or rational souls (§82). Whatever is said about the lower ones (entelechies) is valid for the higher (souls and spirits) but not vice versa. As none of them is without a body (§72), there is a corresponding hierarchy of (1) living beings and animals (2), the latter being either (2) non-reasonable or (3) reasonable. The degree of perfection in each case corresponds to cognitive abilities and only spirits or reasonable animals are able to grasp the ideas of both the world and its creator. Some monads have power over others because they can perceive with greater clarity, but primarily, one monad is said to dominate another if it contains the reasons for the actions of other(s). Leibniz believed that any body, such as the body of an animal or man, has one dominant monad which controls the others within it. This dominant monad is often referred to as the soul. |
要約 『モナドロジー』におけるライプニッツの修辞的戦略は極めて明白である。 まずモナドの記述から始まり(単純な事例から複雑な事例へと進む)、 次にその原理あるいは創造者へと移り、 最後に両者を用いて世界を説明する形で終える。 (I) ライプニッツが宇宙構築において単一の要素のみを許容する限り、その体系は一元論的である。この唯一の要素は「一般にモナドまたはエンテレケイアと呼ばれ る」ものであり、「単純な実体」と説明されている(§§1, 19)。ライプニッツがモナドを「単純」と述べる際、それは「一つであり、部分を持たず、したがって分割不能であるもの」を意味する[5]。エンテレケイ アという語のギリシャ語語源(§18)[6]に基づき、ライプニッツはモナド間に完全性の量的差異を仮定し、それが階層的秩序をもたらす。基本秩序は三層 構造である:(1) エンテレケイア、すなわち創造されたモナド(§48)、(2) 知覚と記憶を持つ魂、すなわちエンテレケイア(§19)、(3) 理性を持つ魂、すなわちスピリット(§82)。下位の存在(エンテレケイア)について述べられることは上位の存在(魂とスピリット)にも当てはまるが、逆 は成立しない。いずれのモナドも身体を伴う(§72)ため、これに対応する階層として(1)生物と(2)動物が存在する。後者は(2)非理性的なものと (3)理性的なものに分けられる。各段階の完全性の程度は認知能力に対応し、世界とその創造主の理念を把握できるのは霊、すなわち理性的な動物のみであ る。一部の単子(モノアド)はより明晰に知覚できるため他を支配するが、主に「ある単子が他の単子の行動原理を内包する場合」に支配関係が成立する。ライ プニッツは、動物や人間の身体を含むあらゆる物質には、内部の単子を統制する支配的単子が存在すると考えた。この支配的単子は往々にして「魂」と呼ばれ る。 |
| (II)
God is also said to be a simple substance (§47) but it is the only one
necessary (§§38–9) and without a body attached (§72). Monads perceive
others "with varying degrees of clarity, except for God, who perceives
all monads with utter clarity".[7] God could take any and all
perspectives, knowing of both potentiality and actuality. As well as
that God in all his power would know the universe from each of the
infinite perspectives at the same time, and so his perspectives—his
thoughts—"simply are monads".[8] Creation is a permanent state, thus
"[monads] are generated, so to speak, by continual fulgurations of the
Divinity" (§47).[9] Any perfection comes from being created while
imperfection is a limitation of nature (§42). The monads are unaffected
by each other, but each have a unique way of expressing themselves in
the universe, in accordance with God's infinite will. |
(II)
神はまた単純な実体であると言われる(§47)が、唯一必要な実体であり(§§38–9)、身体を伴わない(§72)。単子(モナド)は他の単子を「様々
な明瞭さで知覚するが、神だけは例外で、全ての単子を完全に明瞭に知覚する」[7]。神はあらゆる視点を取り得る。潜在性と現実性の両方を知り得るのだ。
さらに神はその全知全能をもって、無限の視点のそれぞれから同時に宇宙を知り得る。ゆえに神の視点―すなわち神の思考―は「単子そのもの」なのである。
[8] 創造は恒常的な状態であり、したがって「[単子]は、いわば神性の絶え間ない閃光によって生成される」のである(§47)。[9]
あらゆる完全性は創造されることによって生じるが、不完全性は自然の限界である(§42)。単子は互いに影響を受けないが、神の無限の意志に従い、宇宙に
おいてそれぞれ独自の表現方法を持つ。 |
| (III)
Composite substances or matter are "actually sub-divided without end"
and have the properties of their infinitesimal parts (§65). A notorious
passage (§67) explains that "each portion of matter can be conceived as
like a garden full of plants, or like a pond full of fish. But each
branch of a plant, each organ of an animal, each drop of its bodily
fluids is also a similar garden or a similar pond". There are no
interactions between different monads nor between entelechies and their
bodies but everything is regulated by the pre-established harmony
(§§78–9). Much like how one clock may be in synchronicity with another,
but the first clock is not caused by the second (or vice versa), rather
they are only keeping the same time because the last person to wind
them set them to the same time. So it is with monads; they may seem to
cause each other, but rather they are, in a sense, "wound" by God's
pre-established harmony, and thus appear to be in synchronicity.
Leibniz concludes that "if we could understand the order of the
universe well enough, we would find that it surpasses all the wishes of
the wisest people, and that it is impossible to make it better than it
is—not merely in respect of the whole in general, but also in respect
of ourselves in particular" (§90).[10] In his day, atoms were proposed to be the smallest division of matter. Within Leibniz's theory, however, substances are not technically real, so monads are not the smallest part of matter, rather they are the only things which are, in fact, real. To Leibniz, space and time were an illusion, and likewise substance itself. The only things that could be called real were utterly simple beings of psychic activity "endowed with perception and appetite."[11] The other objects, which we call matter, are merely phenomena of these simple perceivers. "Leibniz says, 'I don't really eliminate body, but reduce [revoco] it to what it is. For I show that corporeal mass [massa], which is thought to have something over and above simple substances, is not a substance, but a phenomenon resulting from simple substances, which alone have unity and absolute reality.' (G II 275/AG 181)"[12] Leibniz's philosophy is sometimes called "'panpsychic idealism' because these substances are psychic rather than material".[13] That is to say, they are mind-like substances, not possessing spatial reality. "In other words, in the Leibnizian monadology, simple substances are mind-like entities that do not, strictly speaking, exist in space but that represent the universe from a unique perspective."[14] It is the harmony between the perceptions of the monads which creates what we call substances, but that does not mean the substances are real in and of themselves.[15] |
(III)
複合物質あるいは物質は「実際に無限に細分される」ものであり、その無限小の部分の性質を持つ(§65)。有名な一節(§67)はこう説明する。「物質の
各部分は、植物で満たされた庭園や、魚で満たされた池のように考えられる。しかし植物の各枝、動物の各器官、体液の各滴もまた、同様の庭園や同様の池なの
である」。異なる単子同士、あるいはエンテレケイアとその身体の間には相互作用は存在せず、全ては予め定められた調和によって統制されている(§§
78–9)。これは、ある時計が別の時計と同期しているように見えるが、最初の時計が後者の原因ではない(あるいはその逆も同様)状況に似ている。単に、
最後に巻き上げた者が両者を同じ時刻に設定したため、同じ時刻を示しているに過ぎないのだ。単子も同様だ。互いに原因となっているように見えるが、ある意
味で神の予め定められた調和によって「巻き上げられた」結果、同期しているように見えるに過ぎない。ライプニッツは結論づける。「もし我々が宇宙の秩序を
十分に理解できれば、それは最も賢明な人々のあらゆる願いを超え、現状より良くすることは不可能だと気づくだろう。それは全体としてだけでなく、我々自身
という個別の存在に関しても同様である」(§90)。[10] 当時、原子は物質の最小単位と考えられていた。しかしライプニッツの理論では、物質は厳密には実在しない。ゆえに単子こそが物質の最小単位ではなく、実際 に実在する唯一の事物である。ライプニッツにとって空間と時間は幻想であり、物質そのものも同様だった。実在と呼べるものは、「知覚と欲求を備えた」純粋 に単純な精神活動の存在だけだった。[11] 物質と呼ぶ他の対象は、これらの単純な知覚者の単なる現象に過ぎない。「ライプニッツは言う。『私は実体(物体)を排除するのではなく、その本質に還元 (revoco)する。なぜなら、単純な実体を超えた何かを持つと考えられている物質的質量(massa)は、実体ではなく、単純な実体から生じる現象に 過ぎず、唯一それだけが統一性と絶対的現実性を持つことを示すからだ』」 (G II 275/AG 181)」[12] ライプニッツの哲学は「汎心論的観念論」と呼ばれることがある。なぜならこれらの実体は物質的ではなく精神的だからだ。[13] つまりそれらは心のような実体であり、空間的現実性を有していない。「言い換えれば、ライプニッツの単子論において、単純な実体は厳密には空間に存在しな い精神的な存在であり、独自の視点から宇宙を表現している」[14]。単子たちの知覚の調和が我々が実体と呼ぶものを生み出すが、それは実体がそれ自体で 実在することを意味しない。[15] |
| (IV)
Leibniz uses his theory of Monads to support his argument that we live
in the best of all possible worlds. He uses his basis of perception but
not interaction among monads to explain that all monads must draw their
essence from one ultimate monad.[16] He then claims that this ultimate
monad would be God because a monad is a “simple substance” and God is
simplest of all substances, He cannot be broken down any further.[17]
This means that all monads perceive “with varying degrees of
perception, except for God, who perceives all monads with utter
clarity”.[18] This superior perception of God then would apply in much
the same way that he says a dominant monad controls our soul, all other
monads associated with it would, essentially, shade themselves towards
Him. With all monads being created by the ultimate monad and shading
themselves in the image of this ultimate monad, Leibniz argues that it
would be impossible to conceive of a more perfect world because all
things in the world are created by and imitating the best possible
monad.[19] |
(IV)
ライプニッツは、我々が最善の可能世界に住んでいるという主張を支持するために、モナド論を用いる。彼はモナド間の相互作用ではなく知覚の基盤に基づき、
全てのモナドが究極の単一モナドから本質を引き出さねばならないと説明する[16]。そしてこの究極のモナドこそが神であると主張する。なぜならモナドは
「単純な実体」であり、神は全ての物質の中で最も単純な存在であるからである。神はこれ以上分解できない。[17]
これは全てのモナドが「知覚の度合いに差がある」一方で、「神だけは全てのモナドを完全に明瞭に知覚する」ことを意味する。[18]
この神の優れた知覚は、支配的なモナドが我々の魂を制御するのと同様の原理で作用する。つまり、それに結びついた他の全てのモナドは本質的に、神へと自ら
を模倣していくのである。全てのモナドが究極のモナドによって創造され、この究極のモナドの像に自らを染める以上、ライプニッツは、より完全な世界を構想
することは不可能だと論じる。なぜなら、世界にある全てのものは、可能な限り最善のモナドによって創造され、それを模倣しているからだ。[19] |
| A priori and a posteriori Perspectivism |
ア・プリオリに、そしてア・ポステリオリな 観念論 |
| 1. Lamarra A., Contexte
Génétique et Première Réception de la Monadologie, Revue de Synthese
128 (2007) 311–323 2. Leibniz G.W., La Monadologie, edition établie par E. Boutroux, Paris LGF 1991 3. There is no indication that Leibniz has 'borrowed' it from a particular author, e.g. Giordano Bruno or John Dee, to mention just two popular sources 4. Woolhouse R. and Francks R., Leibniz's "New System" and associated contemporary texts, Cambridge Univ. Press 1997 5. Burnham, Douglas. "Gottfried Leibniz: Metaphysics." Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [accessed May 2, 2016]. 6. On pourrait donner le nom d'entéléchies à toutes les substances simples ou Monades créées, car elles ont en elles une certaine perfection (ἔχουσι τὸ ἐντελές) 7. Audi Robert, ed. "Leibniz, Gottfried Wilhelm." The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge; Cambridge University Press (1999): 193. 8. Look, Brandon C. "Gottfried Wilhelm Leibniz." Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz [accessed February 27, 2016]. 9. Translated by Frederic Henry Hedge. "Leibniz's vestige view of God's creative act is employed to support his view of substance as an inherently active being possessed of its own dynamic force" in David Scott, "Leibniz model of creation and his doctrine of substance", Animus 3 (1998) [1] 10. Burnham, Douglas. "Gottfried Leibniz: Metaphysics." Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [accessed May 2, 2016]. 11. Look, Brandon C. "Gottfried Wilhelm Leibniz." Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz [accessed February 27, 2016]. 12. Look, Brandon C. "Gottfried Wilhelm Leibniz." Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz [accessed February 27, 2016]. 13. Pestana, Mark. "Gottfried Wilhelm Leibniz." World Philosophers & Their Works (2000): 1–4. 14. Burnham, Douglas. "Gottfried Leibniz: Metaphysics." Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [accessed May 2, 2016]. 15. Burnham, Douglas. "Gottfried Leibniz: Metaphysics." Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [accessed May 2, 2016]. 16. Look, Brandon C. "Gottfried Wilhelm Leibniz". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. 17. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Monadology. 18. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Monadology. 19. Antognazza, Maria Rosa (2016). Leibniz. Oxford University Press. |
1. ラマラ
A.、「モナドロジーの遺伝的背景と初期受容」、『レヴュー・ド・シンテーズ』128号(2007年)311–323頁 2. ライプニッツ G.W.、『モナドロジー』、E. ブートルー校訂版、パリ LGF 1991年 3. ライプニッツが特定の著者、例えばジョルダーノ・ブルーノやジョン・ディーといった二つの有名な出典からこれを「借用」した証拠はない。 4. ウールハウス R. とフランクス R.、『ライプニッツの「新体系」と関連する同時代文献』、ケンブリッジ大学出版局 1997 5. バーナム、ダグラス。「ゴットフリート・ライプニッツ:形而上学」 インターネット哲学百科事典、http://www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [2016年5月2日アクセス]。 6. すべての単純な実体、あるいは創造された単子(モノアド)は、それ自体に一定の完成性(ἔχουσι τὸ ἐντελές)を備えているため、エンテレキーと呼ぶことができる。 7. オーディ・ロバート編『 ライプニッツ、ゴットフリート・ヴィルヘルム」。『ケンブリッジ哲学辞典』。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局(1999年):193頁。 8. ルック、ブランドン・C。「ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ」。スタンフォード大学、http: //plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz [2016年2月27日アクセス]。 9. フレデリック・ヘンリー・ヘッジ訳。「ライプニッツの神の創造行為に関する痕跡説は、実体が固有の動的力を備えた本質的に能動的な存在であるという彼の見 解を支持するために用いられる」デイヴィッド・スコット「ライプニッツの創造モデルと実体論」『アニムス』3号(1998年) [1] 10. バーナム、ダグラス。「ゴットフリート・ライプニッツ:形而上学」。インターネット哲学百科事典、http: //www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [2016年5月2日アクセス]。 11. ルック、ブランドン・C. 「ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ」. スタンフォード大学, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz [2016年2月27日アクセス]. 12. ルック、ブランドン・C. 「ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ」. スタンフォード大学, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/leibniz [2016年2月27日閲覧]. 13. ペスタナ、マーク. 「ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ」『世界の哲学者とその著作』(2000年):1–4頁。 14. バーナム、ダグラス。「ゴットフリート・ライプニッツ:形而上学」『インターネット哲学百科事典』、http: //www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [2016年5月2日アクセス]。 15. バーナム、ダグラス。「ゴットフリート・ライプニッツ:形而上学」。インターネット哲学百科事典、http: //www.iep.utm.edu/leib-met/#H8 [2016年5月2日アクセス]。 16. ルック、ブランドン・C。「ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ」。スタンフォード哲学百科事典。スタンフォード大学。 17. ライプニッツ、ゴットフリート・ヴィルヘルム。『モナドロジー』。 18. ライプニッツ、ゴットフリート・ヴィルヘルム。『モナドロジー』。 19. アントニャッツァ、マリア・ローザ(2016)。『ライプニッツ』。オックスフォード大学出版局。 |
| Nicholas
Rescher N., G. W. Leibniz's Monadology, University of Pittsburgh Press,
1991, ISBN 0-8229-5449-4, ISBN 978-0-8229-5449-1 Savile A., Routledge Philosophy Guidebook to Leibniz and the Monadology, Routledge (2000), ISBN 0-415-17113-X, ISBN 978-0-415-17113-7 |
ニコラス・レッシャー N.、『G. W.
ライプニッツのモナドロジー』、ピッツバーグ大学出版局、1991年、ISBN 0-8229-5449-4、ISBN
978-0-8229-5449-1 サヴィル A.、『ライプニッツとモナドロジーのラウトレッジ哲学ガイドブック』、ラウトレッジ (2000)、ISBN 0-415-17113-X、ISBN 978-0-415-17113-7 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Monadology |
☆
力と行為(Puissance
et acte)
力 と行為は、物事の変化を説明するために相反して機能する、哲学の二つの概念である。この二つを区別する考え方は、アリストテレスの形而上学にまでさかのぼ る。
プ ラトンの思想は、純粋に形式的なものであり、物事の本質的な変化を説明することはできなかった。それらはまた、非科学的な方法、すなわち弁証法によって導 き出されたものであった。そのため、アリストテレスは、可動的な存在そのものを概念で囲い込もうとした」[1]。アリストテレスは、潜在力と行為との間に 根本的な対立を創り出した。これらは、2つの基本的な存在論的(存在に関連する)カテゴリーである[2]。 力(古代ギリシャ語では「δύναμις」)は、可能性と同義である。現実のものとは対照的に、可能性としてのみ存在するものは、まだ実現されていない、 単なる仮想的なものである。樫の木は、どんぐりの中に潜在的に存在する。石像は石や青銅の中に潜在的に存在する。潜在力とは可能性の状態にあるものであ り、存在の約束である。彫刻家は石を彫ることで石像を現実のものにする[2]。 行為(ギリシャ語でἔργον、およびἐνέργεια)とは、実現、実行された行為、完成した現実である。それは、世界やその構成要素に形を与えるもの です。つまり、行為は物質に浸透し、それを変容させるのです。 アリストテレスは、エンテレキーという概念を展開し、それまで潜在的な状態にあったものが、最終的な実現、すなわち存在の究極の段階へと昇華することを指 すものと定義した[2]。
聖トマス・アクィナスは、行為と可能性の神学を発展させ、本質的に、神は純粋な行為であり、人間は目に見えるものから神の存在を把握することができるが、人間が神そのものを把握することは不可能であると主張した。 1. 力と行為は存在を分断し、あらゆる存在は、純粋な行為であるか、あるいは必然的に力と行為という第一原理かつ本質的な要素から構成されている。 2. 行為は、それが完全性であるゆえに、完全性の能力である力によってのみ制限される。したがって、行為が純粋である秩序においては、それは無限かつ唯一であるほかなく、有限かつ多重である秩序においては、力との真の構成に入るのである。 3. それゆえ、存在そのものの絶対的な理において、神のみが存続し、唯一完全に単純である。存在に参与する他のすべてのものは、存在を制限する性質を持ち、本質と存在という、実質的に区別された原理から構成されている。
エンテレキーの概念は、ハンス・ドリーシュによって、生物に内在する力として再利用され、単純なメカニズムよりも生命現象をよりよく説明できるものとなった。彼は、ウニに関する自身の研究によってこの理論を実証した。
カルナップは、ドリーシュによるエンテレキーの概念の再解釈を批判し、それは観察できないと述べた。
ドリーシュは、磁力はほとんど観察できないが、物理学での使用に支障はないと答えた。
これに対し、カルナップは次のように反論した:磁力が観測不可能であったとしても、少なくとも測定可能であった。しかし、生命力やエンテレキーはそうではない。磁力の概念は科学を進歩させたが、エンテレキーの概念はむしろ未知の前にそれを置き、科学を阻んだ。
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_et_acte
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099