ハイデガーとナチス
Heidegger and the Nazis; Heidegger y el Nazismo

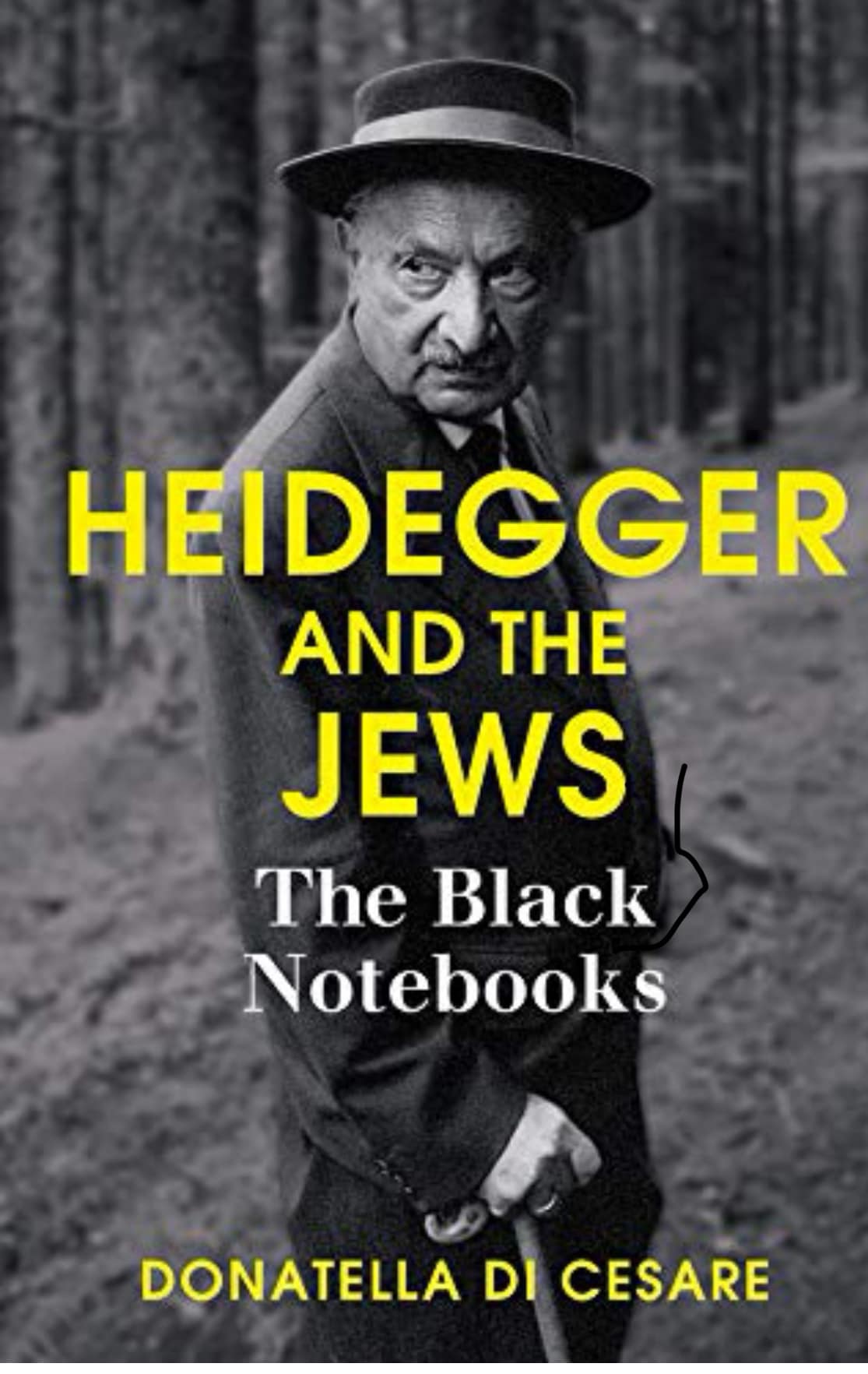
1934年4月23日のフライブルグ大学総長辞任前後の時期のハ イデガー:ナチスの民族指導者の鷲章をつける
ハイデガーとナチス
Heidegger and the Nazis; Heidegger y el Nazismo

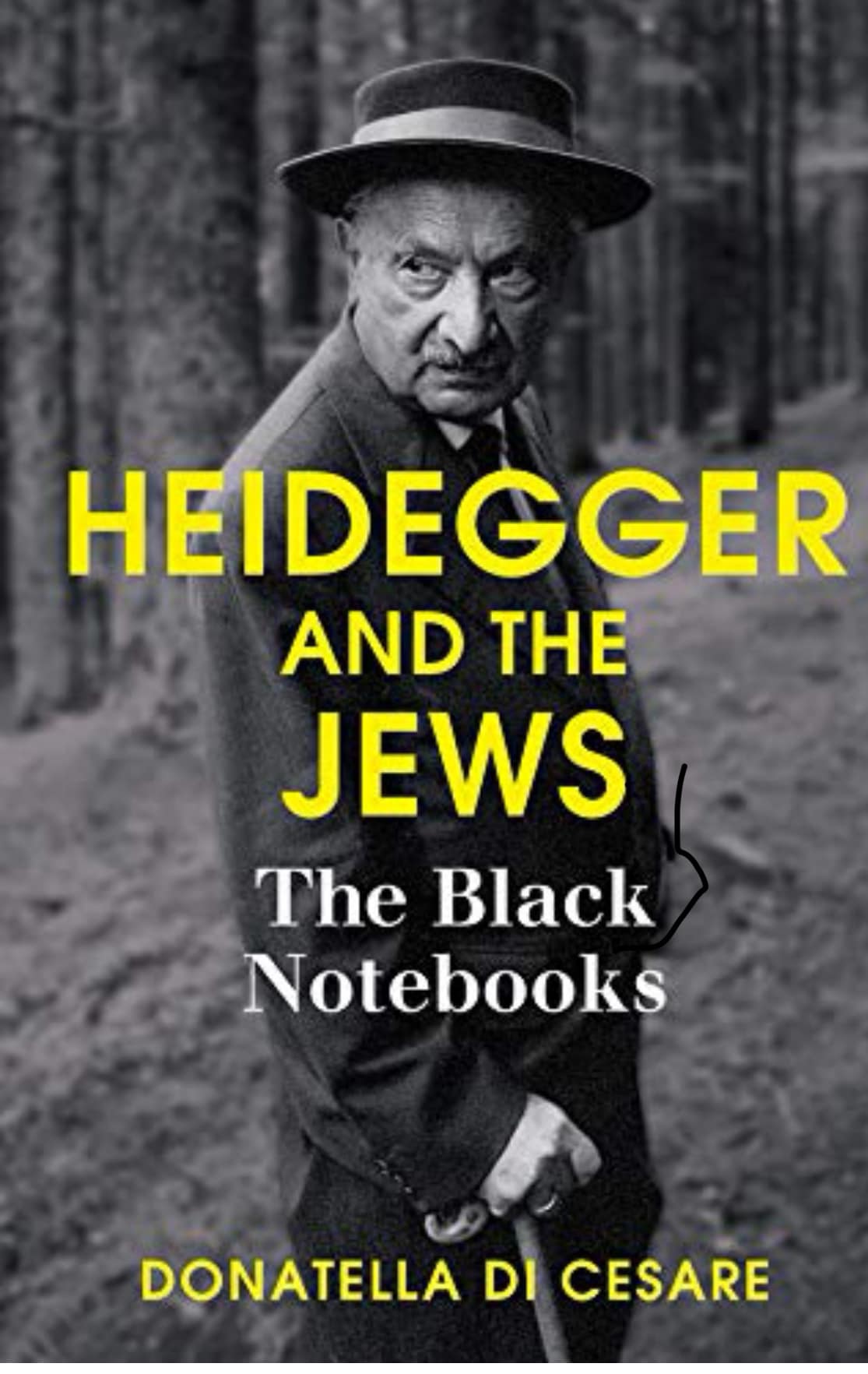
1934年4月23日のフライブルグ大学総長辞任前後の時期のハ イデガー:ナチスの民族指導者の鷲章をつける
解説:池田光穂
★ 「現代におけるハイデガーの著作に関する議論で最も論争を呼んでいるの は、彼の思想が、その道徳的な過ちの公的かつ派手な性格によって、どの程度損なわれているかを判断することである。ハイデガーの国家社会主義運動への支 持、およびナチスや反ユダヤ主義的な言語や表現の使用は、十分に文書化され、暴露されている(Denker & Zaborowski 2009a; Ott 1988 [1993]; Farias 1987 [1989]; Faye 2005 [2009]を参照)。ジュリアン・ヤングが言うように、ハイデガーが「本物のナチであった」という疑いはもはやない。彼の関与は妥協や日和見主義、ある いは臆病さではなく、信念の問題であった(Young 1997: 4)。また、彼は「あからさまな反ユダヤ主義者」であり、「1930年から少なくとも1934年までは、ヒトラーとナチスを強く支持していた」 (Sheehan 2015a: 368)。 また、戦後、ハイデガーがヒトラー政権下におけるナチス運動を支援する政治活動の性格と深さを隠すために、繰り返し嘘をついたり、事実を歪曲したりしてい たことも明らかになっている。さらに、彼はナチズムへの支持を公に明確に否定したことは一度もない。ホロコーストについて語る稀な機会においても、例え ば、ホロコーストを東ドイツに対する抑圧的なソ連の占領と同一視するなどして、ドイツの罪の問題から注意をそらしていた。」(3. Nazi-Era Writings より)
★1944 年ハイデガー(55歳)夏学期、ヘラクレイトス講義。この講義のなかでハイデッガーは「ドイツ民族が西洋の歴史的な民族でありつづけるのか、それともそう でないのかどうかという、このことだけが決定を迫られているのではなくて、今は大地の人間が大地もろともに危険にさらされているのであり、しかも 人間自身によってそうなのである[『全集55』79ページ]」「こ の惑星は炎に包まれている。人間の本質は支離滅裂になっている。ドイツ人がドイツ的なものを見出し、保持 するということが想定されるとすれば、世界史的な熟慮が生まれるのはドイツ人からのみである。それは思い上がりではないが、しかし元初的な苦境を決着にい たるまで持ちこたえるという必然性の知である[『全集55』138ページ]」と語った。
☆「語つまりそのなかで歴史的な人 間の本質が自らを委 ね渡している語とは、真有の語である。この元初的な語は詩作と思索のなかで保有される。たとえ何がそしていかに西洋の外的な歴運が接合されるにせよ、ドイ ツ人たちの最大にして本当の試練、つまり彼らがあるいは無知な者たちによって彼らの意に反して試されるかもしれない彼の試練はなおも目前に迫っている、す なわち、彼ら、ドイツ人たちは真有の真性との融和の内にあるのかどうか、また彼らは死への覚悟を越えて、現代世界の視野の狭さに対して元初的なものをその 目立たない飾りの内へと救い出すほど十分に強靭であるのかどうかと」[『全集55』208ページ]☆2013 年、ヴィットリオ・クロスターマン社全集94-96巻に掲載されたハイデッガーが1930年代から1970年代にかけて書き続けた手稿 「黒ノート」に反ユダヤ主義についての箇所があることが問題に。この件に関しては、ジャン=リュック・ナンシーのみが、一番まともで、ハイデガーのナチス 協力とナチスへの信 奉はゆるぎないもので、誰も知っていたことで「ハイデッガーが反ユダヤ主義に加担したことは1950年代から知られていたし、ハイデッガーの限界とは我々 の限界でもあると論じた」
☆民俗=民族(フェルキッシュ)意識:「フェルキッシュ (独: völkisch)
は、 フォルク(独:
Volk)からの派生語として重要な語である。フェルキッシュは19世紀末から第二次世界大戦終了時までドイツにおいて普通に使われ、当時の出版物と政治
において大きな役割を果たした。20世紀の中頃からこの表現は殆ど使われなくなった(独和辞典では古語として扱われている)。しかしながら、現代のドイツ
においてこの語に合致した運動や政党が2013年‐2014年頃から勃興し、フェルキッシュという語を使った解説記事が増えている。フェルキッシュという
語は現代において人種主義
(レイシズム)という概念に移し替えられたり、反セム主義の一種であると記述されることもある。ドイツ語圏においてフェルキッシュ運動、フェルキッシュ・
ナショナリズムという用語も使われて いる。
フェルキッシュは「民族の、国家主義的」と訳される場合もあるが、近代ドイツの歴史と密接につながっているため、英語のナショナリズム
(nationalsm) ともエスノセントリズム (ethnocentrism)
とも異なる意味を含んでいる。ナチス政権時代において、1933年からフェルキッシュ、もしくはドイツ・フェルキッシュという語はしばしば国家社会主義と
同義語として使われた[15]。この語は政権側で頻繁に 使用されるボキャブラリーに入っていた[16](ナチスの言語, Sprache des
Nationalsozialismusも参照)。フェルキッシュとは別の人種差別的メルクマールを欧州におけるファシズム陣営は作り出した[17]。
フェルキッシュ概念に、同じイデオロギーに根拠づけられたフレムトフェルキッシュ(異 民族)(独:fremdvölkisch)
という語が対置することになった。それゆえ、異民族によって構成される住民集団はド
イツ民族共同体にとって危険な存在と見なされ、居住地域を分けることが
語られた。なるほど、フレムトフェルキッシュ(異民族)は労働力の一部として必要な存在とされたが、法的権利や保護は縮小されるか、認められない扱いを受
けるとされた[18]。フレムトフェルキッシュ(異民族)という語の造語に関して、ナチス政権関係者による関与は大きくはない。ナチス政権成立の1933
年より前において、人種学(優生学)者ハンス・ギュンターが
ドイツ民族の人種学という学問分野においてこの専門用語を用いていた。さらに、19世紀に結成された全ドイツ連盟という汎ゲルマン主義組織の指導者ハイン
リヒ・クラース(ドイツ語版)も1912年においてフレムトフェルキッシュ(異民族)外国人をドイツの労働力として用いることに賛成していた[19]。」
●ハイデガーの政治的存在論(ピエール・ブルデュ)——L'ontologie politique de Martin Heidegger.
| アウトライン |
(ハイデガーの 用語)時間性————(含意)福祉国家糾弾 (ハイデガーの用語)彷徨 の糾弾 ——(含意)反ユダヤ主義 1)歴史的文脈の検証 2)哲学者に陣地をあてがう大学 3)教員やポストを改廃する権力構造 4)ワイマール・ドイツの社会構造 |
| 序論 いかがわしい思想 | ・哲学の世俗からの切断という意識が哲学の限界づけられた考え方 ・哲学と言えども時代の子(ただしこれは超越論的な歴史主義を結果的に肯定する) ・ハイデガーに純粋性を認めるのはナンセンスだが、ハイデガーを政治思想家とするのもナンセンス ・哲学の世俗世界からの自律の有無を考えるのではなく、そこから逃れ得ないこと。あるいは逃れ得た/るべきという哲学者のポーズ(あるいは自己の学問への 無理解)を問うことが重要 ・哲学は特殊な時代性をもつ。すなわち、ナチの時代を生きたハイデガーとその著作の「特殊な時代性」について考察しなければならない。 ・ハイデガーの著作は哲学的に読むと《同時に》政治的にも読まねばならない——二重の読解。 ・さらには、これまでの通俗的な政治概念の相対化、すなわち、読解を通した「政治概念の刷新」がもとめられている。 1)哲学の時代性と純粋性 2)政治的かつ哲学的に読むこと |
| 第1章 純粋哲学と時代 精神 | ・ハイデガー哲学の時代は、「フェルキッシュ(民族的・民俗的)」という概念が重要視された時代である。 ・ハイデガーとその他の思想家(シュペングラー、ユンガー)との関係 1)両大戦間のイデオロギー的雰囲気 2)家父長制/回心/山岳 3)シュペングラーとトレルチ 4)大学内に広がる反主知主義 5)シュペングラーとハイデガー 6)ユンガーとハイデガー 7)ぼんやりした統一 8)倫理—政治的な方向感覚 9)保守的革命 10)第三の道 11)ハイデガー存在論の政治的基礎——「本源的人種」の概念など 12)政治と哲学の境界線 13)能動的ニヒリズムから受動的ニヒリズムへ |
| 第2章 哲学界と可能性 空間 | ・ハイデガーデビュー直前の新カント派の状況 ・時代状況から自律しているとはどういうことか? ・その哲学的読解。 1)哲学界における政治的立場表明 2)哲学界の状況と新しい立場 3)ハイデガーのハビトゥス 4)知的世界のいごこちの悪さ 5)ハイデガーの文体 |
| 第3章 哲学における 「保守的革命」 | ・ハイデガーの目論見は「保守的革命」にある ・「保守的革命」の文脈においては、政治と哲学は対応関係があり、また共存している。それ「相同的」と呼ぶ。 ・哲学的読解と、政治的読解の対応関係を明らかにする 1)政治・大学・哲学を貫く理論路線 2)徹底的な乗り越えの戦略 3)歴史・時間の存在論化とその実践的表現 4)超越論的なものの存在論化から否定的存在論へ |
| 第4章 検閲と作品制作 | ・ハイデガーの哲学文体の検証。 1)形式と内容 2)仮象だけの断絶と哲学体系 3)暴露=隠蔽 4)エリートと大衆 5)社会からの距離 6)倫理的主意主義 |
| 第5章 内的な読解と形 式の尊重 | ・ハイデガーが読者に要求する読解や解釈のやり方について 1)形式的言説は形式的読解を求める 2)哲学者の自己解釈 3)作品と解釈者の相対的立場 4)ハイデガーに共鳴する土壌 |
| 第6章 自己解釈と体系 の進化 | ・ハイデガーによる、ハイデガーの作品の読解 1)体系化の到達点としての「転回」 2)進化の原理としての警戒 3)本質的思考は本質的なことを思考しなかった |
★ナチス時代のハイデガーの書物
| 3. Nazi-Era Writings |
3. ナチス時代のハイデガーの書物 |
| The most controversial issue in
contemporary discussions of Heidegger’s work is that of determining the
extent to which his thought is compromised by the public and
spectacular character of his moral failings. Heidegger’s support for
the National Socialist movement, and his use of Nazi and anti-Semitic
language and tropes, has been amply documented and exposed (see Denker
& Zaborowski 2009a; Ott 1988 [1993]; Farias 1987 [1989]; Faye 2005
[2009]). It is no longer possible to doubt that, as Julian Young puts
it, Heidegger was “a real Nazi: his involvement was a matter of
conviction rather than compromise, opportunism, or cowardice” (Young
1997: 4). He was also “an unabashed anti-Semite”, and “a strong
supporter of Hitler and the Nazis from 1930 through at least 1934”
(Sheehan 2015a: 368). It is also now clear that, after the war,
Heidegger repeatedly lied or distorted the record to conceal the
character and depth of his political activities in support of the Nazi
movement during the Hitler regime. Moreover, he never publicly and
explicitly renounced his support for National Socialism. On the rare
occasions when he addressed the Holocaust, he deflected attention away
from the question of German guilt by, for instance, equating the Shoah
with the repressive Soviet occupation of East Germany. |
現代におけるハイデガーの著作に関する議論で最も論争を呼んでいるの
は、彼の思想が、その道徳的な過ちの公的かつ派手な性格によって、どの程度損なわれているかを判断することである。ハイデガーの国家社会主義運動への支
持、およびナチスや反ユダヤ主義的な言語や表現の使用は、十分に文書化され、暴露されている(Denker & Zaborowski
2009a; Ott 1988 [1993]; Farias 1987 [1989]; Faye 2005
[2009]を参照)。ジュリアン・ヤングが言うように、ハイデガーが「本物のナチであった」という疑いはもはやない。彼の関与は妥協や日和見主義、ある
いは臆病さではなく、信念の問題であった(Young 1997:
4)。また、彼は「あからさまな反ユダヤ主義者」であり、「1930年から少なくとも1934年までは、ヒトラーとナチスを強く支持していた」
(Sheehan 2015a: 368)。
また、戦後、ハイデガーがヒトラー政権下におけるナチス運動を支援する政治活動の性格と深さを隠すために、繰り返し嘘をついたり、事実を歪曲したりしてい
たことも明らかになっている。さらに、彼はナチズムへの支持を公に明確に否定したことは一度もない。ホロコーストについて語る稀な機会においても、例え
ば、ホロコーストを東ドイツに対する抑圧的なソ連の占領と同一視するなどして、ドイツの罪の問題から注意をそらしていた。 |
| While the basic facts of the
Heidegger case are by now well-known, there are widely disparate
interpretations of the significance of these facts for an understanding
of Heidegger: was he a base opportunist, taking advantage of a
revolutionary movement to advance his own aims? Was he politically
naïve? Was he, as he later claimed, hoping to use the rectorship to
protect the university from “unsuitable persons” and from “the
threatening supremacy of the party apparatus and the party doctrine”
(GA16: 574–5)? Was he, as he also claimed, trying to temper the basest
impulses of the Nazi party, and lead the movement in a more positive
direction (see GA16: 377)? Or was he a true believer in Hitler and
Hitler’s National Socialism—an enthusiastic sympathizer with and
accomplice to the Nazi agenda for “German rebirth”? There is a large
and expanding literature devoted to exploring these issues, and
philosophers have staked out a very broad range of positions on these
questions (see Denker & Zaborowski 2009b; Bourdieu 1988 [1991]; Ott
1988 [1993]; Farias 1987 [1989]; Sluga 1993; Pöggeler 1990; Young 1997;
Faye 2005 [2009]; Sheehan 2015a). Nowhere has the debate over the
scandal of Heidegger’s National Socialism been more heated than in
France—perhaps owing to the depth and breadth of influence that
Heidegger had on French philosophy (see Janicaud 2001 [2015]). |
ハイデガー事件の基本的事実はすでに広く知られているが、ハイデガーの
理解にとってこれらの事実の持つ意味については、大きく異なる解釈が存在している。彼は革命運動を利用して自身の目的を推進しようとした卑しい日和見主義
者だったのか?彼は政治的にナイーブだったのか?
後に彼が主張したように、学長職を利用して大学を「不適格な人物」や「党機構と党の教義の脅威的な優越性」から守ろうとしていたのか(GA16:
574-5)? また、彼が主張したように、ナチ党の卑しい衝動を和らげ、運動をより前向きな方向に導こうとしていたのか(GA16:
377を参照)?それとも、彼はヒトラーとヒトラーのナショナリズムを心から信奉し、「ドイツ再生」というナチスの大義に熱狂的に共鳴し、その共犯者で
あったのだろうか?
これらの問題を探究する文献は数多くあり、その数は増え続けている。哲学者たちは、これらの問題について非常に幅広い立場を主張している(Denker
& Zaborowski 2009b; ブルデュー 1988年 [1991年]、オット 1988年 [1993年]、ファリアス
1987年 [1989年]、スルーガ 1993年、ペッゲラー 1990年、ヤング 1997年、フェイ 2005年 [2009年]、シーハン
2015a年)。ハイデガーのナショナリズムに関するスキャンダルをめぐる議論がこれほどまでに白熱したのはフランスにおいてが最も顕著であるが、それは
おそらく、ハイデガーがフランス哲学に与えた影響の深さと広さによるものだろう(Janicaud 2001 [2015]を参照)。 |
| At one end of the spectrum,
Young, maintains that Heidegger’s philosophical works can be fully
‘de-Nazified’—that Heidegger’s philosophical thought does not “stand in
any essential connection to Nazism” (Young 1997: 5). Moreover, Young
argues, “one may accept any of Heidegger’s philosophy, and … preserve,
without inconsistency, a commitment to orthodox liberal democracy”
(Young 1997: 5). |
一方、ヤングは、ハイデガーの哲学作品は完全に「非ナチ化」できると主
張している。すなわち、ハイデガーの哲学思想は「ナチズムと本質的なつながりがあるわけではない」(Young 1997:
5)というのだ。さらに、ヤングは「ハイデガーの哲学のどれかを受け入れ、…正統的な自由民主主義への献身を矛盾なく維持することができる」と主張してい
る(Young 1997: 5)。 |
| At the other extreme, Faye
argues that it is “impossible to dissociate [Heidegger’s work in its
entirety] from his political commitments”, and that Heidegger
“dedicated himself” to “the introduction into philosophy of the very
content of Nazism and Hitlerism” (Faye 2005 [2009: 7]). Indeed, Faye
goes so far as to contend that “Heidegger’s work is not at all a
‘philosophy’”, that in his work “the very principles of philosophy are
abolished” (Faye 2005 [2009: 4 & 316]). |
一方、フェイは「ハイデガーの仕事全体を彼の政治的献身から切り離すこ
とは不可能」であり、ハイデガーは「ナチズムとヒトラー主義のまさにその内容を哲学に導入することに」「身を捧げた」と主張している(Faye
2005 [2009:
7])。実際、フェイは「ハイデガーの著作はまったく『哲学』ではない」と主張し、彼の著作では「哲学の原理そのものが廃止されている」とまで述べている
(Faye 2005 [2009: 4 & 316])。 |
| Claims that Heidegger’s work is not philosophical or “destructive of philosophy” are belied by the fecundity of his thought for ongoing philosophical research in a variety of fields (including the phenomenology of perception and action, the philosophy of mind, the philosophy of artificial intelligence and cognitive science, ontology, the philosophy of time, the philosophy of art, the history of philosophy, and moral psychology). | ハイデガーの仕事は哲学的ではない、あるいは「哲学を破壊する」という
主張は、知覚と行動の現象学、心の哲学、人工知能と認知科学、存在論、時間哲学、芸術哲学、哲学史、道徳心理学など、さまざまな分野における現在進行中の
哲学研究に対する彼の思想の豊饒さによって否定される。 |
| At the same time, the suspicions
raised by Heidegger’s Nazi past (and by his efforts to conceal that
past) are too important to be ignored by scholars and students of his
work. There can be little doubt that much of his work during the
Nazi-era bears unmistakable resonances and affinities with Nazi
ideology. National Socialism’s glorification of traditional rural
German life, and its rhetorical anti-modernism and anti-cosmopolitanism
finds echoes in Heidegger’s critique of technology (see section 5.2).
Nazi rhetoric of renewal and rebirth resonated with Heidegger growing
conviction that Western metaphysics had run its course, that another
beginning was needed (see supplement: Heidegger and the Other
Beginning). Indeed, Heidegger repeatedly rationalized his initial
attraction to the Nazi party on just this basis (see GA95: 407; GA16:
430; GA16: 374). |
同時に、ハイデガーのナチス党員としての過去(およびその過去を隠そう
としたこと)から生じた疑念は、彼の作品の研究者や学生にとって無視できないほど重要である。ナチス党員時代における彼の作品の多くが、ナチス党のイデオ
ロギーと明白な共鳴と親和性を持っていることは疑いの余地がない。ナチズムが称揚する伝統的なドイツの田舎暮らし、そしてその誇張された反近代主義と反国
際主義は、ハイデガーのテクノロジー批判(セクション5.2参照)にも響いている。ナチスの再生と復活をうたうレトリックは、西洋形而上学は行き詰まり、
新たな始まりが必要だというハイデガーの確信を強めていった(補遺:ハイデガーとその他の始まりを参照)。実際、ハイデガーはナチ党に惹かれた理由を、ま
さにこの点に求めて繰り返し正当化している(GA95: 407; GA16: 430; GA16: 374を参照)。 |
| As many scholars have noted,
Heidegger’s embrace of National Socialism was tied up with his critique
of technology. Habermas claims, for instance, that “In 1935 Heidegger
still saw the inner truth and greatness of the National Socialist
movement in the ‘encounter between global technology and modern man’”
(Habermas 1985 [1987: 159]). Heidegger eventually came to view National
Socialism as a “consummate form of modernity”, the “triumph of
machination” (GA96: 127). And that made National Socialism something
that itself needed to be overcome in the transition to a
non-metaphysical form of dwelling (see Habermas 1985 [1987: 159–60]).
But decades later, Heidegger continued to hold that “National Socialism
did indeed go in the direction” of “attaining an adequate relationship
to the essence of technology” (GA16: 677). |
多くの学者が指摘しているように、ハイデガーのナチズムへの傾倒は、テ
クノロジー批判と結びついていた。例えば、ハーバーマスは「1935年、ハイデガーは依然として、ナチズム運動の真髄と偉大さを『グローバルテクノロジー
と近代的人間の出会い』に見出していた」と主張している(Habermas 1985 [1987:
159])。ハイデガーは最終的に、ナチズムを「近代の完成形」、すなわち「策略の勝利」とみなすようになった(GA96:
127)。そして、ナチズムは非形而上学的住居への移行において克服されるべきものとなった(ハーバーマス 1985 [1987:
159–60]を参照)。しかし、それから数十年後、ハイデガーは「ナチズムは確かに『技術の本質との適切な関係を達成する』という方向に向かっていた」
という見解を維持した(GA16: 677)。 |
| Perhaps the most significant and
clearest point of affinity between Nazi ideology and Heidegger’s
writings during the Nazi era centers on the völkisch ethno-nationalism
that Heidegger incorporated into his account of the history of being in
the 1930s. Consistently throughout his career, Heidegger was an
anti-individualist about meaning—that is, he argued that the primary
disclosure of being is social in character. In Being and Time, it is
“the anyone-self” who “articulates the referential context of
significance” in terms of which entities are encountered (SZ 129), and
“prescribes that way of interpreting the world and being-in-the-world”
(SZ 129). After the war, it is neighborhoods and localities of mortals
who disclose the sense of things by dwelling together while gathered by
the fourfold. But for a time in the 1930s Heidegger argues that the
disclosive “we-self” is a people (Volk) that shares a history, a soil,
blood, a language, tasks, possibilities, moods, and a destiny. Like the
Nazis, Heidegger held a racist and anti-Semitic conception of the
essence of the German people, although he rejected the Nazi’s
biologistic conception of race. Like other völkisch nationalists of the
time, Heidegger was convinced that the German people had a special
destiny in saving Western civilization. But for Heidegger, unlike the
Nazis, the leading role for the German people to play was that of
overcoming metaphysics and inaugurating a new history of being. |
おそらく、ナチス時代のナチスイデオロギーとハイデガーの著作の最も重
要な共通点、そして最も明白な共通点は、ハイデガーが1930年代に存在の歴史の説明に取り入れた民族主義的な民族ナショナリズムである。ハイデガーは生
涯を通じて一貫して、意味について反個人主義者であった。つまり、存在の本質的な開示は社会的性格を持つと主張した。『存在と時間』では、「存在体」が遭
遇する「意味の参照文脈を明確にする」のは「誰でも自分自身」であり(SZ 129)、「世界と世界における存在の解釈の方法を規定する」(SZ
129)とされている。戦後、四つのものに集められながら共に住むことで、物事の意味を明らかにするのは、人間たちの近隣や地域である。しかし、1930
年代のある時期、ハイデガーは、明らかにする「私たち自身」は、歴史、土壌、血統、言語、任務、可能性、気分、そして運命を共有する民族(フォルク)であ
ると主張した。ナチスと同様に、ハイデガーはドイツ民族の本質について人種差別的で反ユダヤ的な考えを持っていたが、ナチスの人種に関する生物学的な考え
方は否定していた。当時の他の民族派ナショナリストと同様に、ハイデガーはドイツ民族が西洋文明を救うという特別な使命を持っていると確信していた。しか
し、ハイデガーにとって、ナチスとは異なり、ドイツ民族が果たすべき主導的な役割は、形而上学を克服し、新たな存在の歴史を始めることだった。 |
| Heidegger’s arguments in favor
of an ethno-nationalist account of the disclosure of being are,
however, unconvincing. One can grant the communal character of human
existence, accept that we are essentially historical beings, and agree
with an anti-individualist account of the disclosure of being—all
without tying that disclosure to a particular ethnic group, people,
nation, or state. Heidegger arguments for a völkisch nationalism in his
lecture courses were sketchy at best. And already in the 1940s,
Heidegger came to view the ethno-nationalist conception of a people
(das Völkische) as a product of the subjectivity of modern metaphysics
(see, e.g., GA5: 111, GA54: 204). |
しかしながら、ハイデガーの民族ナショナリズム的な「存在の啓示」に関 する主張は説得力に欠ける。 人間の存在が共同体的であることを認め、人間が本質的に歴史的存在であることを受け入れ、そして「存在の啓示」を特定の民族、人々、国家、あるいは国家体 制に結びつけることなく、反個別主義的な「存在の啓示」の説明に同意することは可能である。 ハイデガーの講義における民族ナショナリズムの主張は、よく言えば大まかなものであった。そして、1940年代にはすでに、ハイデガーは民族主義的な民族 観(das Völkische)を近代形而上学の産物として捉えるようになっていた(例えば、『GA5』111ページ、『GA54』204ページを参照)。 |
| At the same time, we should
remain alive to the fact that Heidegger’s account of the history of
being, his critique of technology, and his essay on the
world-disclosive significance of works of art, all came out of this
period of Heidegger’s adventures in ethno-nationalism. It would be
irresponsible to not sensitize ourselves to the question whether
Heidegger’s nationalist and racist views have affected or distorted his
understanding of history (including his critique of the technological
age). |
同時に、ハイデガーの存在の歴史に関する説明、テクノロジーに対する批
判、芸術作品の世界を明らかにする意義に関する論文は、すべて民族ナショナリズムに傾倒したハイデガーの冒険の時代に生まれたものであるという事実を、私
たちは認識しておくべきである。ハイデガーの民族主義的・人種差別的な見解が、彼の歴史観(技術時代の批判を含む)に影響を与えたり歪めたりしたかどうか
という問題に注意を向けないのは無責任である。 |
| https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#NaziEraWrit |
☆ハイデガーのメタ政治(ハイデガーがナチ政治にコミットメントしている時期に真剣に考えた「ニヒリズムの超克」)
| Heidegger's
metapolitics isn't traditional politics but a profound philosophical
project to critique modern Western thought (metaphysics) that he saw as
leading to technological nihilism and spiritual emptiness, aiming for a
radical "Other Beginning" of history through a return to fundamental
Being, often linked with his controversial embrace of Nazism as a
potential catalyst for this spiritual and cultural transformation of
the German Volk (people) and state, a concept involving a metaphysical
reorientation of humanity's relationship to Being. |
ハイデガーのメタ政治は伝統的な政治ではなく、彼が技術的ニヒリズムと
精神的空虚へと導くと見なした近代西洋思想(形而上学)を批判する深遠な哲学的企てである。それは根本的存在への回帰を通じて歴史の「別の始まり」を目指
すものであり、しばしばドイツ民族と国家の精神的・文化的変革の潜在的触媒としてのナチズム支持という論争的な立場と結びついている。「他の始まり(他者
のはじまり/別のはじまり)」を目指す歴史の根本的転換を志向する。この転換は、ドイツのフォルク(民族)と国家に対する精神的・文化的変革の触媒とし
て、彼が物議を醸したナチズム受容と結びつけられることが多い。この概念は、人間と存在との関係における形而上学的再方向付けを伴うものである。 |
| Core Concepts of Heidegger's Metapolitics: Critique of Metaphysics: Heidegger believed modern metaphysics, culminating in technology, reduced Being to mere "presence" (ousia/substance), leading to the "forgetting of Being" and a world of comfort, calculation, and kitsch, exemplified by the US and Soviet Union as metaphysically similar, notes Project MUSE. |
ハイデガーのメタ政治学の核心概念: 形而上学批判:ハイデガーは、技術に頂点を迎えた近代形而上学が、存在を単なる「在り」(ousia/実体)へと還元し、「存在の忘却」と、米国とソ連が 形而上学的に類似した例として示される、安逸と計算とキッチの世界をもたらしたと考えた。Project MUSEはこう記す。 |
| Ontological Foundation: Metapolitics posits that political practices are rooted in deeper ontological structures (the history of Being) that need radical change, an "ontologisation of the political," explains Cambridge University Press & Assessment. |
存在論的基盤: メタ政治学は、政治的実践がより深い存在論的構造(存在の歴史)に根ざしており、根本的な変革、すなわち「政治の存在論化」が必要だと主張する。ケンブリッジ大学出版局とアセスメントが説明している。 |
| Spiritual Nazism: In his Black Notebooks, this concept becomes explicit: Nazism was seen not just as a political movement but as a potential vehicle for this metaphysical renewal, a spiritual awakening for the German people (Volk) to move beyond modern decadence. |
精神的ナチズム: 彼の『黒いノート』において、この概念は明示される。ナチズムは単なる政治運動ではなく、この形而上学的な再生、すなわちドイツ民族(フォルク)が近代的退廃を乗り越えるための精神的覚醒をもたらす可能性を秘めた手段と見なされていたのだ。 |
| "Second/Other Beginning": The goal of this metapolitical transformation was to prepare for a new historical epoch, a "second beginning," by clearing away the errors of metaphysics and technology. |
「第二の/その他の始まり」: このメタ政治的変革の目的は、形而上学と技術の誤りを一掃することで、新たな歴史的時代、すなわち「第二の始まり」に備えることだった。 |
| Action over Theory: It emphasized spiritual action and authentic decision-making, prioritizing a fundamental shift in human-Being relation over mere political theory or comfortable bourgeois life, according to ResearchGate and Project MUSE. |
理論より行動: ResearchGateとProject MUSEによれば、それは精神的な行動と真の意思決定を強調し、単なる政治理論や安楽なブルジョア的生活よりも、人間存在の関係における根本的な転換を優先した。 |
| Controversy & Interpretation: |
論争と解釈: |
| Connection to Nazism: Heidegger's metapolitics is inseparable from his support for National Socialism, which he viewed as a movement that could enact this profound cultural and spiritual revolution, making him an "ideologue of 'metapolitical fascism'," according to Taylor & Francis Online. |
ナチズムとの関連性: ハイデガーのメタ政治学は、彼がナショナリズムへの支持と切り離せない。彼はナショナリズムを、この深遠な文化的・精神的革命を実現しうる運動と見なして いた。テイラー&フランシス・オンラインによれば、これにより彼は「メタ政治的ファシズムのイデオロギー家」となったのである。 |
| Beyond Conventional Politics: It's "metapolitics" because it aims to change the very foundations of political existence, not just political systems, linking national destiny with philosophical destiny, writes Cambridge University Press & Assessment. |
従来の政治を超えたもの: ケンブリッジ大学出版局とアセスメントはこう記す。それは単なる政治体制ではなく、政治的存在そのものの基盤を変えようとするから「メタ政治」と呼ばれる。国民の運命と哲学的運命を結びつけるのだ。 |
| In essence, Heidegger's
metapolitics sought to re-ground political life in a fundamental
experience of Being, using the upheaval of his time (Nazism) as a
potential, albeit deeply problematic, path towards a new, authentic
historical destiny for humanity, as explored in ResearchGate. |
本質的に、ハイデガーのメタ政治学は、当時の激動(ナチズム)を、人類 にとって新たな、真正な歴史的運命への道筋として——たとえそれが深く問題を抱えていたとしても——潜在的可能性として利用し、政治的生活を存在の根本的 経験に再基盤化しようとした。これはResearchGateで考察されている通りである。 |
| Google AI |
|
| In Martin Heidegger's
philosophy, "metapolitics" is not a typical political theory but a
profound link between his ontology (study of being) and his radical,
ethno-nationalist political engagement with Nazism. Heidegger used the
term in his Black Notebooks to describe a philosophical approach that
sought to transform society at its metaphysical foundation, beyond
conventional politics. Core Concepts Beyond Conventional Politics: For Heidegger, "metapolitics" superseded traditional politics (which he associated with the "end of philosophy" and modern nihilism). It was an attempt to deconstruct modern political ideas—like liberalism and Bolshevism—which he saw as ultimately the "same" in their shared metaphysical underpinnings. Ontology and Politics Intertwined: The concept involves an "ontologisation of the political" and a "politicisation of ontology". This means that the political revolution he advocated was a means to a metaphysical end: the realization of a new, authentic relationship to Being (Sein). Spiritual National Socialism: Heidegger described his political commitment as a "spiritual National Socialism". He believed philosophical concepts could serve as a "weapon" in the struggle for the German people to become a "true community" capable of asking the fundamental question of Being. The Role of the Volk (People): Heidegger's metapolitics centered on the idea of a specific "historical people" or Volk (the German people), who he believed were uniquely situated for this metaphysical transformation. This concept was tied to a radical and essentialist vision of community and destiny, involving anti-Semitic elements that have been widely documented and debated by scholars since the publication of his Black Notebooks. Educational Institutions: A key aspect of his project involved reshaping German educational institutions to implement this "spiritual" engagement and cultivate a new "aristocracy of spirit". In essence, Heidegger's metapolitics was a vision of a total cultural and spiritual transformation, driven by a specific philosophical understanding of history and existence, in direct opposition to modern liberal democracy and rooted in a deeply problematic affiliation with National Socialist ideology |
マーティン・ハイデガーの哲学において、「メタ政治」は典型的な政治理
論ではなく、彼の存在論(存在の研究)と、ナチズムに対する彼の急進的な民族主義的・ナショナリストな政治的関与との深い関連性である。ハイデガーは『黒
いノート』の中で、従来の政治を超えた、形而上学的な基盤から社会を変革しようとする哲学的アプローチを表すためにこの用語を用いた。 中核概念 従来の政治を超越:ハイデガーにとって、「メタ政治」は、従来の政治(「哲学の終焉」や現代のニヒリズムと関連づけていた)に取って代わるものであった。 それは、リベラリズムやボルシェヴィズムといった現代の政治思想を、その共通する形而上学的基盤において、究極的には「同じ」ものと見なして、脱構築しよ うとする試みであった。 存在論と政治の相互浸透:この概念は「政治の存在論化」と「存在論の政治化」を包含する。つまり彼が提唱した政治革命は、形而上学的目的——存在(Sein)との新たな真の関係の実現——を達成するための手段であった。 精神的ナショナリズム:ハイデガーは自らの政治的関与を「精神的ナショナリズム」と表現した。彼は哲学的概念が、ドイツ民族が「存在」の根本的問いを投げかけることのできる「真の共同体」となるための闘争における「武器」となり得ると信じていた。 民族(フォルク)の役割:ハイデガーのメタ政治は、特定の「歴史的民族」すなわちフォルク(ドイツ民族)という概念を中心に据えていた。彼はこの民族が形 而上学的変革に唯一適した立場にあると考えた。この概念は、共同体と運命に関する急進的かつ本質主義的なビジョンと結びついており、彼の『黒ノート』出版 以降、学者たちによって広く記録され議論されてきた反ユダヤ主義的要素を含んでいた。 教育機関:彼の計画の核心は、この「精神的」関与を実践し新たな「精神の貴族」を育成するため、ドイツの教育機関を再構築することにあった。 本質的にハイデガーのメタ政治学は、特定の哲学的歴史観と存在論に基づく文化的・精神的変革の構想であり、近代的自由民主主義と対立し、国家社会主義イデオロギーとの深く問題のある結びつきに根ざしていた。 |
●暴力と政治(権威)
私が与える暴力の定義と は、「人を従属させる破壊的な強制力のこと」である。〈従属させる強制力〉すなわち〈暴力〉の帰結とは、動産の破壊、人間や 動物の殺傷などがある。このために、人は暴力の被害が被らないように、命乞いのように懇願したり、(因果関係の認識として)謝る必要のない謝罪を口にす る。通常は、暴力概念は権力の発露として捉えることができるが(→「ソレルの暴力論」を参照)、以下の、ハンナ・アーレントの暴力概念は、そのように捉え ない特異的な解釈なので、注意が必要である。暴力の反対語は、ある意味空間(A)においては、非暴力であり、非暴力が含意するものは、誰でも想像がつくよ うに「平和」である。他方、「人を従属させる非破壊的な強制力」としての「権威」を暴力に対峙するもの、つまり反対語/反対概念とみなす立場もある。それ が、ハンナ・アーレントの暴力概念であり、この概念は、アーレントが影響を受けた夫ハインリッヒ・ブリュッヒャーとヴァルター・ベンヤミンの影響を受けて いるものと、私(池田)は考えている(→「暴力:その定義」)。
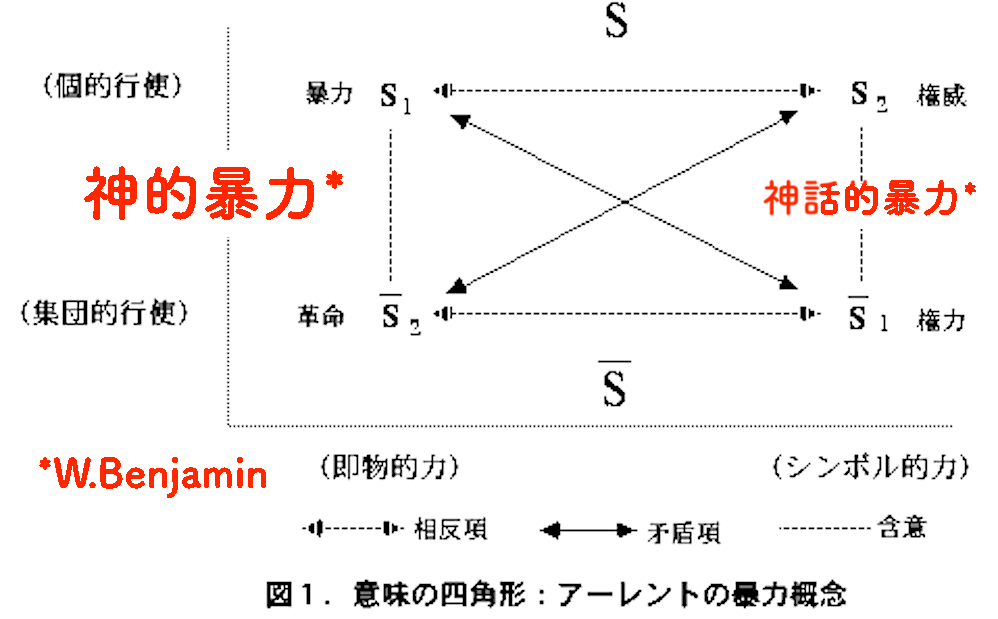
●カント『判断力批判』第一部にもとめる、政治的概念の鍛え方
「まず反省的判断力の働きに基づく趣味判断は、「関心」ないし「利害関心」と結びついていてはな らないということが重要です。カントの言い方では、あらゆる関心は趣 味判断を損ない、趣味判断か らその不偏不党性、つまり判断の公平性を奪う、ということになります。この見解は、この判断が存 在の認識に関わる理論的関心も、実践的行為に関わる道徳的な関心ももってはならない、という帰結 をもたらします。つまり、趣味判断は、知的欲求、感覚的・感性的欲求や道徳的意志などと関わる実 践的判断でもないのてす。したがって、趣味判断があらゆる目的とは分離された観想的な性格をもち、 こうした意味で趣味は自由であることになります。ここから、美感的判断力が自由な判 断でなければならないことが明らかでありましょう」牧野英二『カントを読む』Pp.258-259、岩波書店、2003年。
これらをまとめると次のようになる。1)反省的判断力は、関心や利害関心として結びつい
てはならない。
2)心や利害関心として結びついてはならない理由 は、趣味判断か らその不偏不党性、つまり判断の公平性を奪うからである。
3)この判断は認 識に関わる理論的関心も、実践的行為に関わる道徳的な関心ももってはならないからである。
4)趣味判断は、実践的な判断ではない。つまり、趣 味判断はあらゆる目的とは分離された観想的な性格をもち、
こうした意味で(のみ)趣味は自由である。
5)美感的判断力は自由な判断から生じる(アーレン
トはフランス滞在中にSSの将校に捕まって尋問を受けるが、その時、その将校がとても「ハンサム」であったことを述懐している)。
6)趣味の要求が、特定の共同体のなかで、排他的な
基準でなされることは「不道徳」をうむ——このような間主観的認識が「普遍性」をもつことは今後きちんと証明されなければならない。
7)美感的判断は、多様性をもつことが予測され、か
つ、その「優劣をめぐって」論争的性格をもつが、潜在的には「その価値判断が多元性を担保する限り」は、調停可能である。
8)調停可能という属性には、政治的判断も含まれよう。美感的判断における反省的判断力は、政治的判断における判断のプロセスにも「応用」可能となる(→
「カント『判断力批判』第一部を政治的判断力として読むハンナ・アーレントについて」)。
●マルチン・ハイデガー年譜
【年譜関係】マルチン・ハイデ ガー『存在と時間』ノート、よりコピペ
マルチン・ハイデガー年譜(ウィキペディア日本語による)
1889 9月26日 メスキルヒにてフリードリヒ・ハイデッガーとヨハンナの第一子として生まれる
1903 ハインリヒ・ズーゾ高等学校(Heinrich-Suso-Gymnasium)入学
1906 フライブルクのベルトホルト高等学校(Berthold Gymnasium)でアビトゥーアの準備
1907 ギムナジウム最終年にコンラート・グレーバー博士から、フランツ・ブレンターノの1862年の学位論文「アリストテレスにおける存在者の多様な
意義について」を贈られ、影響を受ける
1909 ティジスのイエズス会修練士修練期用新入生宿舎に登録、すぐに除籍。フライブルク大学神学部に冬学期から入学
1913 7月26日、指導教官はアルトゥール・シュナイダー教授を主査とし、副査ハインリヒ・リッケルトのもと学位論文『心
理学主義の判断論──論理学
への批判的・積極的寄与』を提出し、最優秀(summa cum laude)の評価
1919 プロテスタントに改宗。戦争緊急学期から1923年の夏学期までの時期、ハイデッガーはフッサールの助手として勤めつつ、フライブルク大学の教
壇に立つ。
1922 (
1923-28 )論文『アリストテレスの現象学的解釈──解釈学的状況の
提示』(ナトルプ報告)
解釈学的状況の提示
『ニコマコス倫理学』第6巻
『形而上学』第1巻の第1章と第2章
『自然学』第1巻から第5巻
(第2部について『形而上学』第7巻、第8巻、第9巻の解釈)
1927 エドムント・フッサールによって創刊された『哲学および現象学研究のための年報』の第8巻においてハイデガー『存在と時間』の初版を公刊。『現
象学の根本問題』(Die Grundprobleme der Phänomenologie)
1928 フッサールの後任としてフライブルク大学の教授に招聘され、就任
1929 4月、スイスのダボスで新カント派のエルンスト・カッシーラーとのダヴォス討論を行い、「神に存在論はない」「存在論を必要とするの
は有限者だけである」と語った[152][153]。この討論にはルドルフ・カルナップも参加しており、ハイデッガーに全てを物理学的用語で表現する可能
性について話すとハイデッガーは賛同したという(A parting of the ways : Carnap, Cassirer, and
Heidegger / Michael Friedman, Chicago : Open Court , 2000)。
1929 『カ
ントと形而上学の問題』(Kant und das Problem der
Metaphysik、1929年)『形而上学とは何か』("Was ist Metaphysik?"、1929年)
1932 ルドルフ・カルナップ(Rudolf Carnap,
1891-1970)は「言語の論理的分析による形而上学の克服」
[477]でハイデッガーの「形而上学とは何か」を批判し、形而上学は芸術の代用品にすぎず、形而上学者は「音楽的才能のない音楽家」でしかないと批判し
た
[478]。ハイデッガーは講義草稿でカルナップの哲学は「数学的科学性という見かけの下に伝統的な判断論を極端に平板化し、その根を失わせたもの」で、
「こうした種類の哲学が、ソ連の共産主義と内的にも外的にも関連しているのも、そしてアメリカにおいてその勝利を祝うことになるのも偶然ではない」と書い
ている。
1933 44歳
44歳。1月、ヒトラーが帝国宰相となる。
4月21日、ハイデッガーはフライブルク大学総長に選出。ナチス入党。
5月1日、22名の同僚とともにナチス党に入党。
5月27日「ド イツの大学の自己主張」学長就任演説(19330527)
夏学期「哲 学の根本問題(哲学の根本的問い)」講義。ハイデルベルク大学で「新しい帝国の大学」講演。
10月1日、フライブルク大学「指導者」に任命。
ハイデガー「ドイツの大学の自己主張(Die
Selbstbehauptung der Deutschen Universität)」 一九三三年五月二十七日 学長就任演説(引用元:http://makorin.blog.jp/archives/52004820.html) 一九三三年 第一版 フライブルク, 一九三四年 第二版 ブレスラウ 学 長職を引き受けることは、この高等教育機関を精神的指導する義務を意味する。教師と学生たちの支持は、ドイツの大学の本質に真に、そして共に根ざしている ことによってのみ目覚め、強くなる。しかし、この本質は、まず第一に、そして常に、指導者たち自身が、ドイツ国民の運命をその歴史の刻印に刻み込む、その 精神的な使命の厳しさによって導かれている場合に、真に明確さ、地位、権力を得る。 我々は、この精神的な使命を認識しているだろうか?知っているかどうかに関わらず、避けられない疑問が残る。この高等教育機関の教師と学生である我々は、 ドイツの大学の本質に真に、そして共に根ざしているのだろうか?この本質は、我々の現存在(Dasein)に真の影響力を持っているのだろうか?しかし、 それは、我々がこの本質を根本的に望んでいる場合にのみ可能だ。しかし、それを疑う者などいるだろうか?一般的に、大学の主な本質は「自治」にあるとみな されている。それは維持されるべきだ。しかし、この自治の要求が私たちに何を要求しているかを、私たちは十分に考えたことがあるだろうか? 自治とは、私たち自身が課題を設定し、その実現の方法と手段を自ら決定し、そこで私たちがなりたい自分になることを意味する。しかし、私たち、ドイツ国民 のための高等教育機関であるこの教師と学生たちの集団が、自分たちが何者なのかを本当に知っているだろうか?絶え間なく、そして厳しい自己反省なしに、そ れを知ることができるだろうか? 今日の大学の状況を知っていることも、その過去の歴史を知っていることも、その本質について十分な知識があることの保証にはならない。ただし、その本質を将来に向けて明確かつ厳格に定義し、そのような自己制限の中でそれを望み、その意志の中で自らを主張する場合を除く。 自治は、自己反省に基づいてのみ成立する。しかし、自己反省は、ドイツの大学が自己を主張する力によってのみ行われる。我々はそれを実行するのか、そしてどのように実行するのか? ドイツの大学が自らを主張することは、その本質に対する、元来の共通の意志である。ドイツの大学は、科学から、そして科学を通じて、ドイツ国民の運命の指 導者と守護者を教育し、育成する高等教育機関であると我々は考えている。ドイツの大学の本質に対する意志は、科学に対する意志、すなわち、その国家におい て自らを認識する国民としてのドイツ国民の、歴史的・精神的使命に対する意志である。科学とドイツの運命は、その本質的な意志において、権力を行使しなけ ればならない。そして、それは、教師と生徒が、科学をその最も内なる必要性にさらし、また、ドイツの運命が極度の苦難に直面しているときに、それに耐える ときにのみ実現する。 しかし、「新しい科学の概念」を論じるだけで、今日の科学の独立性や前提条件のないことを否定している限り、科学の本質をその最も内なる必要性において体 験することはできない。この単に否定的な、過去数十年間をほとんど振り返らない行動は、科学の本質に対する真摯な努力のふりをしているにすぎない。 科学の本質を理解したいならば、まず決定的な問題、すなわち、科学は今後も我々にとって存在すべきものなのか、それとも迅速に終焉を迎えるべきものなの か、という問題に直面しなければならない。科学が存在するべきであるということは、決して絶対的な必要条件ではない。しかし、科学が存在すべきであり、我 々のために、そして我々によって存在すべきであるならば、どのような条件の下で、科学は真に存在しうるのか? それは、私たちが精神的・歴史的な現存在(Dasein)の始まりに再び立ち返ったときだけである。その始まりは、ギリシャ哲学の誕生である。そこでは、 西洋人は、その言語の力によって、初めて、存在全体に対して立ち上がり、それを存在として問い、理解する。すべての科学は、それを認識し、望んでいるかど うかに関わらず、哲学である。 すべての科学は、哲学のその始まりに固執している。そこから、その存在の力を引き出しているのだ。ただし、その始まりにまだ対応できる場合に限る。 ここでは、ギリシャの科学の本質的な特徴である 2 つの特性を、現存在(Dasein)に取り戻そう。 ギリシャ人たちは、プロメテウスが最初の哲学者だったという古い伝説を信じていた。アイスキュロスは、このプロメテウスに、知識の本質を表現する次の言葉を語らせている。 tegnh d`anagkhj asqenestera makrw (Prom. 514 ed. Wil.) 「しかし、知識は必然性よりもはるかに無力である。」つまり、物事に関するあらゆる知識は、まず運命の圧倒的な力に翻弄され、その前に失敗するということだ。 だからこそ、知識は、その最高の反抗力を発揮しなければならない。そうして初めて、存在の隠された力の全容が現れ、真に失敗するのだ。そうして初めて、存 在はその測り知れない不変性の中で開かれ、知識にその真実を与えるのだ。この、知識の創造的な無力についての格言は、純粋に自己に立脚し、それゆえ自己を 忘れた知識、すなわち「理論的」態度として解釈される知識に当てはまるものと思われる。しかし、ギリシャ人にとってケウリアとは何だろうか?それは、物事 の豊かさとその要求にのみ結びついた純粋な考察であると言われる。この考察的な行動は、ギリシャ人を引用して、それ自体のためになされるべきである。しか し、この主張は間違っている。なぜなら、第一に、「理論」はそれ自体のために生じるのではなく、存在そのものに近づき、その苦難の中に留まるという情熱に よってのみ生じるものだからだ。第二に、ギリシャ人は、この観察的な問いかけを、人間にとっての最高の人間活動、すなわち「energeia(活動)」の 一形態、いや、最高形態として理解し、実行するために奮闘しているのだ。彼らの意図は、実践を理論に合わせることでなく、逆に、理論そのものを真の実践の 最高の実現として理解することだった。ギリシャ人にとって、科学は「文化遺産」ではなく、国民と国家の現存在(Dasein)そのものを決定づける中核 だった。彼らにとって、科学は単に無意識を認識する手段ではなく、現存在(Dasein)を鋭く保ち、それを包括する力であった。 科学とは、絶えず隠れている存在全体の中で、疑問を持ち続けることである。この行動的な忍耐は、運命の前では無力であることを認識している。 これが科学の初期の本質だ。しかし、この始まりはすでに2500年も前のことではないのか?人間の活動の進歩は、科学も変化させたのではないか?確かにそ うだ!その後登場したキリスト教神学による世界解釈、そしてさらに後の近代における数学的・技術的思考は、科学をその始まりから時間的にも内容的にも遠ざ けた。しかし、それによってその始まり自体が克服されたり、あるいは無にされたりしたわけではない。なぜなら、もし、ギリシャの科学の起源が偉大なもので あるならば、その偉大さの始まりは、その偉大さの最大のものであるからだ。その偉大さの始まりがまだ存在していなければ、今日のあらゆる成果や「国際機 関」にもかかわらず、科学の本質は、その空虚化や消耗さえも免れることはできなかっただろう。その始まりは今も続いている。それは、はるか昔に過ぎ去った 過去ではなく、私たちの前にある。その始まりは、これから起こるすべてのもの、そして私たちをも超えた、最も偉大なものとして、すでに過ぎ去っている。そ の始まりは私たちの未来に侵入し、その偉大さを再び取り戻すという、遠い運命としてそこに立っている。 この遠い運命に、始まりの偉大さを取り戻すために断固として従うときだけ、科学は現存在(Dasein)の最も内なる必要性となる。そうでなければ、科学は、私たちが偶然出くわすもの、あるいは、知識の単なる進歩を促進するための、危険のない活動の安らぎにすぎない。 しかし、私たちが始まりの遠い決定に従うならば、科学は私たちの精神的・民族的現存在(Dasein)の基本的な出来事にならなければならない。 そして、私たちの現存在(Dasein)が大きな変化に直面しているならば、情熱的に神を追い求めた最後のドイツ人哲学者、フリードリヒ・ニーチェが言っ たことが真実であるならば、 「神は死んだ」という彼の言葉が真実であるならば、今日の存在の中で人間が見捨てられたというこの状況を真剣に受け止めなければならないならば、科学はど うなるのか? そうすれば、ギリシャ人が当初、存在に対して抱いていた賞賛に満ちた忍耐は、隠された不確かなもの、すなわち疑問に満ちたものに対する、まったく無防備な 曝露へと変化する。疑問はもはや、知識としての答えへの克服可能な前段階ではなく、疑問そのものが知識の最高の形態となる。疑問は、あらゆるものの本質を 開示する、その固有の力を展開する。疑問は、避けられないものに対する視点を極限まで単純化することを強いる。 そのような疑問は、科学を個別の分野に封じ込めた状態を打ち破り、境界も目標もない分散状態から、孤立した分野や隅々に散らばった状態から、科学を再び、 人間と歴史の現存在(Dasein)における、世界を形成するあらゆる力の豊饒と恩恵、すなわち、自然、歴史、言語、民族、慣習、国家、 詩、思考、信仰、病気、狂気、死、法律、経済、技術など。 我々が、存在の全体としての不確実性の中で、疑問を持ち、覆い隠さない姿勢を貫くという意味で、科学の本質を理解したいと思うならば、この本質的な意志 は、我々の民族に、最も内面的かつ最も外的な危険、すなわち、真に精神的な世界をもたらす。なぜなら、「精神」とは、空虚な鋭敏さでも、無責任な機知の遊 びでも、知性による無限の分析でも、ましてや世界的な理性でもなく、本来、存在の本質に対する調和のとれた、知識に基づく決意であるからだ。そして、民族 の精神世界は、文化の上部構造でも、有用な知識や価値観の武器庫でもなく、その民族の地球と血に根ざした力を、その現存在(Dasein)の最も内なる興 奮と最も広範な動揺の力として、最も深く保存する力である。精神世界だけが、その民族の偉大さを保証する。なぜなら、それは、偉大さを求める意志と衰退を 容認する意志との絶え間ない決断を、私たちの民族が未来の歴史に向けて踏み出した行進の歩調とすることを強いるからだ。 この科学の本質を求めるならば、大学の教師陣は、絶え間ない世界の不確実性という危険の最前線に、真に前進しなければならない。そこで耐えること、すなわ ち、あらゆるものの苦難に本質的に近いその場所で、共通の疑問と共同の意見が生まれるならば、教師陣は強力な指導力を持つようになる。なぜなら、指導にお いて決定的なのは、単に先頭に立つことではなく、独断や支配欲からではなく、最も深い使命と最も広範な義務によって、単独で行動できる力である。そのよう な力は、本質に結びつき、最善の人材を選抜し、新たな勇気を持つ者たちの真の支持を呼び起こす。しかし、我々は従順な人々をまず目覚めさせる必要はない。 ドイツの学生たちは前進している。そして彼らが求めているのは、彼ら自身の運命を、確立された、知識に基づく真実へと高め、解釈力ある言葉と行動の明快さ の中に位置づけることができる指導者たちである。 ドイツの学生たちが、ドイツの運命が極度の苦境にある中でそれに立ち向かおうとする決意から、大学の本質に対する意志が生まれている。この意志は、ドイツ の学生たちが新しい学生法によって自らをその本質に基づく法律の下に置き、それによってまずその本質を限定する限り、真の意志である。自らに法律を与える ことは、最高の自由である。よく歌われる「学問の自由」は、ドイツの大学から排除される。この自由は、否定的なものだけだったため、偽りの自由だった。そ れは主に、無頓着さ、意図や傾向の恣意性、行動や行動の自由を意味していた。ドイツの学生の自由という概念は、今、その真実性を取り戻しつつある。この自 由から、今後、ドイツの学生団体の結束と奉仕が展開されるだろう。 最初の絆は、国民共同体への絆だ。それは、あらゆる階層や国民の一員たちの努力、願望、能力に、協力し、行動して参加することを義務づける。この絆は、今後、労働奉仕によって確固たるものとなり、学生現存在(Dasein)に根付くことになる。 二つ目の絆は、他の民族の中で、国家の名誉と運命に対する絆だ。これは、知識と能力によって確保され、規律によって鍛えられた、最後まで尽くす覚悟を求める。この絆は、今後、兵役として、現存在(Dasein)全体を取り囲み、浸透していく。 学生たちの3つ目の絆は、ドイツ国民の精神的使命に対するものだ。この国民は、その歴史を、人間現存在のあらゆる世界形成の力の優位性を明らかにする場と して位置づけ、その精神的世界を常に新たに勝ち取ろうと努力することで、自らの運命に影響を与えている。このように、自らの現存在の究極的な疑問にさらさ れているこの国民は、精神的な国民でありたいと願っている。この民族は、その指導者や守護者たちに、最高、最広、そして最も豊かな知識の、最も厳しい明快 さを自らに、そして自らのために要求する。早い時期に成人期へと踏み出し、その意志を国家の将来の運命に広げる学生たちは、この知識に奉仕することを根本 的に自らに課している。彼らにとって、知識への奉仕は、もはや「高貴な」職業への単調で迅速な訓練であってはならない。政治家や教師、医師や裁判官、牧師 や建築家たちは、国民と国家の現存在(Dasein)を導き、その基本的な側面において、人間存在の世界を形成する力を守り、鋭敏に保つ。そのため、これ らの職業と、それらへの教育は、知識への奉仕に委ねられている。知識は職業に奉仕するものではなく、その逆である。職業は、国民が自らの現存在全体につい て持つ、最高かつ本質的な知識を生み出し、管理する。しかし、この知識は、存在や価値そのものを安穏に認識することではなく、存在するものの圧倒的な力の 中で、現存在が直面する最も深刻な脅威である。存在そのものの疑わしさは、国民に労働と闘争を強いるものであり、職業が属する国家に国民を強制的に組み入 れるものである。 国民による、精神的使命における国家の運命への3つの結びつきは、ドイツの本質と同じ起源を持つ。そこから生じる3つの奉仕、すなわち労働奉仕、兵役奉仕、知識奉仕は、同等に必要であり、同等の地位にある。 国民に関する実践的な知識、国家の運命に関する準備的な知識は、精神的使命に関する知識と一体となって、初めて、我々が実現すべき科学の本質と完全性を生み出す。それは、我々が精神的・歴史的現存在の始まりという遠い運命に身を委ねることを前提としている。 この科学は、ドイツの大学の本質が、科学から、そして科学を通じて、ドイツ国民の運命の指導者と守護者を教育し、育成する高等教育機関として定義される場合に意味されるものである。 この本来の科学の概念は、「客観性」だけでなく、まず第一に、民族の歴史的・精神的世界のなかで、本質的で単純な疑問を投げかけることを義務づける。そう、そこから初めて、客観性は真に確立され、その性質と限界を見出すことができるのだ。 この意味での科学は、ドイツの大学という組織を形作る力にならなければならない。そこには二つの意味がある。教師と学生は、それぞれの方法で科学の概念に 魅了され、その魅力に留まらなければならない。同時に、この科学の概念は、教師と学生が共同で科学的な活動を行う基本的な形態、すなわち学部や学科に、変 革をもたらす形で介入しなければならない。 学部は、その科学の本質に根ざした精神的立法の能力を発展させ、現存在(Dasein)を圧迫する力を、民族の精神的な世界へと変容させることによって、初めて学部となる。 学科は、最初からこの精神的立法の領域に入り、それによって学科の境界を取り払い、古臭くて不自然な外部の職業訓練を克服して初めて、学科としての役割を果たす。 学部や専門分野が、その科学の本質的で単純な問題に取り組み始めた瞬間、教師と生徒たちは、国民国家の現存在(Dasein)が抱える究極の必要性と苦難にすでに包まれている。 しかし、科学の本質的な本質を形作るには、厳格さ、責任、そして卓越した忍耐力といった、それとは比較にならないほどの要素が必要だ。それに対して、既成の手法を忠実に守ることや、熱心にそれを変更することは、ほとんど重要ではない。 しかし、ギリシャ人が「知識とは何か」という疑問さえも、正しい基盤と確実な軌道に乗せるのに 3 世紀を要したならば、ドイツ大学の真髄の解明と発展が、今学期や来学期に達成されるとは、なおさら考えられない。 しかし、科学の本質から、ドイツの大学は、労働、防衛、知識という 3 つの奉仕が、もともと形成力として融合した場合にのみ、その姿と力を発揮するということだけは確かだ。つまり、 教師陣の本質的な意志は、科学の本質に関する知識の単純さと広範さに目覚め、強くなければならない。生徒たちの本質的な意志は、知識の最高の明快さと規律 に自らを駆り立て、国民と国家に関する共同研究を、科学の本質に要求し、決定的に組み込むことで形作らなければならない。両者の意志は、互いに闘わなけれ ばならない。意志と思考の能力、心の力、身体の能力はすべて、闘争によって開花し、闘争によって高められ、闘争として維持されなければならない。 我々は、問う者たちの知識に基づく闘争を選び、カール・フォン・クラウゼヴィッツの「偶然の救いを軽率に期待することは放棄する」という言葉を信条とする。 しかし、教師と学生たちの闘争共同体は、教師陣と学生たちが他の国民よりも質素で、厳格で、必要のない現存在(Dasein)を送っている場合にのみ、ド イツの大学を精神的な立法の場へと変貌させ、その大学を、国民とその国家に最高の奉仕を行うための最も厳格な集合体の中心とすることができる。すべての指 導者は、追随者たちに独自の力を認める必要がある。しかし、従うことには抵抗が伴う。指導と従うことにおけるこの本質的な対立は、曖昧にしたり、ましてや 消し去ったりしてはならない。 闘争だけが対立を明らかにし、教師と生徒全体の組織に、自己主張を制限する基本的な気風を植え付け、真の自治に向けた断固とした自己認識を可能にするのだ。 ドイツの大学の本質を求めるのか、求めないのか?自己認識と自己主張を、表面的な努力ではなく、根本的に、そしてどこまで追求するかは、我々次第である。あるいは、最善の意図をもって、古い制度を変更し、新しい制度を追加するだけなのか。誰もそれを妨げる者はいない。 しかし、西洋の精神的力が失われ、西洋が崩壊し、陳腐な偽りの文化が崩壊し、すべての力が混乱に陥り、狂気に窒息するならば、誰も我々にそれを望むかどうか尋ねることはないだろう。 そのようなことが起こるかどうかは、歴史的・精神的な民族として、私たちがまだ、そして再び自分自身を望んでいるかどうか、あるいはもはや自分自身を望ん でいないかどうかによってのみ決まる。一人ひとりが、この決定を避けようとした場合でも、そしてまさにその場合にこそ、その決定に関与する。 しかし、私たちは、私たちの民族が歴史的使命を果たすことを望んでいる。 私たちは、私たち自身を望んでいる。なぜなら、私たちの上にすでに手を伸ばしている、民族の若く、そして最も若い力が、すでにそれを決定しているからだ。 しかし、この出発の素晴らしさと偉大さは、古代ギリシャの知恵が「 ta ... megala panta episfalh ... 」という言葉で表現した、深く広大な思慮深さを私たちが心に抱いて初めて、完全に理解できるものである。 (プラトン、ポリティア 497 d, 9) |
Martin Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen
Universität. Die Übernahme des Rektorats ist die Verpflichtung zur geistigen Führung dieser hohen Schule. Die Gefolgschaft der Lehrer und Schüler erwacht und erstarkt allein aus der wahrhaften und gemeinsamen Verwurzelung im Wesen der deutschen Universität. Dieses Wesen aber kommt ernst zu Klarheit, Rang und Macht, wenn zuvörderst und jederzeit die Führer selbst Geführte sind— geführt von der Unerbittlichkeit jenes geistigen Auftrags, der das Schicksal des deutschen Volkes in das Gepräge seiner Geschichte zwingt. Wissen wir um diesen geistigen Auftrag? Ob je oder nein, unabwendbar bleibt die Frage: sind wir, Lehrerschaft und Schülerschaft dieser hohen Schule, in das Wesen der deutschen Universität wahrhaft und gemeinsam verwurzelt? Hat dieses Wesen echte Prägekraft für unser Dasein? Doch nur dann, wenn wir dieses Wesen von Grund aus wollen. Wer möchte aber daran zweifeln? Gemeinhin sieht man den vorwaltenden Wesenscharakter der Universität in ihrer »Selbstverwaltung«; die soll erhalten bleiben. Allein— haben wir es auch ganz bedacht, was dieser Anspruch auf Selbstverwaltung von uns fordert? Selbstverwaltung heißt doch: uns selbst die Aufgabe setzen und selbst Weg und Weise ihrer Verwirklichung bestimmen, um darin selbst zu sein, was wir sein wollen. Aber wissen wir denn, wer wir selbst sind, diese Körperschaft von Lehrern und Schülern der höchsten Schule des deutschen Volkes? Können wir das überhaupt wissen, ohne die ständigste und härteste Selbstbesinnung? Weder die Kenntnis der heutigen Zustände der Universität, noch auch die Bekanntschaft mit ihrer früheren Geschichte verbürgen schon ein hinreichendes Wissen von ihrem Wesen— es sei denn, daß wir zuvor in Klarheit und Härte dieses Wesen für die Zukunft umgrenzen, in solcher Selbstbegrenzung es wollen, und daß wir in solchem Wollen uns selbst behaupten. Selbstverwaltung besteht nur auf dem Grunde der Selbstbesinnung. Selbstbesinnung aber geschieht nur in der Kraft der Selbstbehauptung der deutschen Universität. Werden wir sie vollziehen und wie? Die Selbstbehauptung der deutschen Universität ist der ursprüngliche, gemeinsame Wille zu ihrem Wesen. Die deutsche Universität gilt uns als die hohe Schule, die aus Wissenschaft und durch Wissenschaft die Führer und Hüter des Schicksals des deutschen Volkes in die Erziehung und Zucht nimmt. Der Wille zum Wesen der deutschen Universität ist der Wille zur Wissenschaft als Wille zum geschichtlichen geistigen Auftrag des deutschen Volkes als eines in seinem Staat sich selbst wissenden Volkes. Wissenschaft und deutsches Schicksal müssen zumal im Wesenswillen zur Macht kommen. Und sie werden es dann und nur dann, wenn wir— Lehrerschaft und Schülerschaft— einmal die Wissenschaft ihrer innersten Notwendigkeit aussetzen und wenn wir zum anderen dem deutschen Schicksal in seiner äußersten Not standhalten.— Das Wesen der Wissenschaft erfahren wir allerdings nicht in seiner innersten Notwendigkeit, solange wir nur— vom »neuen Wissenschaftsbegriff« redend— einer allzu heutigen Wissenschaft die Eigenständigkeit und Voraussetzungslosigkeit bestreiten. Dieses lediglich verneinende und kaum über die letzten Jahrzehnte zurückblickende Tun wird nachgerade zum Schein einer wahrhaften Bemühung um das Wesen der Wissenschaft. Wollen wir das Wesen der Wissenschaft fassen, dann müssen wir erst der Entscheidungsfrage unter die Augen gehen: soll Wissenschaft fernerhin für uns noch sein, oder sollen wir sie einem raschen Ende zutreiben lassen? Daß Wissenschaft überhaupt sein soll, ist niemals unbedingt notwendig. Soll Wissenschaft aber sein und soll sie für uns und durch uns sein, unter welcher Bedingung kann sie dann wahrhaft bestehen? Nur dann, wenn wir uns wieder unter die Macht des Anfangs unseres geistig-geschichtlichen Daseins stellen. Dieser Anfang ist der Aufbruch der griechischen Philosophie. Darin steht der abendländische Mensch aus einem Volkstum kraft seiner Sprache erstmals auf gegen das Seiende im Ganzen und befragt und begreift es als das Seiende, das es ist. Alle Wissenschaft ist Philosophie, mag sie es wissen und wollen— oder nicht. Alle Wissenschaft bleibt jenem Anfang der Philosophie verhaftet. Aus ihm schöpft sie die Kraft ihres Wesens, gesetzt, daß sie diesem Anfang überhaupt noch gewachsen bleibt. Wir wollen hier zwei auszeichnende Eigenschaften der ursprünglichen griechischen Wesens der Wissenschaft unserem Dasein zurückgewinnen. Bei den Griechen ging ein alter Bericht um, Prometheus sei der erste Philosoph gewesen. Diesen Prometheus läßt Aischylos einen Spruch sagen, der das Wesen des Wissens ausspricht: tegnh d`anagkhj asqenestera makrw (Prom. 514 ed. Wil.) »Wissen aber ist weit unkräftiger denn Notwendigkeit. « Das will sagen: jedes Wissen um die Dinge bleibt zuvor ausgeliefert der Übermacht des Schicksals und versagt vor ihr. Eben deshalb muß das Wissen seinen höchsten Trotz entfalten, für den erst die ganze Macht der Verborgenheit des Seienden aufsteht, um wirklich zu versagen. So öffnet sich gerade das Seiende in seiner unergründbaren Unabänderlichkeit und leiht dem Wissen seine Wahrheit. Dieser Spruch von der schöpferischen Unkraft des Wissens für ein rein auf sich selbst gestelltes und dabei selbstvergessenes Wissen finden möchte, das man uns als die »theoretische« Haltung deutet.— Aber was ist die qewria für den Griechen? Man sagt: die reine Betrachtung, die nur der Sache in ihrer Fülle und Forderung verbunden bleibt. Dieses betrachtende Verhalten soll unter Berufung auf die Griechen um seiner selbst willen geschehen. Aber diese Berufung hat unrecht. Denn einmal geschieht die «Theorie» nicht um ihrer selbst willen, sondern einzig in der Leidenschaft, dem Seienden als solchem nahe und unter seiner Bedrängnis zu bleiben. Zum andern aber kämpfen die Griechen gerade darum, dieses betrachtende Fragen als eine, ja als die höchste Weise der energeia, des »am-Werke-Seins«, des Menschen zu begreifen und zu vollziehen. Nicht stand ihr Sinn danach, die Praxis der Theorie anzugleichen, sondern umgekehrt, die Theorie selbst als die höchste Verwirklichung echter Praxis zu verstehen. Den Griechen ist die Wissenschaft nicht ein »Kulturgut«, sondern die innerst bestimmende Mitte des ganzen volklich-staatlichen Daseins. Wissenschaft ist ihnen auch nicht das bloße Mittel der Bewußtmachung des Unbewußten, sondern die das ganze Dasein scharfhaltende und es umgreifende Macht. Wissenschaft ist das fragende Standhalten inmitten des sich ständig verbergenden Seienden im Ganzen. Dieses handelnde Ausharren weiß dabei um seine Unkraft vor dem Schicksal. Das ist das anfängliche Wesen der Wissenschaft. Aber liegt dieser Anfang nicht schon zweieinhalb Jahrtausende zurück? Hat nicht der Fortschritt menschlichen Tuns auch die Wissenschaft verändert? Gewiß! Die nachkommende christlich-theologische Weltdeutung, ebenso wie das spätere mathematisch-technische Denken der Neuzeit haben die Wissenschaft zeitlich und sachlich von ihrem Anfang entfernt. Aber damit ist der Anfang selbst keineswegs überwunden oder gar zunichte gemacht. Denn gesetzt, die ursprüngliche griechische Wissenschaft ist etwas Großes, dann bleibt der Anfang dieses Großen sein Größtes. Das Wesen der Wissenschaft könnte nicht einmal entleert und vernutzt werden, wie es trotz aller Ergebnisse und »internationaler Organisationen« heute ist, wenn die Größe des Anfangs nicht noch bestünde. Der Anfang ist noch. Er liegt nicht hinter uns als das längst Gewesene, sondern er steht vor uns. Der Anfang ist als das Größte im voraus über alles Kommende und so auch über uns schon hinweggegangen. Der Anfang ist in unsere Zukunft eingefallen, er steht dort als die ferne Verfügung über uns, seine Größe wieder einzuholen. Nur wenn wir dieser fernen Verfügung entschlossen uns fügen, um die Größe des Anfangs zurückzugewinnen, nur dann wird uns die Wissenschaft zur innersten Notwendigkeit des Daseins. Andernfalls bleibt sie ein Zufall, in den wir geraten, oder das beruhigte Behagen einer gefahrlosen Beschäftigung zur Förderung eines bloßen Fortschritts von Kenntnissen. Fügen wir uns aber der fernen Verfügung des Anfangs, dann muß die Wissenschaft zum Grundgeschehnis unseres geistig-volklichen Daseins werden. Und wenn gar unser eigenstens Dasein selbst vor einer groß en Wandlung steht, wenn es wahr ist, was der leidenschaftlich den Gott suchende letzte deutsche Philosoph, Friedrich Nietzsche, sagte: »Gott ist tot«— , wenn wir Ernst machen müssen mit dieser Verlassenheit des heutigen Menschen inmitten des Seienden, wie steht es dann mit der Wissenschaft? Dann wandelt sich das anfänglich bewundernde Ausharren der Greichen vor dem Seienden zum völlig ungedeckten Ausgesetztsein in das Verborgene und Ungewisse, d.i. Fragwürdige. Das Fragen ist dann nicht mehr nur die überwindbare Vorstufe zur Antwort als dem Wissen, sondern das Fragen wird selbst die höchste Gestalt des Wissens. Das Fragen entfaltet dann seine eigenste Kraft der Aufschließung des Wesentlichen aller Dinge. Das Fragen zwingt dann zur äußersten Vereinfachung des Blickes auf das Unumgängliche. Solches Fragen zerbricht die Verkapselung der Wissenschaften in gesonderte Fächer, holt sie zurück aus der ufer- und ziellosen Zerstreuung in vereinzelte Felder und Ecken und setzt die Wissenschaft wieder unmittelbar aus der Fruchtbarkeit und dem Segen aller weltbildenden Mächte des menschlich-geschichtlichen Daseins, als da sind: Natur, Geschichte, Sprache; Volk, Sitte, Staat; Dichten, Denken, Glauben; Krankheit, Wahnsinn, Tod; Recht, Wirtschaft, Technik. Wollen wir das Wesen der Wissenschaft im Sinne des fragenden, ungedeckten Standhaltens inmitten der Ungewißheit des Seienden in Ganzen, dann schafft dieser Wesenswille unserem Volke seine Welt der innersten und äußersten Gefahr, d.h. seine wahrhaft geistige Welt. Denn »Geist« ist weder leerer Scharfsinn, noch das unverbindliche Spiel des Witzes, noch das uferlose Treiben verstandesmäßiger Zergliederung, noch gar die Weltvernunft, sondern Geist ist ursprünglich gestimmte, wissende Entschlossenheit zum Wesen des Seins. Und die geistige Welt eines Volkes ist nicht der Überbau einer Kultur, sowenig wie das Zeughaus für verwendbare Kenntnisse und Werte, sondern sie ist die Macht der tiefsten Bewahrung seiner erd- und bluthaften Kräfte als Macht der innersten Erregung und weitesten Erschütterung seines Daseins. Eine geistige Welt allein verbürgt dem Volke die Größe. Denn sie zwingt dazu, daß die ständige Entscheidung zwischen dem Willen zur Größe und dem Gewährenlassen des Verfalls das Schrittgesetz wird für den Marsch, den unser Volk in seine künftige Geschichte angetreten hat. Wollen wir dieses Wesen der Wissenschaft, dann muß die Lehrerschaft der Universität wirklich vorrücken in den äußersten Posten der Gefahr der ständigen Weltungewißheit. Hält sie dort stand, d.h. erwächst ihr von dort— in der wesentlichen Nähe der Bedrängnis aller Dinge— das gemeinsame Fragen und gemeinschaftlich gestimmte Sagen, dann wird sie stark zur Führerschaft. Denn das Entscheidende im Führen ist nicht das bloße Vorangehen, sondern die Kraft zum Alleingehenkönnen, nicht aus Eigensinn und Herrschgelüste, sondern kraft einer tiefsten Bestimmung und weitesten Verpflichtung. Solche Kraft bindet an das Wesentliche, schafft die Auslese der Besten und weckt die echte Gefolgschaft derer, die neuen Mutes sind. Aber wir brauchen die Gefolgschaft nicht erst zu wecken. Die deutsche Studentenschaft ist auf dem Marsch. Und wen sie sucht, das sind jene Führer, durch die sie ihre eigene Bestimmung zur gegründeten, wissenden Wahrheit erheben und in die Klarheit des deutend-wirkenden Wortes und Werkes stellen will. Aus der Entschlossenheit der deutschen Studentenschaft, dem deutschen Schicksal in seiner äußersten Not standzuhalten, kommt ein Wille zum Wesen der Universität. Dieser Wille ist ein wahrer Wille, sofern die deutsche Studentenschaft durch das neue Studentenrecht sich selbst unter das Gesetz ihres Wesens stellt und damit dieses Wesen allererst umgrenzt. Sich selbst das Gesetz geben, ist höchste Freiheit. Die vielbesungene »akademische Freiheit« wird aus der deutschen Universität verstoßen; denn diese Freiheit war unecht, weil nur verneinend. Sie bedeutete vorwiegend Unbekümmertheit, Beliebigkeit der Absichten und Neigungen, Ungebundenheit im Tun und Lassen. Der Begriff der Freiheit des deutschen Studenten wird jetzt zu seiner Wahrheit zurückgebracht. Aus ihr entfalten sich künftig Bindung und Dienst der deutschen Studentenschaft. Die erste Bindung ist die in die Volksgemeinschaft. Sie verpflichtet zum mittragenden und mithandelnden Teilhaben am Mühen, Trachten und Können aller Stände und Glieder des Volkes. Diese Bindung wird fortan festgemacht und in das studentische Dasein eingewurzelt durch den Arbeitsdienst. Die zweite Bindung ist die an die Ehre und das Geschick der Nation inmitten der anderen Völker. Sie verlangt die in Wissen und Können gesicherte und durch Zucht gestraffte Bereitschaft zum Einsatz bis ins Letzte. Diese Bindung umgreift und durchdringt künftig das ganze studentische Dasein als Wehrdienst. Die dritte Bindung der Studentenschaft ist die an den geistigen Auftrag des deutschen Volkes. Dies Volk wirkt an seinem Schicksal, indem es seine Geschichte in die Offenbarkeit der Übermacht aller weltbildenden Mächte des menschlichen Daseins hineinstellt und sich seine geistige Welt immer neu erkämpft. So ausgesetzt in die äußerste Fragwürdigkeit des eigenen Daseins, will dies Volk ein geistiges Volk sein. Es fordert von sich und für sich in seinem Führern und Hütern die härteste Klarheit des höchsten, weitesten und reichsten Wissens. Eine studentische Jugend, die früh sich in die Mannheit hineinwagt und ihr Wollen über das künftige Geschick der Nation ausspannt, zwingt sich von Grund aus zum Dienst an diesem Wissen. Ihr wird der Wissensdienst nicht mehr sein dürfen die dumpfe und schnelle Abrichtung zu einem »vornehmen« Beruf. Weil der Staatsmann und Lehrer, der Arzt und der Richter, der Pfarrer und der Baumeister das volklich-staatliche Dasein führen und in seinen Grundbezügen zu den weltbildenden Mächten des menschlichen Seins bewachen und scharf halten, deshalb sind diese Berufe und die Erziehung zu ihnen dem Wissensdienst überantwortet. Das Wissen steht nicht im Dienste der Berufe, sondern umgekehrt: die Berufe erwirken und verwalten jenes höchste und wesentliche Wissen des Volkes um sein ganzes Dasein. Aber dieses Wissen ist uns nicht die beruhigte Kenntnisnahme von Wesenheiten und Werten an sich, sondern die schärfste Gefährdung des Daseins inmitten der Übermacht des Seienden. Die Fragwürdigkeit des Seins überhaupt zwingt dem Volk Arbeit und Kampf ab und zwingt es in seinen Staat, dem die Berufe zugehören. Die drei Bindungen— durch das Volk an das Geschick des Staates im geistigen Auftrag— sind dem deutschen Wesen gleichursprünglich. Die drei von da entspringenden Dienste— Arbeitsdienst, Wehrdienst und Wissensdienst— sind gleich notwendig und gleichen Ranges. Das mithandelnde Wissen um das Volk, das sich bereithaltende Wissen um das Geschick des Staates schaffen in eins mit dem Wissen um den geistigen Auftrag erst das ursprüngliche und volle Wesen der Wissenschaft, deren Verwirklichung uns aufgegeben ist— gesetzt, daß wir uns in die ferne Verfügung des Anfangs unseres geistig-geschichtlichen Daseins fügen. Diese Wissenschaft ist gemeint, wenn das Wesen der deutschen Universität umgrenzt wird als die hohe Schule, die aus Wissenschaft und durch Wissenschaft die Führer und Hüter des Schicksals des deutschen Volkes ind die Erziehung und Zucht nimmt. Dieser ursprüngliche Begriff der Wissenschaft verpflichtet nicht nur zur »Sachlichkeit«, sondern zuerst zur Wesentlichkeit und Einfachheit des Fragens inmitten der geschichtlich-geistigen Welt des Volkes. Ja— hieraus kann sich erst Sachlichkeit wahrhaft begründen, d.h. ihre Art und Grenze finden. Die Wissenschaft nach diesem Sinne muß zur gestaltenden Macht der Körperschaft der deutschen Universität werden. Darin liegt ein Doppeltes: Lehrerschaft und Schülerschaft müssen einmal je in ihrer Weise vom Begriff der Wissenschaft ergriffen werden und ergriffen bleiben. Zugleich muß aber dieser Begriff der Wissenschaft umgestaltend eingreifen in die Grundformen, innerhalb derer die Lehrer und Schüler jeweils in Gemeinschaft wissenschaftlich handeln: in die Fakultäten und in die Fachschaften. Die Fakultät ist nur Fakultät, wenn sie sich zu einem im Wesen ihrer Wissenschaft verwurzelten Vermögen geistiger Gesetzgebung entfaltet, um die sie bedrängenden Mächte des Daseins in die eine geistige Welt des Volkes hineinzugestalten. Die Fachschaft ist nur Fachschaft, wenn sie sich von vornherein in den Bereich dieser geistigen Gesetzgebung stellt und damit die Schranken des Faches zu Fall bringt und das Muffige und Unechte äußerlicher Berufsabrichtung überwindet. In dem Augenblick, wo die Fakultäten und Fachschaften die wesentlichen und einfachen Fragen ihrer Wissenschaft in Gang bringen, sind Lehrer und Schüler auch schon von denselben letzten Notwendigkeiten und Bedrängnissen des volklichstaatlichen Daseins umgriffen. Die Ausgestaltung jedoch des ursprünglichen Wesens der Wissenschaft verlangt ein solches Ausmaß an Strenge, Verantwortung und überlegener Geduld, daß dem gegenüber etwa die gewissenhafte Befolgung oder die eifrige Abänderung fertiger Verfahrungsweisen kaum ins Gewicht fallen. Wenn aber die Griechen drei Jahrhunderte brauchten, um auch nur die Frage, was das Wissen sei, auf den rechten Boden und in die sichere Bahn zu bringen, dann dürfen wir erst recht nicht meinen, die Aufhellung und Entfaltung des Wesens der deutschen Universität erfolge im laufenden oder kommenden Semester. Aber eines freilich wissen wir aus dem angezeigten Wesen der Wissenschaft, daß die deutsche Universität nur dann zu Gestalt und Macht kommt, wenn die drei Dienste— Arbeits-, Wehr- und Wissensdienst— urprünglich zu einer prägenden Kraft sich zusammenfinden. Das will sagen: Der Wesenswille der Lehrerschaft muß zu der Einfachheit und Weite des Wissens um das Wesen der Wissenschaft erwachen und erstarken. Der Wesenswille der Schülerschaft muß sich in die höchste Klarheit und Zucht des Wissens hinaufzwingen und sie Mitwissenschaft um das Volk und seinen Staat in das Wesen der Wissenschaft fordernd und bestimmend hineingestalten. Beide Willen müssen sich gegenseitig zum Kampf stellen. Alle willentlichen und denkerischen Vermögen, alle Kräfte des Herzens und alle Fähigkeiten des Leibes müssen durch Kampf entfaltet, im Kampf gesteigert und als Kampf bewahrt bleiben. Wir wählen den wissenden Kampf der Fragenden und bekennen mit Carl von Clausewitz: »Ich sage mich los von der leichtsinnigen Hoffnung einer Errettung durch die Hand des Zufalls.« Die Kampfgemeinschaft der Lehrer und Schüler wird aber nur dann die deutsche Universität zur Stätte der geistigen Gesetzgebung umschaffen und in ihr die Mitte der straffsten Sammlung zum höchsten Dienst am Volke in seinem Staat erwirken, wenn Lehrerschaft und Schülerschaft einfacher, härter und bedürfnisloser als alle anderen Volksgenossen ihr Dasein einrichten. Alle Führung muß der Gefolgschaft die Eigenkraft zugestehen. Jedes Folgen aber trägt in sich den Widerstand. Dieser Wesensgegensatz im Führen und Folgen darf weder verwischt, noch gar ausgelöscht werden. Der Kampf allein hält den Gegensatz offen und pflanzt in die ganze Körperschaft von Lehrern und Schülern jene Grundstimmung, aus der heraus die sich begrenzende Selbstbehauptung die entschlossene Selbstbesinnung zur echten Selbstverwaltung ermächtigt. Wollen wir das Wesen der deutschen Universität, oder wollen wir es nicht? Es steht bei uns, ob und wie weit wir uns um die Selbstbesinnung und Selbstbehauptung von Grund aus und nicht nur beiläufig bemühen oder ob wir— in bester Absicht— nur alte Einrichtungen ändern und neue anfügen. Niemand wird uns hindern, dies zu tun. Aber niemand wird uns auch fragen, ob wir wollen oder nicht wollen, wenn die geistige Kraft des Abendlandes versagt und dieses in seinen Fugen kracht, wenn die abgelebte Scheinkultur in sich zusammenstürzt und alle Kräfte in die Verwirrung reißt und im Wahnsinn ersticken läßt. Ob solches geschieht oder nicht geschieht, das hängt allein daran, ob wir als geschichtlich-geistiges Volk uns selbst noch und wieder wollen— oder ob wir uns nicht mehr wollen. Jeder einzelne entscheidet darüber mit, auch dann und gerade dann, wenn er vor dieser Entscheidung ausweicht. Aber wir wollen, daß unser Volk seinen geschichtlichen Auftrag erfüllt. Wir wollen uns selbst. Denn die junge und jüngste Kraft des Volkes, die über uns schon hinweggreift, hat darüber bereits entschieden. Die Herrlichkeit aber und die Größe dieses Aufbruchs verstehen wir dann erst ganz, wenn wir in uns jene tiefe und weite Besonnenheit tragen, aus der die alte griechische Weisheit das Wort gesprochen: ta ... megala panta episfalh ... »Alles Große steht im Sturm...« (Platon, Politeia 497 d, 9) Aus: Heidegger, Martin; Die Selbstbehauptung der deutschen Universität; Breisgau, 19342; S. 5 - 22 |
1934
4月23日の会議で総長辞任を伝える。
5月、ドイツ法律アカデミー法哲学委員会(委員長ハンス・フランク)に招聘された。
6月30日から7月2日にかけて長いナイフの夜(レーム一 揆;SA粛清事件)で突撃隊がナチ党によって粛清。エルンスト・クリーク(Ernst Krieck, 1882-1947)と対立。クリークは「第三帝国」とい う用語の考案者(1917)といわれている。
夏学期、フライブルク大学で「言 葉の本質への問いとしての論理学」講義。
夏以降、ベルリン大学教官アカデミー設立計画。
1934-1935年冬学期「ヘ
ルダーリンの讃歌『ゲルマーニエン』と『ライン』」講義。
1935 46歳
夏学期、フライブルク大学で「形 而上学入門」を講義。
秋、物理学者カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカー、ハイゼンベルクとトートナウベルク山荘で数日間対話する。
11月13日、フライブルク芸術学協会で「芸術作品の起源」講演。
ニーチェ全集刊行委員となり、「ニーチェ文庫」を訪問。
1935年から1936年にかけての冬学期に「物
への問い:カントの超越論的原則論に向けて」講義。
1936 47歳
1月、チューリヒで「芸術作品の起源」講演。
夏学期、フライブルク大学で「シェ リング『人間的自由の本質について』」講義。
ローマのイタリアドイツ文化研究所で「ヘ ルダーリンと詩の本質」「ヨーロッパとドイツ哲学」の講演。
ヒトラー・ユーゲントの機関紙『意志と力』から非難される。
5月14日、ローゼンベルク事務局からの調査を受ける。
5月29日、ハイデッガーへの監視命令が国家秘密情報機関から出された。
11月17日-24日と12月4日に、フランクフルト自由ドイツ高等神学校で「芸術作品の起源」講演。
1936年から1937年にかけての冬学期に「ニーチェ,芸術としての力への意志」講義。
1936年から1938年にかけて草稿群『哲学への寄与論考』を書いた。
1937 48歳
夏学期、フライブルク大学で「西洋的思考におけるニーチェの形而上学的な根本の立場」講義。
ジャン・ヴァール(Jean André Wahl、1888−1974)に、自分の問題は実存ではなく存在でありヤスパースとは異なると語る。
1937年から1938年にかけての冬学期に「哲学の根本的問い 論理学精選諸問題」講義。
1938 49歳
6月9日、フライブルク大学で「形而上学による近世的世界像の基礎づけ」を講演、のちに「世 界像の時代(Die Zeit des Weltbildes)」と改題。
1938年から1939年にかけての冬学期「ニーチェ 反時代的考察第二編」講義
1939 50歳
夏学期、「認識としての力への意思についての教説」講義。
9月、ナチスのポーランド侵攻により第二次世界大戦開始。
ゼミナール「言語の本質について:言語の形而上学:ヘルダー言語起源論に寄せて」。
1939年から1940年の冬、ユンガー「労働者」について議論。
1940 51歳
「真性についてのプラトンの教説」を『精神的伝統』第二年次年報に発表。
第二学期講義「ニーチェ ヨーロッパのニヒリズム」
1941 52歳
フライブルク大学で「ド イツ観念論の形而上学:シェリング」を講義。
夏学期、「根本諸概念」講義。
1941-1942年冬学期、予告された「ニー
チェの形而上学」ではなく、「ヘ
ルダーリンの讃歌『回想』」講義。
1942 53歳
『存在と時間』第5版ではフッサールの献辞は削除される。
草稿「形而上学の克服」。
夏学期、「ヘ ルダーリンの讃歌『イスター』」講義。
1942-1943年冬学期にパルメニデス講義。
「ヘー
ゲルの経験概念」講演。
1943 54歳
真理の本質について」出版。
ヘラクレイトス講義。
講演「ニーチェの言葉:神は死んだ」。
1944 55歳
1944 年ハイデガー(55歳)夏学期、ヘラクレイトス講義。この講義のなかでハイデッガーは「ドイツ民族が西洋の歴史的な民族でありつづけるのか、それともそう でないのかどうかという、このことだけが決定を迫られているのではなくて、今は大地の人間が大地もろともに危険にさらされているのであり、しかも 人間自身によってそうなのである[『全集55』79ページ]」「こ の惑星は炎に包まれている。人間の本質は支離滅裂になっている。ドイツ人がドイツ的なものを見出し、保持 するということが想定されるとすれば、世界史的な熟慮が生まれるのはドイツ人からのみである。それは思い上がりではないが、しかし元初的な苦境を決着にい たるまで持ちこたえるという必然性の知である[『全集55』138ページ]」と語った。
「語つまりそのなかで歴史的な人間の本質が自らを委
ね渡している語とは、真有の語である。この元初的な語は詩作と思索のなかで保有される。たとえ何がそしていかに西洋の外的な歴運が接合されるにせよ、ドイ
ツ人たちの最大にして本当の試練、つまり彼らがあるいは無知な者たちによって彼らの意に反して試されるかもしれない彼の試練はなおも目前に迫っている、す
なわち、彼ら、ドイツ人たちは真有の真性との融和の内にあるのかどうか、また彼らは死への覚悟を越えて、現代世界の視野の狭さに対して元初的なものをその
目立たない飾りの内へと救い出すほど十分に強靭であるのかどうかと」[『全集55』208ページ]
軍務を免除された500人の学者と芸術家のなかに入れられず、「不用」グループの最年長の筆頭として国民突撃隊(Deutscher Volkssturm)に招集された。
夏、ライン川保塁工事に従事。
1944年-45年の冬学期にフライブルク大学で「哲 学入門―思索と詩作」 を講義、11月8日で招集のため中断した。
11月27日、連合軍の爆撃でフライブルクは壊滅した。
1945 56歳
4月30日、ヒトラー自殺。
5月7日、ドイツ降伏。
6月、フランス軍がバーデン=ヴュルテンベルク州を占領。
フィヒテナウのヴィルデンシュタイン城に避難。城近くの岩山の上でカント、ヘルダーリンを講義した。
夏学期は6月24日に終了。
6月27日、ベルンハルト・フォン・ザクセン=マイニンゲン公の森林官宅で講演「貧しさ」。
7月16日、フランス占領軍がレーテブック47番地の家屋接収を通告したため、市長に抗議。
7月23日、非ナチ化純化委員会の査問。ヤスパースを頼るが、厳しい内容の報告をされる。
11月から12月にかけてフランス占領当局によってフライブルク大学において非ナチ化を行う純化委員会の査問を受ける。
年末にコンラート・グレーバー大司教に救援を求めた。
1946 57歳
1月19日、純化委員会がハイデッガーの教職活動剥奪と年金減額をフランス軍政当局に提案。フランス軍政局は年金削除を命じた。
3月8日、グレーバー大司教は教皇ピウス12世にハイデッガーは沈思反省していると報告。
バーデンヴァイラー在のビンスワンガー派の精神科医ヴィクトリア・フライヘル・フォン・ゲープザッテルの診察を受ける。
フライブルクの家は占領軍の宿営として接収されたためトートナウベルクの山荘に住んだ。
夏、フランス軍政当局はハイデッガーの無期限教職禁止令を指令。これは大学からの免職ではなく、研究教授としての在留を認めたものでもあっ た [5]。12月、バーデン州文部大臣から大学教職無期限停止令が下された。
夏、フランス軍政当局が無期限教職禁止令を指令。
中国人シャオレンイーと『老子』のドイツ語訳に着手したが、中断した。
10月、ベルンのペルー大使館秘書官アダルペルト・ワグナーから経済援助をうける。
11月10日、ジャン・ボーフレが書簡で質問。
12月、バーデン州文部大臣から大学教職無期限停止令が下された。
1947 58歳
5月、フランス軍政局は年金削除を取り消す。ジャン・ボーフレへの返信。
1949 60歳
2月6日、ヤスパースとの文通を開始。
3月、フランス軍政局はナチスとの関係は「服従することなき同行者。制裁に及ばず」と最終決定。
5月、フライブルク大学評議会がハイデッガーを名誉教授として復権させ、教職活動の再開案を過半数で可決した。
ジャン・ボーフレへの返信が「『ヒューマニズム』に関する書簡」としてベルンで出版。
11月から「ヨーロッパユダヤ文化再建委員会」のナチス略奪文化財の調査でハンナ・アーレントが訪欧していた。
1950 61歳
ハンナ・アーレントが、ヤスパースに会ったあ と、1月にフライブルクを訪問し、ハイデッガーと会った[328]。ハイデッガーはアーレントのホテルを訪れ、またハイデッガーの家では妻エル フレーデと三人で会ったが、諍いとなった
1951 復職し、退官教授
1952
5月19日、ハンナ・アーレントは再びフライブルクを訪問し、ハイデッガーと会った[335]。6月6日の夫への手紙でハイデッガー の講義はすばらしいものであったが、その妻とは悶着をおこし、ハイデッガーの5万ページの未発表原稿は「本来ならそれを彼女(妻エルフレーデ)が数年のあ いだにスムーズにタイプすることができていたはず」なのにしなかった、ハイデッガーが頼れるのは弟だけと報告している
1953
『形而上学入門』がマックス・ニーマイヤー書店より再刊される。当時24歳の学生ユルゲン・ハーバーマスは「『存在と時間』の魅力に 取り憑かれていただけに、文体の隅々までファシズム的なものの染み込んでいるこの講義を読んで大きなショックを受け」、「ハイデッガーとハイデッガーに対 して考える」を1953年7月25日フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング紙上に発表し、「この運動の内的真理と偉大さ」という文中での表現に ついて注釈も序文での説明もないまま刊行したハイデッガーを「ファシスト的知性」と非難し、「数百万人の人間に対する、今日我々みなが知っている計画的な 殺人も、運命的な迷誤として存在史的に理解することができるというのだろうか。それは帰責能力をもって殺人を行った人々の実際の犯罪ではないのか。それに 対しては、一つの民族全体が良心の呵責を感じねばならぬのではないのか」と質問した。
1953
1927年の初版以来『存在と時間』の冒頭には「上巻」の文字があったが、ハイデッガーは1953年の第7版からこれを削除。
1967
7月24日、詩人パウル・ツェランがフライブルク大学で朗読会を開き、ハイデッガーも聴衆としており、翌日7月25日、トートナウベ ルクのハイデッガー山荘を訪れた[371]。ツェランから詩を送られたハイデッガーは1968年1月30日付礼状書簡で「私は幾つかのことはまだ、いつの 日か、無-言を脱して対話に入れるものと思っています」と書いた[372]。1967年、ハンナ・アレントがハイデッガーを訪問。
1969 ハンナ・アレントが夫ハインリヒ・ブリューヒャーとハイデッガーを訪問し、それからは毎年のようにハイデッガー宅を訪問する
1976 5月26日死去
1987
Heidegger y el Nazismo, でヨーロッパで大スキャンダルになる。ガダマーやデリダは、ファリアスのハイデガーの読みを批判することで批判し、ハイデガーの反ユダヤ主義はすでに知ら れて問題にならずとした。ハイデガーを生粋のファシストとしたい派と、ハイデガーの哲学上のゆるぎない業績と、ハイデガーの「世俗的で矮小な」アイヒマン 的なナチへ関与には関心のない「哲学ユートピア」派に、無残にも別れてしまった。ハイデガーの詳細な伝記を書いたザフランスキーも、擁護派に回っている。 それぐらい、ハイデガーの思想は偉大ということか?
1989
マールブルク大学と同時期にやはりハイデッガーを招聘しようとしていたゲッティンゲン大学のゲオルク・ミッシュに提出した同内容の論考が発見さ れ、その内容から「ナトルプ報告」が『存在と時間』の初期草稿であるとする推測の正しかったことが証明。
2013
ヴィットリオ・クロスターマン社全集94-96巻に掲載されたハイデッガーが1930年代から1970年代にかけて書き続けた手稿 「黒ノート」に反ユダヤ主義についての箇所があることが問題に。この件に関しては、ジャン=リュック・ナンシーのみが、一番まともで、ハイデガーのナチス協力とナチスへの信 奉はゆるぎないもので、誰も知っていたことで「ハイデッガーが反ユダヤ主義に加担したことは1950年代から知られていたし、ハイデッガーの限界とは我々 の限界でもあると論じた」
▶︎ナチズムと存在論(的修辞)には深い関係があり、ハイデガーがそれに関わったことは間違いが ない。
▶︎︎ナチズムは、反共産主義のイデオロギーを標榜しており、経済階級は民族Volkという、超 概念的な単一体のなかに溶け込んでいくだろうと予測された。
「フェルキッシュ (独: völkisch)は、 フォルク(独: Volk)からの派生語として重要な語である。フェルキッシュは19世紀末から第二次世界大戦終了時までドイツにおいて普通に使われ、当時の出版物と政治 において大きな役割を果たした。20世紀の中頃からこの表現は殆ど使われなくなった(独和辞典では古語として扱われている)。しかしながら、現代のドイツ においてこの語に合致した運動や政党が2013年‐2014年頃から勃興し、フェルキッシュという語を使った解説記事が増えている。フェルキッシュという 語は現代において人種主義 (レイシズム)という概念に移し替えられたり、反セム主義の一種であると記述されることもある。ドイツ語圏においてフェルキッシュ運動、フェルキッシュ・ナショナリズムという用語も使われて いる。 フェルキッシュは「民族の、国家主義的」と訳される場合もあるが、近代ドイツの歴史と密接につながっているため、英語のナショナリズム (nationalsm) ともエスノセントリズム (ethnocentrism) とも異なる意味を含んでいる。ナチス政権時代において、1933年からフェルキッシュ、もしくはドイツ・フェルキッシュという語はしばしば国家社会主義と同義語として使われた[15]。この語は政権側で頻繁に 使用されるボキャブラリーに入っていた[16](ナチスの言語, Sprache des Nationalsozialismusも参照)。フェルキッシュとは別の人種差別的メルクマールを欧州におけるファシズム陣営は作り出した[17]。 フェルキッシュ概念に、同じイデオロギーに根拠づけられたフレムトフェルキッシュ(異 民族)(独:fremdvölkisch) という語が対置することになった。それゆえ、異民族によって構成される住民集団はド イツ民族共同体にとって危険な存在と見なされ、居住地域を分けることが 語られた。なるほど、フレムトフェルキッシュ(異民族)は労働力の一部として必要な存在とされたが、法的権利や保護は縮小されるか、認められない扱いを受 けるとされた[18]。フレムトフェルキッシュ(異民族)という語の造語に関して、ナチス政権関係者による関与は大きくはない。ナチス政権成立の1933 年より前において、人種学(優生学)者ハンス・ギュンターが ドイツ民族の人種学という学問分野においてこの専門用語を用いていた。さらに、19世紀に結成された全ドイツ連盟という汎ゲルマン主義組織の指導者ハイン リヒ・クラース(ドイツ語版)も1912年においてフレムトフェルキッシュ(異民族)外国人をドイツの労働力として用いることに賛成していた[19]。」
Fremdvölkische: Fremdvölkische
('foreign
races') was a term used during the Nazi era to describe people who were
not of "German or related blood" (Nuremberg Laws). The term at first
was used only by members of the Schutzstaffel, but later was used by
the Reich police, justice system, and state bureaucracy.
▶︎ハイデガー自身の特殊な言語観:ドイツ語が古代ギリシャから直接継承された言語。ラテン語 は、異形の導管であったが、ドイツ語はその影響を受けなかった。(Heidegger's German- Centrism)
▶︎︎歴史と民族の存在はとても深く結びついている(1935)
▶ハイデガーはナチズムに協力したよりも、むしろ、急進的ナチズムの推進者だった(49-50)
リンク
文献
その他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099