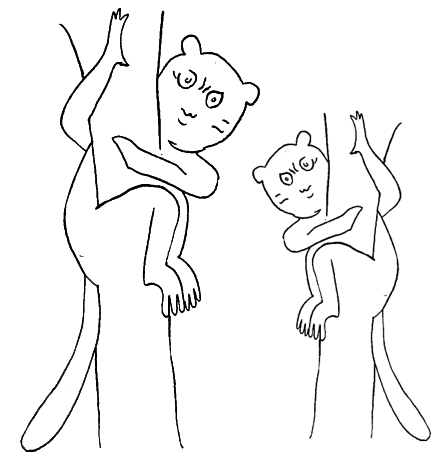
ディペシュ・チャクラバルティ
Dipesh Chakrabarty,
b.1948
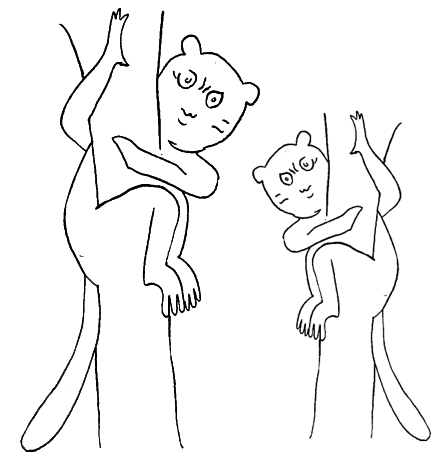
☆
| Dipesh Chakrabarty
(* 15. Dezember 1948 in Kolkata) ist ein indischer Historiker, der sich
mit Themen wie Kulturimperialismus, Postkolonialismus, der
Menschheitsgeschichte und der Arbeiterbewegung im indischen Bengalen
befasst. Er ist ein Vorreiter der postkolonialen Geschichtsschreibung. |
ディペシュ・チャクラバルティ(1948年12月15日、コルカタ生まれ)は、文化帝国主義、ポストコロニアリズム、人類史、インドのベンガル地方における労働者運動などを研究するインドの歴史家。ポストコロニアル史学の先駆者でもある。 |
| Leben Chakrabarty besuchte das Presidency College an der University of Calcutta, wo er einen Abschluss in Physik machte. Später erhielt er ein Diplom in Business Management des Indian Institute of Management, ebenfalls in Kalkutta. An der Australian National University in Canberra, Australien, promovierte er im Fach Geschichte. Zurzeit (2021) ist er Professor an der University of Chicago, am Lawrence A. Kimpton-Lehrstuhl des Fachbereichs für Südasiatische Sprachen und Kulturen. Er verfasst Artikel in der Fachzeitschrift Public Culture, die von der Duke University herausgegeben wird. Zuvor lehrte er am Centre for Studies in Social Sciences in Kalkutta. Chakrabarty ist Mitglied der Subaltern Studies Group und setzt sich mit Theorien des Postkolonialismus und ihrer Verbindung zur Geschichtsschreibung auseinander. 2004 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt, 2006 zum Ehrenfellow der Australian Academy of the Humanities, 2010 Ehrendoktor der Universität London, 2011 der Universität Antwerpen. Toynbee Prize 2014. 2023 wurde Chakrabarty zum Korrespondierenden Mitglied der British Academy gewählt. |
人生 チャクラバルティは、カルカッタ大学プレジデンシー・カレッジで物理学を専攻し、学位を取得した。その後、同じくカルカッタにあるインド経営大学院で経営 学の学位を取得した。オーストラリアのキャンベラにあるオーストラリア国立大学で、歴史学の博士号を取得した。現在(2021年)、シカゴ大学南アジア言 語文化学科のローレンス・A・キンプトン教授を務めている。デューク大学が発行する学術誌「パブリック・カルチャー」に論文を執筆している。以前は、カル カッタの社会科学研究センターで教鞭をとっていた。 チャクラバルティは、サブアルタン・スタディーズ・グループのメンバーであり、ポストコロニアル主義の理論と歴史学との関連について研究している。 2004年にアメリカ芸術科学アカデミー会員に選出され、2006年にオーストラリア人文科学アカデミー名誉フェロー、2010年にロンドン大学名誉博 士、2011年にアントワープ大学名誉博士の称号を授与された。2014年にトインビー賞を受賞。2023年に英国学士院の通信会員に選出された。 |
| Wirken Als Chakrabarty im Jahr 2000 seine Aufsatzsammlung Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (dt.: Europa als Provinz: Perspektiven postkolonialer Geschichtsschreibung) publizierte, war die geistige Strömung des Postkolonialismus bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts dabei, sich mit den Auswirkungen der Kolonialmacht auf die Kolonialisierten zu beschäftigen, nachdem die Kolonialmacht das Land längst wieder verlassen hatte. Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer grundsätzlichen Überarbeitung. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Chakrabarty legt den Schwerpunkt auf die Problematik einer Geschichtsschreibung in seinem Heimatland Indien. Er weist nach, dass „Europa im historischen Wissen als stillschweigender Maßstab fungiert“[1], und schildert die Schwierigkeiten, sich von der allgegenwärtigen europäischen Geschichte zu lösen, ohne die eine indische Geschichtsschreibung gar nicht möglich zu sein scheint. Denn die Geschichte Indiens, aber auch anderer ehemaliger Kolonien, werde von europäischen Diskursen geprägt. Begrifflichkeiten wie Kapitalismus, Bürgertum oder Aufklärung, Vernunft, die zum Handwerkszeug eines jeden Historikers gehören, erscheinen als vermeintlich universal einsetzbare, neutrale Größen. Jedoch sei dies nicht der Fall. Durch ihren Entstehungskontext in der europäischen Geschichte beziehen sie sich nach Chakrabarty als deren inhärenten Vergleichspunkt auf diese. Entsprechende Phänomene im Kontext kolonialer Geschichtsschreibung blitzen dann als ‚Variationen einer Haupterzählung' auf, in der Europa das unausgesprochene Subjekt bleibt.[2] Kulturell oder sonstig bedingte ‚Abweichungen' erscheinen somit automatisch in einem defizitären Licht, wodurch die ehemalige Kolonie auf der repräsentativen Ebene der Sprache immer wieder in der Situation des Mangels verhaftet. Die europäische Moderne wird als ein universaler Maßstab betrachtet und ungeachtet der Bindung an die europäische Kulturgeschichte von außereuropäischen Intellektuellen auf die eigene Kulturgeschichte angewendet. Die Geschichte Europas sei der Prototyp einer universalen Entwicklung aller Geschichten. Diese Diskrepanz falle automatisch zu Lasten der nichteuropäischen Kulturen, da durch das nicht zu erreichende „Ideal“ eine Geschichte des Mangels und des Scheiterns entstehe.[3] Grundlegend stelle das Macht- bzw. Herrschaftsproblem und die Subalternität indischer Geschichte einen globalen Aushandlungs- und Abgrenzungsprozess dar, der Gegensätze zwischen europäisch und außereuropäisch markiere. Obwohl es nicht um eine simple Ablehnung der Moderne oder einen „kulturellen Relativismus“ gehe, betrachtet er Europa als eine Provinz einer heterogenen Welt und spricht sich für eine kontextuelle Geschichtsschreibung aus, um die bestehenden Machtverhältnisse aufzubrechen, so dass die Gleichsetzung von europäischer Geschichte mit einer Universalgeschichte verhindert wird. Die Ambivalenzen, Widersprüche, Gewaltanwendungen, Tragödien und ironischen Momente der Geschichte der Moderne müssten aufgedeckt werden. Daher regt Chakrabarty unter anderem an, die Geschichte der modernen Medizin, des öffentlichen Gesundheitswesens und der persönlichen Hygiene zu verfolgen. An dieser Schnittstelle des modernen Menschen, der sowohl eine öffentliche Seite als auch eine private besitzt, wurden pandemisch und alltäglich moderne Werte mit den Mitteln von Gewalt durchgesetzt (z. B. Impfzwang).[4] Doch reicht die Dekonstruktion der westlich geprägten Geisteswissenschaften nicht aus, weil die Klimakrise und die Macht des Menschen die Grenzen des postkolonialen Diskurses sprengen, der „in Bezug auf die Umwelt blind“ war. Wie Gayatri Chakravorty Spivak in den 1990er Jahren konstatiert hat, werde das Globale (inkl. der kapitalistischen Globalisierung) durch das Planetare „überschrieben“, ohne dabei die sozialen und kulturellen Differenzen zu ignorieren: „Das Globale ist eine humanozentrische Konstruktion; der Planet dezentriert den Menschen.“[5] |
影響 チャクラバルティが2000年にエッセイ集『Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference(ヨーロッパを地方化する:ポストコロニアル思想と歴史的差異)』を出版したとき、ポストコロニアル主義の知的潮流は、20世紀半ば からすでに、植民地支配の影響について考察し始めていた。ポストコロニアル史学の視点)を出版した当時、ポストコロニアル主義という知的潮流は、植民地支 配がすでに終焉してから久しいにもかかわらず、植民地支配が被支配者に与えた影響について考察し始めていた。 この記事またはこのセクションは、根本的な見直しが必要です。改善にご協力ください。その後、このマークを削除してください。 チャクラバルティは、母国インドの歴史記述の問題に焦点を当てています。彼は、「歴史的知識において、ヨーロッパは暗黙の基準として機能している」[1] ことを指摘し、インドの歴史記述には欠かせない、至る所に存在するヨーロッパの歴史から脱却することの難しさを述べています。なぜなら、インドだけでな く、他の旧植民地の歴史も、ヨーロッパの議論によって形作られているからだ。資本主義、ブルジョアジー、啓蒙、理性など、あらゆる歴史家の道具である用語 は、普遍的に適用できる中立的な概念のように見える。しかし、実際にはそうではない。チャクラバルティによれば、これらの概念は、ヨーロッパの歴史の中で 生まれた背景から、その比較基準としてヨーロッパに固有のものとなっている。植民地時代の歴史記述における同様の現象は、「主要な物語のバリエーション」 として現れ、ヨーロッパが暗黙の主題として残る。[2] したがって、文化的またはその他の要因による「逸脱」は、自動的に欠乏的な光の中で現れ、その結果、言語の表現レベルにおいて、旧植民地は常に欠乏の状況 に陥る。ヨーロッパの近代は、普遍的な基準とみなされ、ヨーロッパの文化史との結びつきにもかかわらず、ヨーロッパ以外の知識人によって、自らの文化史に 適用されている。ヨーロッパの歴史は、すべての歴史の普遍的な発展の原型である。この不一致は、達成不可能な「理想」によって欠乏と失敗の歴史が生まれる ため、自動的に非ヨーロッパ文化に不利に働く。[3] 基本的に、インドの歴史における権力・支配の問題と従属性は、ヨーロッパと非ヨーロッパの対立を浮き彫りにする、グローバルな交渉と境界設定のプロセスを 表している。 彼は、単に近代を否定したり、「文化的相対主義」を唱えるわけではないが、ヨーロッパを異質な世界の一地方と捉え、既存の権力関係を打破し、ヨーロッパの 歴史を普遍的な歴史と同一視することを防ぐため、文脈に応じた歴史記述を提唱している。近代史の矛盾、対立、暴力、悲劇、皮肉な瞬間を明らかにする必要が ある。そのため、チャクラバルティは、近代医学、公衆衛生、個人衛生の歴史を追うことを提案している。公共の側面と私的な側面の両方を持つ現代人のこの交 差点では、パンデミックや日常生活の中で、暴力(例えば、予防接種義務)によって現代的価値観が押し付けられてきた。[4] しかし、気候危機と人間の力は、「環境に関して盲目」だったポストコロニアル論の限界を打ち破っているため、西洋の影響を受けた人文科学の脱構築だけでは 不十分だ。1990年代にガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクが指摘したように、グローバル(資本主義的グローバル化を含む)は、社会的・文化的差 異を無視することなく、惑星的なものによって「上書き」されている。「グローバルは人間中心の構築物であり、惑星は人間を中心から外す」[5]。 |
| Veröffentlichungen in deutscher Sprache Wir Erdlinge. Eine planetarische Perspektive auf die menschliche Geschichte. Aus dem Englischen von Christine Pries. In: APZ 14–15/2025, Bundeszentrale für politische Bildung, S. 4–8. online Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter. Aus dem Englischen von Christine Pries, Suhrkamp, Berlin 2025, ISBN 978-3-518-30046-6. (Zeitschriftenaufsätze von 2009 bis 2019; zuerst 2022) Ausstellungskatalog: The Ultimate Capital is the Sun: Metabolismus in Kunst, Politik, Philosophie und Wissenschaft, de/en. Neue Gesellschaft für bildende Kunst, Berlin 2014, ISBN 978-3-938515-57-0. Europa als Provinz. Perspektiven postkolonialer Geschichtsschreibung. Aus dem Englischen von Robin Cackett, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-593-39262-2.[6][7] (Aufsatzsammlung). in anderen Sprachen The Calling of History: Sir Jadunath Sarkar and His Empire of Truth. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA 2015, ISBN 978-0-226-10044-9. Hg. mit Henning Trüper und Sanjay Subrahmanyam: Historical Teleologies in the Modern World. Bloomsbury Academic, London 2015, ISBN 978-1-4742-2106-1. El humanismo en la era de la globalización. Katz Barpal Editores, Buenos Aires/Madrid 2009, ISBN 978-84-96859-52-4. Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies. University of Chicago Press, Chicago, Illinois 2004, ISBN 0-226-10039-1. Cosmopolitanism. mit Carol Breckenridge, Sheldon Pollock und Homi K. Bhabha. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historial Difference. Princeton UP, Princeton, NJ 2000, ISBN 0-19-565537-0. Rethinking Working Class History: Bengal, 1890–1940. Princeton UP, Princeton NJ 2000, ISBN 0-691-07030-X. Communal Riots and Labour: Bengal’s Jute Mill Hands in the 1890s. Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta 1976. |
出版物 ドイツ語 Wir Erdlinge(私たち地球人)。人類の歴史を惑星的な視点から見た本。英語からドイツ語へ翻訳:クリスティン・プリエス。掲載:APZ 14–15/2025、連邦政治教育センター、4–8 ページ。オンライン Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter(惑星時代における歴史の気候)。英語からドイツ語へ翻訳:クリスティン・プリエス、スールカンプ、ベルリン 2025 年、 ISBN 978-3-518-30046-6。(2009 年から 2019 年までの雑誌掲載論文、2022 年初版) 展覧会カタログ:The Ultimate Capital is the Sun: Metabolismus in Kunst, Politik, Philosophie und Wissenschaft(究極の資本は太陽である:芸術、政治、哲学、科学におけるメタボリズム)、ドイツ語/英語。Neue Gesellschaft für bildende Kunst、ベルリン 2014 年、 ISBN 978-3-938515-57-0。 ヨーロッパは地方である。ポストコロニアル歴史学の見方。ロビン・カケット訳、キャンパス出版社、フランクフルト・アム・マイン、2010年、ISBN 978-3-593-39262-2。[6][7](論文集)。 他の言語 The Calling of History: Sir Jadunath Sarkar and His Empire of Truth. シカゴ大学出版局、イリノイ州シカゴ、2015年、ISBN 978-0-226-10044-9。 ヘニング・トゥルーパー、サンジェイ・スブラマニヤムと共編:Historical Teleologies in the Modern World. ブルームズベリー・アカデミック、ロンドン、2015年、 ISBN 978-1-4742-2106-1。 El humanismo en la era de la globalización. Katz Barpal Editores、ブエノスアイレス/マドリード、2009年、ISBN 978-84-96859-52-4。 Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies. University of Chicago Press、シカゴ、イリノイ州、2004年、 ISBN 0-226-10039-1。 コスモポリタニズム。キャロル・ブレッケンリッジ、シェルドン・ポロック、ホミ・K・ババと共著。 Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historial Difference. Princeton UP、プリンストン、ニュージャージー 2000、ISBN 0-19-565537-0。 『労働者階級の歴史を再考する:ベンガル、1890-1940』プリンストン大学出版局、ニュージャージー州プリンストン、2000年、ISBN 0-691-07030-X。 『共同体の暴動と労働:1890年代のベンガルのジュート工場労働者』社会科学研究センター、カルカッタ、1976年。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Dipesh_Chakrabarty |
|
| ディペシュ・チャクラバルティ(Dipesh Chakrabarty、1948年12月15日 - )は、インドの歴史学者。ポストコロニアル理論やサバルタン研究にも貢献している。 現在、シカゴ大学歴史学部のローレンス・A・キンプトン特別功労教授。人類に多大な学術的・公的貢献をした社会科学者を表彰する、アーノルド・J・トインビー教授の名を冠したトインビー賞の2014年受賞者である[1]。 |
|
| 略歴 コルカタ生まれ。コルカタ大学プレジデンシー・カレッジで物理学の学士号を取得。インド経営大学院コルカタ校(Indian Institute of Management Calcutta)で経営学ポスト・グラデュエイト・ディプロマ(Post Graduate Diploma in Management: MBA)を取得した。その後、キャンベラのオーストラリア国立大学へ進み、歴史学の博士号を取得した[2]。 チャクラバルティは、幅広いプログラムの客員教員を務めてきた。プリンストン大学人文科学研究所客員フェロー(2002年)、コルカタ大学社会科学研究セ ンター歴史学Hitesranjan Sanyal客員教授(2003年)、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校人文科学センター客員教授(2004年)、ゲッティンゲン大学マックスプ ランク歴史科学研究所客員フェロー(2005年)、カリフォルニア大学アーバイン校実験批判理論セミナー教員(2005 年)、シドニー工科大学客員教授(2005年および2009年)、ジャワハルラール・ネルー大学歴史研究センター客員教授(2005年)、プラット・イン スティテュートのスカラー・イン・レジデンス(2005年)、欧州人文大学(リトアニア・ヴィリニュス)客員教授(2006年)、アイオワ大学Ida Beam卓越客員教授(2007年)、ミネソタ大学高等研究所卓越客員研究員(2007年)、ベルリン高等研究所フェロー(2008~2009年)。ワシ ントン大学シアトル校カッツ人文学部教授(2009年)、英国マンチェスター大学ホールズワース客員教授(2009年)、人間科学研究所(オースリア・ ウィーン)(2010年)、ヴィクトリア大学(カナダ)ランズダウン講師(2012年)、イリノイ大学アーバナシャンペーン校ニコルソン特別客員研究員 (2013年)。2014年、チャクラバルティは人間科学研究所(ウィーン)で人間科学レクチャー、チャンカヤ自治体(トルコ・アンカラ)で公開講座、ク イーンズ大学(カナダ)学長特別客員研究員、ストーニーブルック大学(ニューヨーク)人文科学研究所卓越客員研究員、バルセロナ大学(スペイン)客員研究 員、オーストラリア国立大学教養学部人文学研究センター客員フェロー(2014年)[3]、ライデン大学地域研究所 (LIAS) 人文学GLASS研究員(2015年)[4]等を歴任した。 また、2014年から2016年までインフォシス賞の人文学部門の審査員を務めた[5]。 研究者のクリスティン・フェアは、彼女がチャクラバルティの学生だった1994年に、彼が不適切な性的発言をしたと告発している[6]。 |
|
| https://x.gd/hh6uS |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099