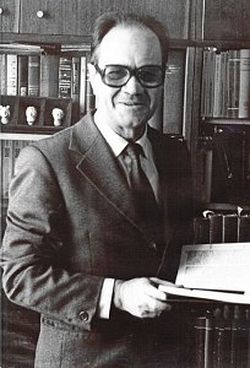
アルセニイ・グリガ
Arseny Gulyga, 1921-1996
☆アルセニー・ウラジーミロヴィチ・グリガは、ソ連国内だけでなく海外でも知られる数少ないソ連の哲学者の一人である。彼は哲学史を専門とし、ヘーゲル (1970年)、カント(1977年)、シェリング(1982年)、ショーペンハウアー(2003年、死後出版)など、数多くの哲学者の肖像を知識人伝の 形式で著した。読者にとってこれらの著作は、重要思想家の複雑な哲学への「入門書」として機能し、生前にドイツ語、英語、フランス語、中国語、日本語へ翻 訳された。グリガの国際的成功は、哲学教育分野に存在した空白、すなわち一般読者、特に若者向けに書かれた平易な哲学理論解釈の不足を埋めたことに起因す る。今日では哲学分野にもこうした「入門書」が数多く存在するが、1970~80年代の哲学者たちは、西側諸国では学術研究に、ソ連ではイデオロギー活動 に、それぞれ専念していたのである。
| Arseny Gulyga (1921-1996) - An Encyclopedia of Russian Thought Arseny Vladimirovich Gulyga is one of a few Soviet philosophers known not only in the Soviet Union, but also abroad. He specialized in the history of philosophy and composed a number of philosophical portraits in the genre of intellectual biography, including on Hegel (1970), Kant (1977), Schelling (1982), and Schopenhauer (published posthumously in 2003). For his readers, these works served as “soft” introductions to the complex philosophies of important thinkers, and during his lifetime his work was translated into German, English, French, Chinese, and Japanese. Gulyga’s international success is likely due to the fact that he filled a lacuna that existed in the field of philosophical education: namely, the lack of popular and accessible interpretations of philosophical theories written for a broad audience, and in particular for young people. Nowadays there are numerous such “introductions” in the field of philosophy, but in the 1970s and 80s philosophers were primarily engaged in either scholarly research, as in the West, or in ideology, as in the Soviet Union. Arseny Gulyga was born in Czechoslovakia in 1921. His father was a metallurgical engineer who had emigrated from Russia after the 1917 Bolshevik Revolution. After the end of the Civil War, the family returned to Russia by invitation of Sergo Ordzhonokidze, a Georgian Bolshevik and later Politburo member. However, Gulyga’s father was arrested in 1937 and executed in 1938, an event that had a significant influence on the remainder of Arseny Gulyga’s personal and professional life. It was only in 1940 that he was able to enroll in the Philosophy Department at the Moscow Institute of History, Philosophy, and Literature; his studies were then interrupted by the Second World War. He initially served in the war as a platoon commander on the Volkhov Front, and later as a translator at regiment headquarters and as an organizer of German anti-fascists operations. He was seriously wounded during the war and was awarded several orders and medals for his service. When the war ended he was in Koenigsberg, at the rank of captain. Gulyga went on to work in the Department of Culture in the Berlin Military Administration as a culture officer (Kulturoffizier) for theaters. He also took part in the denazification of representatives of German culture and, after returning home to Russia, worked for the military newspaper Trevoga. In 1945, Gulyga graduated from the Philosophy Department of Moscow State University. In 1955, he was demobilized from the Soviet Army. He studied at the graduate school of the Institute of the History of the Academy of Sciences of the USSR and defended his dissertation on the topic of the formation of the United Socialist Party in Germany. His early publications were devoted to problems of the American occupation of the Far East during the Russian Civil War. In the field of philosophy, his doctoral dissertation was titled “German Materialism at the End of the 18th Century” (“Nemetskii materializm v kontse XVIII veka”). Gulyga spent more than forty years working at the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the USSR (Moscow): between 1956 and his death in 1996, not including a two-year fellowship he accepted at the Wissenschaftskolleg in Berlin between 1991-1993. He detailed his academic experiences at the Institute of Philosophy in his memoir, “A Half a Century on Volkhonka” (“Polveka na Volkhonke”), which was published in the journal Molodaia Gvardiia in 1997. |
アルセニー・グリガ(1921-1996) アルセニー・ウラジーミロヴィチ・グリガは、ソ連国内だけでなく海外でも知られる数少ないソ連の哲学者の一人である。彼は哲学史を専門とし、ヘーゲル (1970年)、カント(1977年)、シェリング(1982年)、ショーペンハウアー(2003年、死後出版)など、数多くの哲学者の肖像を知識人伝の 形式で著した。読者にとってこれらの著作は、重要思想家の複雑な哲学への「入門書」として機能し、生前にドイツ語、英語、フランス語、中国語、日本語へ翻 訳された。グリガの国際的成功は、哲学教育分野に存在した空白、すなわち一般読者、特に若者向けに書かれた平易な哲学理論解釈の不足を埋めたことに起因す る。今日では哲学分野にもこうした「入門書」が数多く存在するが、1970~80年代の哲学者たちは、西側諸国では学術研究に、ソ連ではイデオロギー活動 に、それぞれ専念していたのである。 アルセニー・グリガは1921年、チェコスロバキアで生まれた。父は冶金技師で、1917年のボルシェビキ革命後にロシアから亡命していた。内戦終結後、 家族はグルジア人ボルシェビキで後に政治局員となるセルゴ・オルジョノキゼの招きでロシアへ戻った。しかし1937年に父は逮捕され、1938年に処刑さ れた。この出来事はアルセニー・グリガのその後の人生と職業生活に重大な影響を与えた。彼がモスクワ歴史・哲学・文学大学哲学部に在籍できたのは1940 年になってからであり、その学業は第二次世界大戦によって中断された。彼は当初ヴォルホフ戦線で小隊長として従軍し、後に連隊司令部で翻訳官、ドイツ人反 ファシスト作戦の組織者として活動した。戦争中に重傷を負い、その功績により複数の勲章とメダルを授与された。終戦時、彼は大尉の階級でケーニヒスベルク にいた。その後、ベルリン軍事行政局文化部で劇場担当文化将校(クルトゥーロフィツィアー)として勤務。ドイツ文化関係者の脱ナチ化にも関与し、ロシア帰 国後は軍新聞『トレヴォーガ』で働いた。 1945年、グリガはモスクワ大学哲学部を卒業した。1955年にはソ連軍から除隊。ソ連科学アカデミー歴史研究所の大学院で学び、ドイツにおける統一社 会党の形成を主題とする博士論文を提出した。初期の著作はロシア内戦期の極東におけるアメリカ占領問題に捧げられた。哲学分野における博士論文の題名は 「18世紀末のドイツ唯物論」(『Nemetskii materializm v kontse XVIII veka』)であった。グリガはソ連科学アカデミー哲学研究所(モスクワ)で40年以上勤務した。1956年から1996年の死去までで、1991年から 1993年にかけてベルリンのヴィッセンシャフトスコレグで受けた2年間のフェローシップは含まれない。彼は哲学研究所での学術的経験を回顧録『ヴォルホ ンカでの半世紀』(原題:Polveka na Volkhonke)に詳述し、これは1997年に雑誌『モロダヤ・グヴァルディア』に掲載された。 |
| The History of Philosophy as Biography Gulyga’s interest in the genre of philosophical biography can be explained by two philosophical positions he held: on the one hand, he is convinced that philosophy can only exist as the history of philosophy; on the other hand, he believes that philosophy is not a realm of pure and autonomous ideas but, like art, is an individual performance (“Wir leben im Zeitalter des Kosmismus” 875). Therefore, in his work he tries to engage important ideas by describing their genesis moments; for example, in his biography of Kant, he writes that “Kant has no other biography than the history of his thought” (Kant 5). This principle of identifying the life of a philosopher with his or her thought underlies all Gulyga’s biographies. The result of such an approach is that philosophical ideas are placed against a broader cultural background and become dependent upon the personal histories of their creators. The reception of Gulyga’s works was ambivalent: critical among academics, and affirmative among the broad reading public. Vladimir Zeman, a contemporary reviewer of Gulyga’s book on Kant, rightly points out that “when we consider him as a historian of philosophy, Gulyga does not generally show any obvious interpretative bias. His conception of his task allows him to concentrate on presentation rather than on in-depth analysis or on the evaluation of Kant’s philosophical position” (172). In spite of the deficiencies of his method, Gulyga’s publications were significant events in Soviet philosophy, since they were able to mitigate the official, anonymous, and teleological jargon of Marxism-Leninism. His work offered an alternative understanding of philosophy as a personal process of creation and as a process of developing concepts and solving problems. In his memoirs, “A Half a Century on Volkhonka,” and elsewhere, Gulyga claims: “The Institute of Philosophy has existed for over fifty years. What is the best that our institute has achieved? It is the series “The Philosophical Heritage” (“Filosofskoe nasledie”). Over 100 volumes have been published, whereby everything else is temporary” (“Wir leben im Zeitalter des Kosmismus,” 875). These words are not merely a critical statement; rather, in them we can see Gulyga’s scholarly orientation and his strategic vision of philosophy. He is convinced that the significance of philosophy is connected to its capability to adapt the ideas developed by previous generations (876). The basic task of philosophy consists in understanding, clarifying, and developing existing concepts and theories (877-78). It is for this reason that he defines the primary goal of philosophical activity as the “popularization, dissemination, and realization of philosophical world heritage” (878). Within the history of Soviet philosophy, Gulyga’s thought can be described in enlightenment terms. Indeed, his major contribution is his work in eighteenth and nineteenth century German philosophy, as well as his role in the rediscovery of Russian religious philosophy that took place during the final years of the Soviet period. He took great care to advance Soviet philosophical education in a variety of ways, including through research, editing and publishing primary sources material, and organizing cultural societies. In 1963, Gulyga founded the well-known series “Philosophical Heritage,” which he co-edited. Under Gulyga’s editorship, the works of Herder, Kant, Lessing, Hegel, Schiller, Schelling, Goethe, and many others were published. In the early 1980s, in particular, the series published forgotten Russian authors for the public, including works by Vladimir Solovyov, Nikolai Berdiaev, Vasily Rozanov, and Nikolai Karamzin. In the late 1970s, he organized a seminar on problems of Russian culture at the Institute of Philosophy. He worked as the deputy editor of the “Philosophical Heritage” series until 1982, when he was expelled from the board for editing the works of Russian cosmist Nikolai Fyodorov, who was branded as a religious obscurantist, necrophile, mystic, and racist (Andreeva). At the beginning of perestroika, he established the Dostoevsky Literary and Philosophical Society, which became the center that promoted public interest in the study of the Russian national philosophical tradition. Two areas of world philosophy, namely German and Russian philosophy, attracted Gulyga’s attention. He considers these traditions to be interconnected and assumes their mutual influence on each other. His methodological premise is that “there is only one world of human culture and only one world philosophy” (“Wir leben im Zeitalter des Kosmismus” 874). Moreover, he represents the view that “original Russian philosophy is a direct continuation of classical German philosophy” (874). It is for this reason that he tries to explicate connections between Kant and Solovyov, insofar as they acknowledged the primacy of practical philosophy. He believes that “it is impossible to understand Russian philosophy without Schelling” (871) and saw in the Slavophile’s concept of sobornost’—or a spiritual community of people living together—an allusion to Hegel’s concept of the “concrete-general” (das Konkret-Allgemeine). His seminar dedicated to philosophical problems of historical scholarship became a platform for discussing the methodological problems of the history of philosophy, a seminar he began at the Institute of Philosophy in 1963 and led for about a decade. |
哲学史を伝記として グリガが哲学伝記というジャンルに関心を持った理由は、彼が抱いていた二つの哲学的立場で説明できる。一方では、哲学は哲学史としてのみ存在し得ると確信 していた。他方では、哲学は純粋で自律的な観念の領域ではなく、芸術と同様に個人の実践であると考えていた(「我々はコスミズムの時代に生きている」 875頁)。したがって彼の著作では、重要な思想の誕生瞬間を描くことでそれらと向き合おうとする。例えばカント伝において「カントには思想史以外の伝記 は存在しない」(『カント』5頁)と記している。哲学者の生涯をその思想と同一視するこの原理は、グルィガの全伝記に貫かれている。このアプローチの結 果、哲学思想はより広範な文化的背景に置かれ、その創始者の個人的な歴史に依存するようになる。 グリガの著作に対する評価は両義的であった。学界では批判的だったが、一般読者層では肯定的だった。グーリガのカンツ論を批評した同時代の評論家ウラジー ミル・ゼーマンは、正しくこう指摘している。「哲学史家としてのグーリガは、概して明らかな解釈的偏向を示さない。彼の任務観は、深層分析やカンツの哲学 的立場の評価よりも、提示に集中することを許容している」(172頁)。方法論上の欠陥にもかかわらず、グリガの著作はソ連哲学において重要な出来事で あった。なぜならそれらは、マルクス・レーニン主義の公式的で匿名的な目的論的専門用語を和らげることに成功したからだ。彼の仕事は、哲学を個人的な創造 過程として、また概念を発展させ問題を解決する過程として理解する別の可能性を示した。 回顧録『ヴォルホンカでの半世紀』などで、グリガはこう述べている。「哲学研究所は50年以上存続してきた。我々の研究所が成し遂げた最高の成果とは何 か?それは『哲学的遺産』シリーズ(Filosofskoe nasledie)である」。100巻以上が刊行され、それ以外の全ては一時的なものに過ぎない」(『我々はコスミズムの時代に生きる』875頁)。この 言葉は単なる批判的発言ではなく、グルィガの学問的指向と哲学に対する戦略的ビジョンを窺わせる。彼は、哲学の意義は過去の世代が発展させた思想を適応さ せる能力と結びついていると確信している(876頁)。哲学の基本的任務は、既存の概念や理論を理解し、明確化し、発展させることにある(877-78 頁)。このため彼は、哲学的活動の第一目標を「哲学的世界遺産の普及、伝播、実現」と定義する(878頁)。 ソ連哲学史において、グリガの思想は啓蒙主義的観点から説明できる。実際、彼の主要な貢献は18~19世紀ドイツ哲学の研究と、ソ連末期に起こったロシア 宗教哲学の再発見における役割にある。彼は研究活動、一次資料の編集・出版、文化団体の組織化など多様な方法でソ連哲学教育の推進に尽力した。 1963年、グリガは著名な叢書『哲学遺産』を創刊し、共同編集を担当した。グリガの編集のもと、ヘルダー、カント、レッシング、ヘーゲル、シラー、シェ リング、ゲーテら多数の著作が刊行された。特に1980年代初頭には、ウラジーミル・ソロヴィヨフ、ニコライ・ベルジャエフ、ヴァシーリー・ロザーノフ、 ニコライ・カラムジンら忘れ去られたロシア人作家の作品を一般向けに刊行した。1970年代後半には、哲学研究所でロシア文化問題に関するセミナーを組織 した。彼は1982年まで『哲学的遺産』シリーズの副編集長を務めたが、ロシア宇宙主義者ニコライ・フョードロフの著作を編集したことで編集委員会から追 放された。フョードロフは宗教的蒙昧主義者、死体愛好者、神秘主義者、人種差別主義者とレッテルを貼られていた(アンドレーエワ)。ペレストロイカ初期に は、ドストエフスキー文学・哲学協会を設立した。同協会はロシア国民哲学伝統の研究に対する社会的関心を促進する中心的存在となった。 世界哲学の二大領域、すなわちドイツ哲学とロシア哲学がグリガの関心を引いた。彼はこれらの伝統が相互に関連し合い、互いに影響し合っていると考える。そ の方法論的前提は「人類文化の世界は一つであり、世界哲学も一つである」というものだ(「我々はコスミズムの時代に生きる」874頁)。さらに彼は「ロシ アの独創的哲学は古典的ドイツ哲学の直接的継承である」という見解を表明している(874頁)。この理由から、実践哲学の優位性を認めた点において、カン トとソロヴィヨフの関連性を解明しようと試みるのである。彼は「シェリングなしにロシア哲学を理解することは不可能である」(871頁)と確信し、スラヴ 主義者の概念であるソボルノスト(共同生活する人々の精神的共同体)に、ヘーゲルの「具体的普遍」(das Konkret-Allgemeine)概念への言及を見出した。歴史学の哲学的問題に捧げられた彼のセミナーは、哲学史の方法論的問題を議論する場と なった。このセミナーは1963年に哲学研究所で始まり、約10年間にわたって続けられた。 |
| A Marxist Approach to the History of Philosophy Gulyga was without a doubt a Marxist historian of philosophy, and his work interprets philosophical positions through the lens of dialectical materialism. This concerns his studies in the field of German classical philosophy in particular, for instance his emphasis on the dialectical moments in Kant’s philosophy: “Kant posed the problem of dialectics” (Nemetskaia klassicheskaia filosofiia 58). When explaining the concept of the categorical imperative, Gulyga gives a sociological explanation: “The day-to-day experience of the society of Kant’s day is opposed to morality; it destroys a person spiritually, rather than educates her” (66). He criticizes the “early” Fichte for his idealism: “In Fichte’s philosophy, there is no authentic object, and this is why the material activity of society exists beyond it” (135). He interpretes young Schelling as a “materialist and atheist” (171). In his opinion, “as compared with Hegel, Schelling, however, has one advantage: in his work, the earthly corps of dialectics are visible, as are its connection with natural science” (176). He summs up the development of German idealism as follows: “The dialectics of idealism was born in the writing of Kant, Fichte, and Schelling, but it was necessary to grow and systematize it. The solution to this problem fell to Hegel” (208). On the Phenomenology of Spirit, he writes that “the master–slave dialectic in Hegel, to a certain extent, anticipates Marx’s analysis of the alienation of labor in capitalist society” (222). He claims that Feuerbach “has prepared a construction site for materialistic dialectics” (293) and that “Feuerbach’s main achievement is atheism” (294). One could continue the list of such quotations. However, Gulyga’s analysis and systematization of German philosophy from the perspective of the origin of dialectic thought does not diminish the significance of his work in his book German Classical Philosophy (Nemetskaia klassicheskaia filosofiia, 1986). This book provides an impressive, vivid, and mostly balanced panorama of the development of German philosophy in the work of Herder, Schiller, Humboldt, Fichte, Schelling, Goethe, Hegel, and others, with particular emphasis on their polemic with Kant. It is rather difficult to follow the development of German philosophy in this period, but Gulyga’s approach is successful since it concentrates on significant thematic interactions that defined the philosophical work of the day. What is more, the book is rich in conceptual, historical, and literary allusions, as well as in anecdotes and facts about a panoply of figures from the 18th century. Last but not least, it is due to Gulyga that Kant—whom Lenin dismissed in his work Materialism and Empiriocriticism (Materializm i empiriokrititsizm, 1909) as an agnostic and dualist and who therefore became persona non grata in Soviet philosophy—found a place in the history of Soviet philosophy. Gulyga began his academic career in the Soviet Union and ended it in post-Soviet Russia. These historical perturbations had a deep impact on his intellectual development. It would be adequate to characterize his experience according to Sergei Bulgakov’s famous expression, that it was a move from “Marxism to Idealism.” However, in Gulyga’s case, the development of his later thought did not involve a complete refusal of Marxist ideals but involved a critique of Marxism in regard to how it was realized in Soviet practice. Thus, Gulyga remained convinced that Marx was “a great thinker” and that “Marxist philosophy is part of a unified world philosophy” (“Wir leben im Zeitalter des Kosmismus,” 879). However, he considers the socialist practice of the Soviet Union to be a perverse deviation from authentic Marxism. He says, for instance, in one of his interviews: “The entire history of the Soviet Union was sooner an attempt to refute Marx than an attempt to realize his ideas” (ibid.). |
マルクス主義的哲学史観 グリガは疑いなくマルクス主義的哲学史家であり、その著作は弁証法的唯物論の視点から哲学的立場を解釈する。これは特にドイツ古典哲学分野の研究に顕著 で、例えばカント哲学における弁証法的瞬間を強調している:「カントは弁証法の問題を提起した」(『ドイツ古典哲学』58頁)。カントの「定言命法」概念 を説明するにあたり、グリガは社会学的解釈を与える。「カント時代の社会における日常的経験は道徳に反する。それは人間を精神的に破壊するものであり、教 育するものではない」(66頁)。彼は「初期」フィヒテの理想主義を批判する:「フィヒテの哲学には真正な対象が存在せず、だからこそ社会の物質的活動は それを超越して存在する」(135頁)。若いシェリングを「唯物論者かつ無神論者」と解釈する(171頁)。彼の見解では、「ヘーゲルと比較して、シェリ ングには一つの利点がある。彼の著作では、弁証法の地上的形態が可視化され、自然科学との関連性も示されている」(176)。彼はドイツ観念論の発展を次 のように総括する:「観念論の弁証法はカント、フィヒテ、シェリングの著作において誕生したが、それを発展させ体系化する必要があった。この課題の解決は ヘーゲルに委ねられた」(208)。『精神現象学』については「ヘーゲルにおける主従弁証法は、ある程度、資本主義社会における労働の疎外に関するマルク スの分析を先取りしている」(222)と記す。またフォイエルバッハは「唯物弁証法の建設現場を整えた」(293)とし、「フォイエルバッハの主たる功績 は無神論である」(294)と主張する。こうした引用例はさらに挙げられる。しかしグルィガによるドイツ哲学の分析と体系化は、『精神現象学』において 「ヘーゲルにおける主従弁証法は、ある程度、資本主義社会における労働の疎外に関するマルクスの分析を先取りしている (293)と記し、「フォイエルバッハの主要な業績は無神論である」(294)とも述べている。 このような引用例はさらに挙げられる。しかし、グリーガが弁証法的思考の起源という観点からドイツ哲学を分析・体系化したことは、彼の著書『ドイツ古典哲 学』(Nemetskaia klassicheskaia filosofiia, 1986)における業績の意義を損なうものではない。本書はヘルダー、シラー、フンボルト、フィヒテ、シェリング、ゲーテ、ヘーゲルらによるドイツ哲学の 発展を、特にカントとの論争に焦点を当てつつ、印象的で鮮烈かつ概ね均衡の取れたパノラマとして提示する。この時代のドイツ哲学の展開を追うのは容易では ないが、当時の哲学的活動を規定した重要な主題的相互作用に集中するグリーガの手法は成功している。さらに本書は、18世紀の多様な人物たちに関する逸話 や事実に加え、概念的・歴史的・文学的な言及にも富んでいる。最後に、グルィガのおかげで、レーニンが『唯物論と経験批判論』(1909年)において不可 知論者かつ二元論者として退け、ソビエト哲学において不遇の扱いを受けたカントが、ソビエト哲学史における地位を得たのである。 グリガはソビエト連邦で学問的キャリアを始め、ポストソビエト時代のロシアで終えた。こうした歴史的変動は彼の知的発展に深い影響を与えた。セルゲイ・ブ ルガーコフの有名な表現を借りれば、彼の経験は「マルクス主義から観念論への移行」と特徴づけられるだろう。しかしグリガの場合、後年の思想発展はマルク ス主義の理想を完全に否定するものではなく、ソ連の実践におけるその実現形態に対する批判を伴っていた。したがってグリガは、マルクスが「偉大な思想家」 であり、「マルクス主義哲学は統一された世界哲学の一部である」という確信を保ち続けた(「我々はコスミズムの時代に生きている」、879頁)。しかし彼 は、ソビエト連邦の社会主義実践を、正統なマルクス主義からの歪んだ逸脱と見なしている。例えばあるインタビューでこう述べている:「ソビエト連邦の全歴 史は、マルクスの思想を実現しようとする試みというより、むしろ彼を反証しようとする試みであった」(同上)。 |
| Wisdom and Humanism in Gulyga’s Philosophy Gulyga was a Marxist with his own, non-Marxist understanding of philosophy as wisdom. He says in one of his interviews: “Philosophy is not an academic science; it is, I would say, not a science at all. It is more than mere science: it is world wisdom.” (“Wir leben im Zeitalter des Kosmismus,” 875). This understanding of philosophy had an impact on his reception of philosophical theories. In all his intellectual biographies, he appears to conduct his analyses and evaluations according to the criterion of the truth-goodness-beauty triad, which he viewed as the elements of wisdom. For instance, he claims that “Fichte considers any philosophy, any science empty, if it does not serve the self-assertion of man” (Nemetskaia klassicheskaia filosofiia, 136). Or, as we read in one of his books: “the first and the last word of the mature Kant is about the individual. Kant’s criticism is largely born due to an interest in the life of the human being. The Copernican turn began with reflection on the destiny of man. The problem of freedom underlies the Critique of Pure Reason” (90). Thus, according to Gulyga, any theory is only valuable if it is able to improve conditio humana. As well, he seemed convinced of the superiority of ethics and aesthetics over theoretical philosophy. Rolf George, for instance, described his impression of Gulyga’s book on Kant as follows: I have heard the book castigated as a propaganda effort. This allegation is absurd in the extreme. There are technical flaws, and occasional distant echoes of Official Philosophy, but this is above all an intelligent and humane book. If it is propaganda for anything, then it is for these virtues. (493) Indeed, this view can be generally applied to all of Gulyga’s philosophical historical portraits, since his focus on wisdom gives his work a humanistic character. Gulyga’s specific historical consciousness forms the basis for his understanding of the present age. He defines it as “postmodernity,” in contrast to the “modernity” of the nineteenth and twentieth centuries. In his terms, “modernity” means “everything that corresponds to the present time and is in a certain contrast to the old, to the past. Hence, the past is considered a prerequisite of the present. It is a lower, suspended step” (“Wir leben im Zeitalter des Kosmismus” 876). On the contrary, “postmodernity” refers to “the past not as a mere prerequisite, but as its own inseparable part. It is a fusion of what is and what was” (ibid.). This general attitude constitutes the methodological framework of his studies on the history of philosophy: he focused on the aspects of theories that he deemed suitable for further development and application in contemporary research contexts. |
グリガの哲学における知恵とヒューマニズム グリガはマルクス主義者でありながら、哲学を「知恵」として捉える独自の非マルクス主義的理解を持っていた。彼はインタビューでこう述べている。「哲学は 学術的科学ではない。むしろ、科学そのものではないと言える。単なる科学を超えた存在だ。それは世界の知恵である」 (「我々はコスミズムの時代に生きる」875頁)。この哲学観は彼の哲学理論受容に影響を与えた。彼の知的伝記全般において、彼は知恵の要素と見なした 「真実・善・美」の三要素を基準に分析と評価を行っているように見える。例えば彼は「フィヒテは、人間の自己主張に役立たない哲学や科学は空虚だと考え る」(『ロシア古典哲学』136頁)と主張する。あるいは彼の著作の一つにはこうある:「成熟したカントの最初と最後の言葉は個人についてだ。カントの批 判は主に人間の生活への関心から生まれた。コペルニクス的転回は人間の運命への省察から始まった。自由の問題は『純粋理性批判』の根底にある」(90 頁)。したがってグリガによれば、あらゆる理論は人間の条件を改善できる場合にのみ価値を持つ。また彼は、理論哲学に対する倫理学と美学の優位性を確信し ているようだった。例えばロルフ・ゲオルゲは、グリーガのカンツに関する著作についての印象を次のように述べている: この本をプロパガンダ的試みとして非難する声を聞いたことがある。この主張は極めて荒唐無稽だ。技術的な欠陥や、時折公式哲学の遠い反響が聞こえる部分は あるが、何よりもこれは知性的で人間味あふれる書物である。もしこれが何かを宣伝するならば、それはこうした美徳のためだろう(493)。 実際、この見解はグリガの哲学的歴史人物像全般に当てはまる。彼の知恵への焦点が、その著作に人文主義的性格を与えているからだ。 グリガの特異な歴史意識は、現代理解の基盤を成す。彼はこれを19・20世紀の「近代性」と対比し「ポストモダニティ」と定義する。彼の用語によれば、 「近代性」とは「現代に対応し、古いもの、過去と一定の対照をなすあらゆるもの」を意味する。したがって、過去は現代の前提条件と見なされる。それは「よ り低い、中断された段階」である(「我々はコスミズムの時代に生きている」876頁)。これに対し「ポストモダニティ」は「過去を単なる前提条件ではな く、それ自体と不可分な一部として捉える。それは現在と過去の融合である」(同上)。この一般的な姿勢が、彼の哲学史研究の方法論的枠組みを構成してい る。彼は理論の諸側面のうち、現代の研究文脈においてさらなる発展と応用が可能と考えた部分に焦点を当てたのである。 |
| The Religious Turn and the Russian Idea After perestroika, Gulyga became increasingly concerned with studies in the field of aesthetics. In 1987, he published the books What is Aesthetics? (Chto takoe estetika?) and The Principles of Aesthetics (Printsipy estetiki). After the collapse of the Soviet Union, he was intensively involved in re-conceptualising the notorious “Russian idea.” The major result of his activity in this regard is his book The Russian Idea and its Creators (Russkaia ideia i ee tvortsy, 1995). Gulyga says, ironically, that the collapse of the Soviet Union had one positive effect: namely, that it “led, first of all, to the return of the Russian idealist tradition,” which is capable of returning traditional Christian religious values to the Russian people (“Wir leben im Zeitalter des Kosmismus,” 871). For him, Solovyov, Dostoevsky, and Fedorov are the most important representatives of Russian philosophy. However, Gulyga believes that the disintegration of the former Soviet empire was an extremely negative event. His nostalgia for the “Great Russia” of the past found its expression, first of all, in his paper “The Formula of Russian Culture” (“Formula russkoi kul’tury,” 1992). In this article, he connects the political crisis of the USSR with a cultural crisis, which he defines as “the loss of a national self-awareness” (145). According to him, the idea of national unity could serve as a basis for political reunification. In contrast to the official Marxist-Leninist definition of the nation as distinguished by shared territorial, economic, and socialist content, Gulyga offers the concept of nation as a “commonality of sanctuaries” (143; 149). Within this perspective, Russian Orthodoxy comes forward as the “creator and keeper” (sozdatel’ i khranitel’) of the sacred (149). According to Gulyga, the mission of Russian religious philosophy, as well as Orthodoxy, is to form national identity. This idea is clearly expressed in his last book, The Russian Idea and Its Creators. The key idea of this publication can be formulated as following: “The most important idea within practical philosophy is the fate of the homeland (rodina)” (18). For this reason, the book has attracted attention not only as an introduction to Russian religious philosophy from Dostoevsky to Losev, guided primarily by the question of “the eternal in Russian philosophy” (to use Boris Vysheslavtsev’s formulation), but also as an explication of Gulyga’s civic position, which was based on Christian orthodox values and traditional Slavophile-Cosmist axioms. One of the most valuable contributions of this book is the way it restored the equilibrium between two branches of the history of philosophy, the German and the Russian traditions, a task that Gulyga made the guiding force of his professional life. We can turn to the words of Mischka Dammaschke and Wladislaw Hedeler to summarize Gulyga’s role in the history of Soviet philosophy: “Throughout his life, Arseny Gulyga was a bridge builder between the Russian and German philosophical worlds of thought” (920). Maja Soboleva, June 2018 |
宗教的転回とロシア思想 ペレストロイカ後、グリガは美学分野の研究にますます関心を深めた。1987年には『美学とは何か?』(Chto takoe estetika?)と『美学の原理』(Printsipy estetiki)を出版した。ソビエト連邦崩壊後は、悪名高い「ロシア思想」の再概念化に精力的に取り組んだ。この分野における彼の活動の主要な成果 が、1995年の著書『ロシア思想とその創造者たち』(『Русская идея и ее творцы』)である。グリガは皮肉を込めて、ソ連崩壊には一つの良い効果があったと述べる。すなわち「何よりもまずロシア観念論の伝統が復活した」こ とであり、この伝統こそがロシア国民に伝統的なキリスト教的宗教的価値観を回復させうるという(「我々はコスミズムの時代に生きている」、871頁)。彼 にとって、ソロヴィヨフ、ドストエフスキー、フェドロフはロシア哲学の最も重要な代表者である。しかしグリガは、旧ソ連帝国の解体は極めて否定的な出来事 だったと考えている。過去の「偉大なるロシア」への彼の郷愁は、まず第一に論文『ロシア文化の公式』(1992年)に表現された。この論文で彼は、ソ連の 政治的危機を「国民的自己認識の喪失」と定義する文化的危機と結びつける(145頁)。彼によれば、国民的統一の理念は政治的再統合の基盤となり得る。マ ルクス・レーニン主義の公式定義が、共有された領土・経済・社会主義的内容によって国民を区別するのに対し、グリガは国民を「聖域の共有性」として提示す る(143; 149)。この視点において、ロシア正教は聖なるものの「創造者かつ守護者」(sozdatel’ i khranitel’)として前面に立つ(149)。 グリガによれば、ロシア宗教哲学および正教の使命は国民的アイデンティティの形成にある。この思想は彼の遺作『ロシア思想とその創造者たち』に明示されて いる。同書の核心思想は「実践哲学における最重要概念は祖国(ロディナ)の運命である」(18頁)と要約できる。このため本書は、ドストエフスキーからロ セフに至るロシア宗教哲学の概説書として注目されただけでなく(ボリス・ヴィシェスラフツェフの表現を借りれば「ロシア哲学における永遠性」の問いを主軸 に据えた)、キリスト教正教の価値観と伝統的なスラヴ主義・コスミズムの公理に基づくグリガの市民的立場の解説書としても注目された。本書の最も貴重な貢 献の一つは、哲学史における二つの流れ、すなわちドイツとロシアの伝統の均衡を回復した点にある。これはグリガが自身の専門的活動の指針とした課題であっ た。ミシュカ・ダマシュケとウラディスラフ・ヘデラーの言葉は、ソビエト哲学史におけるグリガの役割を要約している。「アルセニー・グリガは生涯を通じ て、ロシアとドイツの哲学的思考世界の架け橋であった」(920頁)。 マヤ・ソボレワ、2018年6月 |
| Bibliography Andreeva, Iskra S. “Filosofiia est’ tozhe poeziia: Arsenii Vladimirovich Gulyga (1921-1996).” Russkaia filosofiia vo vtoroi polovine XX veka. INION RAN, 1999, pp. 54-82. Dammaschke, Mischka and Wladislaw Hedeler. “Nekrolog auf einen Philosophen – Arsenij Wladimirowitsch Gulyga (21.4.1921-10.7.1996).” Deutsche Zeitschrift für Philosophie, vol. 44, no. 5, 1996, pp. 917-20. Gulyga, Arsenii. Chto takoe estetika?. Prosveshchenie, 1987. —. “Formula russkoi kul’tury.” Nash sovremennik, no. 4, 1992, pp. 142-49. —. Kant. Molodaia gvardiia, 1997. —. Nemetskaia klassicheskaia filosofiia. Mysl, 1986. —. “Polveka na Volkhonke.” Molodaia gvardiia, no. 4, 1997, pp: 160-220. —. Printsipy estetiki. Politizdat, 1987. —. Russkaia ideia i ee tvortsy. Soratnik, 1995. —. “Wir leben im Zeitalter des Kosmismus.” Deutsche Zeitschrift für Philosophie, vol. 40, no. 8, 1992, pp. 870-81. Rolf, George 1987. “The Lives of Kant.” Philosophy and Phenomenological Research, vol. 47, vo. 3, Mar., 1987, pp. 485-500. Zeman, Vladimir. 1986. Arseniy Gulyga. Immanuel Kant. Studies in Soviet Thought 31 (2):170-174. |
参考文献 Andreeva, Iskra S. 「哲学は詩でもある:アルセニー・ウラジーミロヴィチ・グリガ(1921-1996)」。『20世紀後半のロシア哲学』INION RAN、1999年、54-82ページ。 Dammaschke, Mischka and Wladislaw Hedeler. 「哲学者の追悼 – アルセニー・ウラジーミロヴィチ・グリガ(1921年4月21日-1996年7月10日)」『ドイツ哲学雑誌』第44巻第5号、1996年、917-20 ページ。 Gulyga, Arsenii. Chto takoe estetika?. Prosveshchenie, 1987. —. 「ロシア文化の公式」. Nash sovremennik, 第 4 号, 1992, pp. 142-49. —。カント。『モロダヤ・グヴァルディア』誌、1997年。 —。ドイツ古典哲学。『ミスル』誌、1986年。 —。「ヴォルホンケの半世紀」。『モロダヤ・グヴァルディア』誌、第4号、1997年、160-220ページ。 —. 『美学の原理』 Politizdat、1987年。 —. 『ロシアの思想とその創造者たち』 Soratnik、1995年。 —. 「我々はコスミズムの時代に生きている」 Deutsche Zeitschrift für Philosophie、第40巻、第8号、1992年、870-81ページ。 Rolf, George 1987. 「カントの生涯」 Philosophy and Phenomenological Research, vol. 47, vo. 3, Mar., 1987, pp. 485-500. ゼマン、ウラジミール。1986年。アルセニー・グリガ。イマヌエル・カント。『ソビエト思想研究』31 (2):170-174。 |
| Stolovich, Leonid Asmus, Valentin Averintsev, Sergei Cosmism Druskin, Yakov |
ストローヴィッチ、レオニード アスムス、ヴァレンティン アヴェリンツェフ、セルゲイ コスミズム ドルスキン、ヤコフ |
| https://filosofia.dickinson.edu/encyclopedia/gulyga-arseny/ |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099